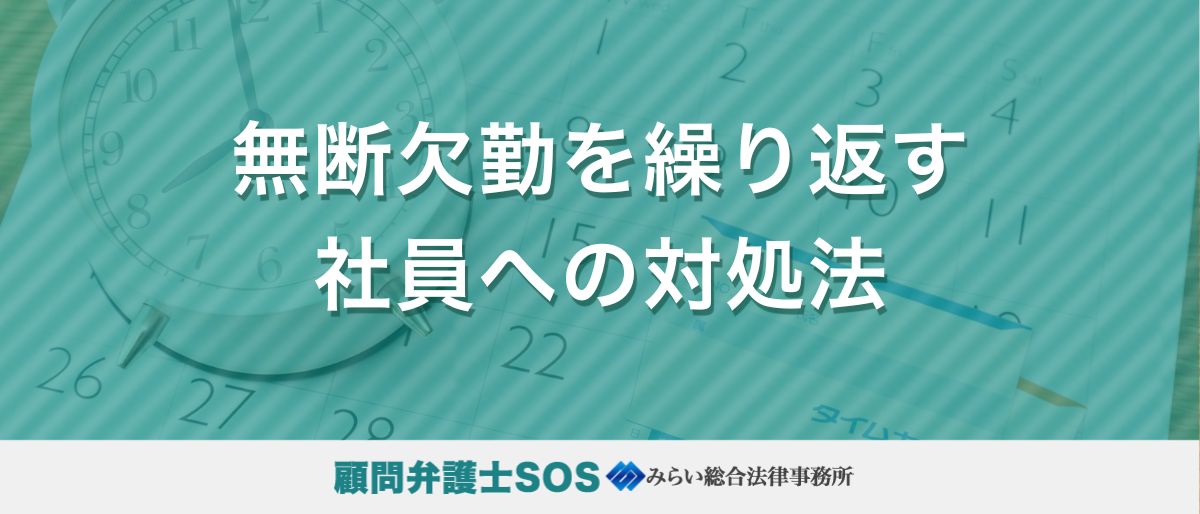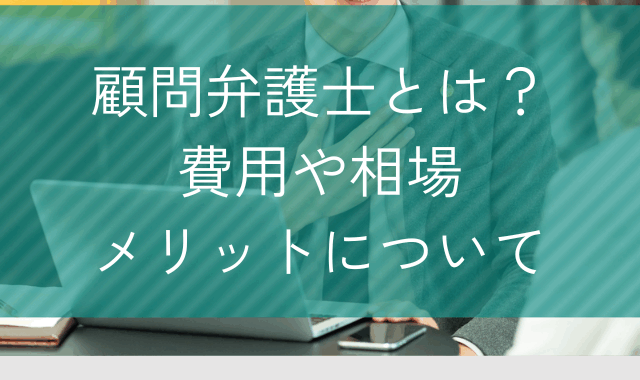無断欠勤を繰り返す社員への対処法
無断欠勤を繰り返す社員がいると、
- ・生産性が下がる
- ・他の社員から不満が噴出する
- ・社内秩序が乱れて他の社員の士気が下がる
といった問題などが起きて、会社の業務に大きな支障をきたす可能性があります。
そのため、会社としては早急に対応する必要があるのは言うまでもありません。
「社員が無断で会社に来なくなった」、「しかも連絡がとれない」といった状況が続く場合、最終的に会社としては退職扱いや解雇についても検討することになると思います。
しかしその場合、あとで従業員との間で訴訟トラブルに発展する可能性もあります。
実際、会社側が敗訴しているケースも少なくないですし、多額の金銭の支払いを命じられた判例もあります。
そこで、本記事では具体的な事例を交えながら、次のポイントを中心に解説していきます。
- ・無断欠勤をする社員への対応の内容と手順
- ・解雇に踏み切る際の手順と注意するべきポイント
- ・不当解雇と判断されてしまうポイント
- ・弁護士に相談・依頼するべき理由 など
目次
社員の無断欠勤とは?
その原因と対策で
知っておくべきこと
無断欠勤の定義と影響
無断欠勤とは、社員が事前の連絡なしに、勤務予定日に出勤しないことを指します。
これが繰り返されると、会社にとっては次のような影響が生じます。
- ・業務の停滞:欠勤者の業務をカバーする必要があり、他の社員の負担が増加する。
- ・職場の士気の低下:他の社員が不公平感を抱き、モチベーションが低下する可能性
- ・企業の信用低下:顧客対応やプロジェクト進行に影響が出ることで、企業の評価が下がる。
無断欠勤の原因と対応策
無断欠勤を繰り返す社員には、さまざまな理由が考えられます。
ここでは主な原因と対応策について考えてみます。
急な体調不良などの健康問題
<事例>
風邪や体調不良、ケガなどで突然出勤できなくなり、連絡が遅れるケース。
<対応策>
緊急時の連絡方法を明確にし、定期的な健康管理の重要性を社内で周知する。
メンタル不調や精神疾患
<事例>
精神的な不調から出社意欲が低下したり、うつ症状などのため欠勤。
<対応策>
メンタルヘルス相談窓口の設置や、業務負担の見直しを検討する。
家庭の事情による欠勤
<事例>
育児や介護など家庭の問題が突然発生し、事前連絡できないまま欠勤。
<対応策>
フレックスタイムやリモートワーク制度を導入し、柔軟な勤務形態を確保する。
職場でのトラブルや
ハラスメント
<事例>
上司や同僚などとのトラブル、パワハラ・セクハラなどの影響で出社を拒むケース。
<対応策>
ハラスメント相談窓口を設置し、適切な対応を企業として明確にする。
転職活動中の欠勤
<事例>
他社への転職活動を進めているが、会社へ伝えず面接などのために欠勤を続ける。
<対応策>
早めに退職意向を確認し、円滑な引継ぎできるよう調整する。
給与や待遇への不満
<事例>
給与や昇進の機会が少ないこと、人事異動や転勤などに不満を抱いた社員が欠勤を繰り返す。
<対応策>
透明性のある評価制度を確立し、さらに社員の成長機会を提供する。
業務過負荷による欠勤
<事例>
仕事量が多すぎるため社員が疲弊し、無断で欠勤する。
<対応策>
業務の割り振りを見直し、適正な労働環境を整備する。
人間関係の悪化
<事例>
職場やチーム内での対立や人間関係のストレスが影響し、職場へ行くことが困難になる。
<対応策>
社員間のコミュニケーション促進や、部署異動の選択肢を提供する。
長期的なモチベーション低下
<事例>
業務が単調などの理由でやりがいを感じられず、欠勤を繰り返す。
<対応策>
キャリア相談や研修プログラムを導入し、社員の成長機会を増やす。
退職準備のための欠勤
<事例>
社員がすでに退職の意思を固めているが、会社と話し合うことなく欠勤を続ける。
<対応策>
定期的な個別面談を実施し、退職時の円滑な対応を進める。
このように、無断欠勤が発生する理由はさまざまあります。
後ほど解説しますが、企業側が社員の状況を理解し、適切なルールと対応策を準備し、コミュニケーションを図っていくことで、問題を未然に防ぐことが可能です。
無断欠勤で起きるトラブル事例とその対応
無断欠勤をする社員への対応では、慎重な対応が求められます。
しかし、企業側の対応が適切でない場合、さらなる問題に発展することがあります。
ここでは、無断欠勤が引き金となって起きがちな、よくあるトラブル例とその対応について解説します。
社員が連絡を拒否する
無断欠勤した社員に連絡をしても電話に出ない、折り返しの連絡がない、メールの返信がないなど会社との接触を避けるケース。
- ・緊急連絡先(家族や身元保証人など)へ確認をする。
- ・書面による通知を送り、正式な対応を求める。
- ・勤務規則に基づき、複数回の連絡無視が続いた場合は懲戒処分を検討する。
無断欠勤の理由が不明確
「体調不良」、「家庭の事情」などの漠然とした理由を繰り返し、具体的な事情を話そうとしないケース。
- ・面談を実施し、問題を明確にする。
- ・健康上の理由であれば、診断書の提出を求める。
- ・業務負担が原因の場合は仕事の調整を提案する。
他の社員から不満が出る可能性
無断欠勤者の業務を他の社員が負担することなどが繰り返され、不満が募ることで職場の士気が低下する。
- ・欠勤者への適切な対応を社内で共有し、透明性を確保する。
- ・一時的な業務調整を行ない、負担を分散する。
- ・公平なルールを設け、無断欠勤者への処分を明確化する。
法的問題に発展する
会社が強制的な対応を取りすぎると、社員から「不当な処分を受けた」として訴えられるリスクがある。
- ・就業規則に基づいた処分を行なう。
- ・懲戒処分を決定する際は、弁護士など労働法の専門家に相談する。
- ・退職勧奨の際は、適切な説明と合意形成を重視する。
社員が突然退職する
無断欠勤が続いた後、突然退職届を提出し、仕事の引継ぎをしないまま退職するケース。
- ・できるだけ早い段階で面談を行ない、退職の意向を確認する。
- ・業務の引継ぎ手順を定め、退職時の混乱を防ぐ。
- ・退職届の提出ルールを明確化し、無断欠勤後の突然退職を予防する。
無断欠勤への対応は、ただ就業規則を当てはめるような対応ではなく、社員の心理状態や職場環境を考慮したバランスの取れた対応が求められます。
適切な対策を講じることで、トラブルを未然に防ぎ、職場の健全な運営を維持していくことが大切です。
無断欠勤を繰り返す社員に
どう対応するか?
無断欠勤を繰り返す社員に対しては、次のような手順で対応していきます。
無断欠勤の社員への具体的な
対応と手順
初期対応:迅速な状況確認と
対応
初期対応として、まずは欠勤が確認された時点で次のことを実行します。
- ・速やかに連絡を取る:メールや電話で本人と連絡をとり、欠勤の理由を確認する。
- ・職場の状況を把握する:他の社員への影響を考慮し、対応策を決定する。
- ・柔軟な対応を検討する:状況によっては、一時的なリモートワークなどを提案する。
面談による問題把握
無断欠勤が続く場合は社員と直接面談を行ない、問題の原因を探ります。
- ・ヒアリングの実施:欠勤の理由を聞き、解決策を模索する。
- ・健康面の確認:必要に応じて、医療機関の受診をすすめる。
- ・業務内容の見直し:負担の軽減や業務調整を行なう。
規則の明確化と指導
企業の規則を明確化することで、無断欠勤の問題の予防や改善に取り組みます。
- ・就業規則の確認:社内規則を周知し、欠勤時の報告ルールを強化する。
- ・警告の実施:欠勤が続く場合、正式な警告を発行する。
- ・改善計画の提示:問題解決のための具体的な改善策を社員と共有する。
最終措置: 契約の見直し
改善が見られない場合は、最終的な措置として雇用契約の見直しを検討します。
- ・懲戒処分の検討:状況に応じて、減給や降格などの処分を実施。
- ・退職勧奨:問題が継続する場合、退職勧奨を行なう。
- ・解雇の決定:最終的には、就業規則に基づき解雇手続きを進める。
会社から連絡を入れる際の
メール例文と注意ポイント
無断欠勤をしている社員に対して、まずは次のような内容のメールを送るのがいいでしょう。
件名: 【重要】無断欠勤についてのご連絡
〇〇様
お疲れ様です。人事部の〇〇です。
最近、事前の連絡なく欠勤される状況が続いておりますが、ご自身の体調やご家庭の事情など、何かお困りのことがございましたら、ぜひご相談ください。
業務の円滑な進行のため、欠勤される場合は事前の連絡をいただくことが必要です。
無断欠勤が続きますと、業務への影響が大きくなり、規則に基づいた対応を検討せざるを得なくなります。
まずは一度、お話を伺えればと思いますので、ご都合の良い日時をお知らせください。
適切なサポートができるよう、会社としても柔軟に対応を検討いたします。
お手数ですが、〇〇日までにご返信いただけますようお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
〇〇(部署名・名前)
〇〇株式会社
このようなメールでは、社員に対して注意喚起をしつつも、強制的なトーンにならないよう配慮します。
状況に応じて、より厳しく通知することもできますが、まずは話し合いの機会を設けることが重要です。
無断欠勤の社員と話す際の
効果的な対応について
無断欠勤の社員と対話する際は、叱責するのではなく、原因を探りながら改善策を見出すことが重要なポイントになります。
次のような対応を意識しながら、社員との建設的な話し合いを行なっていくことが大切です。
冷静で落ち着いた態度を保つ
感情的にならず、落ち着いた口調で話すことで社員が心を開きやすくなります。
厳しい指摘をする場合でも威圧的な態度は避け、ともに解決策を探す姿勢を示すことが大切です。
事実を伝え、影響を説明する
無断欠勤の状況と、それが業務や周囲におよぼす影響を具体的に説明します。
たとえば、「〇〇さんの欠勤により、△△の業務が滞ってしまい、他の社員の負担が増えている」と客観的な事実を伝えることで、問題の重要性を理解してもらいます。
理由を丁寧に聞く
「何か困っていることはありますか?」や「最近の状況について教えてもらえますか?」といった質問をして、社員が話しやすい環境を作ります。
体調不良や家庭の事情など、欠勤の背景を正しく理解することが必要です。
解決策を共に考える
欠勤の理由に応じて、可能な対策を提案します。
- ・健康上の問題:医療機関の受診をすすめ、必要なら休職制度を案内する
- ・家庭の事情:フレックスタイムやリモートワークの活用を検討。
- ・業務負担の問題:仕事の割り振りを見直し、負担を軽減。
ルールの明確化と今後の期待を伝える
無断欠勤が続くことは、会社の業務に支障をきたすことになるため、就業規則を再確認することも必要です。
たとえば、「今後、欠勤時には必ず連絡をお願いしたいです」など、具体的な期待を伝えることで改善のきっかけを作ることができます。
フォローアップの実施
継続的な対話が、長期的な改善につながります。
話し合い後も定期的に社員の様子をチェックし、必要に応じて追加のサポートを提供しながらケースに応じて、アプローチを調整しながら進めていきます。
無断欠勤の社員と前向きな関係を築きながら、問題解決に向かっていくことが大切です。
その他の対応について
手紙や内容証明の送付
メールなどで返信が来ない場合、手紙を送付することも選択肢になります。
その場合、相手の受け取りを確認できる内容証明郵便も検討します。
自宅訪問
相手からのレスポンスがない場合は自宅への訪問も検討します。
職場でのハラスメント行為が原因の場合なども含め、トラブルの当事者が訪問するようなことは避けるべきです。
また、郵便受けの中や洗濯物、電気メーター、ガスメーター、水道メーターなどを確認したり、場合によっては賃貸物件の管理会社等に状況確認をします。
家族や身元保証人への連絡/
警察への連絡
自宅訪問でも在宅の有無が確認できない場合、無断欠勤の社員の家族や身元保証人など緊急連絡先へ連絡をします。
ここでも連絡が取れない場合は、警察への連絡も検討するのがいいでしょう。
会社が取るべき無断欠勤の防止策
社内ルールの明確化と周知
労働基準法の第106条1項では、使用者は労働者に対して就業規則を周知する義務があることを規定しています。
会社が社員の無断欠勤を防止するためには、明確な定義と社内ルールを設けて就業規則などで規定し、社員に周知しておくことが重要です。
<就業規則の明示例>
第1条:無断欠勤の定義
- 1. 無断欠勤とは、事前連絡なく勤務予定日に出勤しない行為を指す。
- 2. 連絡の遅れも含め、勤務開始時刻から〇時間以内に会社へ連絡がない場合は、無断欠勤とみなす。
第2条:欠勤時の報告義務
- 1. 欠勤の際は、勤務開始前の〇時間前までに上司または人事部へ連絡を行なうこと。
- 2. 連絡手段は、電話・メール・社内チャットツールのいずれかを使用する。
第3条:無断欠勤が発生した際の対応
- 1. 無断欠勤が確認された場合、速やかに本人へ連絡し、状況を確認する。
- 2. 連絡がつかない場合は緊急連絡先へ確認を行なう。
- 3. 〇日以上無断欠勤が続いた場合、正式な警告書を発行する。
第4条:懲戒処分の基準
1. 無断欠勤が〇回以上繰り返された場合、以下の処分を検討する。
- ・口頭注意
- ・文書による警告
- ・減給・賞与減額
- ・降格処分
- ・就業規則に基づく懲戒処分(最悪の場合、解雇)
第5条:相談・改善のための措置
- 1. 無断欠勤者には、状況を改善するために個別面談を実施する。
- 2. 健康面や家庭の事情など特別な理由がある場合は、必要に応じて勤務形態の見直しを検討する。
このようなルールを明確に定めておくことで、無断欠勤への対応を体系化し、公平な処置が可能になります。
なお、条文については企業文化や業務内容に応じて、柔軟に改訂など行なうといいでしょう。
会社側の社員に対する対応義務に注意
労働契約法では、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と規定しています(第5条)。
そのため、無断欠勤が続く場合は、まず社員の健康状態や家庭の事情を確認する努力が必要です。
また、一方的な懲戒処分や解雇を行なう前に面談や通知を行ない、状況の改善を促す教育や指導などのプロセスを経ることが推奨されます。
会社が、こうした手順を踏まないと従業員の無断欠勤を認めることになってしまいますし、たとえば懲戒解雇後に元社員から不当解雇で訴えられた場合などに備える必要もあります。
教育や指導を行なった記録を書面やメールなどに残しておくことも必要です。
会社が取ることができる最終的な
措置と注意ポイント
教育や指導を行なっても無断欠勤が改善されない場合は、懲戒処分や解雇などを検討する必要があります。
懲戒処分
会社が社員の就業規則違反や企業秩序違反行為に対して課す制裁罰(不利益処分)を「懲戒処分」といいます。
一般的に、懲戒処分には軽いものから順に次のものがあります。
- ・けん責、戒告
- ・減給
- ・降格
- ・出勤停止
- ・論旨解雇
- ・懲戒解雇 など
通常、懲戒処分が有効になる要件としては次のことがあげられます。
- ・就業規則に懲戒事由と懲戒の種類が定められている。
- ・就業規則の懲戒事由に該当する事実がある。
- ・懲戒処分の種類や量定が社会通念上相当である(重すぎない)。
- ・懲戒処分の適正な手続きを経ている。
無断欠勤が「業務の円滑な遂行を著しく妨げる」と判断された場合、減給・降格・解雇などの処分が可能ですが、そこに至るまでに合理的な手続きが求められます。
たとえば、次のようなケースでは懲戒処分が無効とされた判例があるので注意が必要です。
- ・就業規則などに規定がない
- ・直接の面談がなかった
- ・社員に弁明の機会を与えなかった
- ・2、3日の無断欠勤での懲戒解雇 など
退職勧奨
懲戒処分を実施しても無断欠勤が続き、改善されないような場合は「退職勧奨」を行なうという選択肢もあります。
会社が社員を説得して退職を促し、合意を得たうえで解約あるいは辞職としての退職をさせることを退職勧奨といいます。
解雇とは違い、社員の同意のうえなので法的なリスクが少ないという利点があります。
ただし、退職するかどうかは社員の自由意思であるため、会社が強制した場合は不当な退職強要として違法と判断される可能性が高いといえます。
解雇
会社が最終的に下す懲戒処分のうち、もっとも重いものは解雇になります。
ただし、無断欠勤が続いても直ちに社員を解雇できるわけではないことに注意が必要です。
第16条(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
つまり、会社が無断欠勤を続ける社員を解雇するには、「客観的、合理的な理由」と「社会通念上、相当であると認められる理由」が必要で、これを「解雇権濫用法理」といいます。
- ・無断欠勤の理由や悪質性
- ・無断欠勤の回数や期間
- ・欠勤が業務に与えた影響
- ・企業からの注意指導、社員の改善の見込みの有無
- ・これまでの類似事案における企業の取扱いなどの対応 など
なお、心身の故障による解雇が有効とされるための理由は限定的で、次の場合などがあります。
- ・心身の故障の程度が、雇用の目的を達成することができないといえる程度にまで達している場合。
- ・治療によっても回復する可能性がない場合。
普通解雇と懲戒解雇の
違いについて
普通解雇
- ・従業員による債務不履行(約束違反)を理由に雇用契約を終了させるものです。
- ・通常、2週間以上連続で無断欠勤が続いていて、本人との連絡が取れない場合が普通解雇が認められる目安になっています。
1週間程度の無断欠勤の場合は不当解雇と判断している裁判例がほとんどだといえます。 - ・ただし、「無断欠勤の原因がハラスメントなど職場環境にある場合」や「従業員の精神疾患が無断欠勤の原因になっている場合」は、2週間以上無断欠勤があっても、解雇が無効(不当解雇)と判断されることがあるので注意が必要です。
- ・就業規則に根拠となる規定がなくても、民法627条に基づき普通解雇することができます
懲戒解雇
- ・懲戒解雇:重大な企業秩序違反を犯した従業員に対し制裁として行なうものです。
- ・懲戒解雇とするためには、就業規則に定められた懲戒事由に該当する必要があります。
- ・懲戒解雇はもっとも重い懲戒処分であること、普通解雇に比べ懲戒解雇の要件は厳格であることなどから、裁判に発展するリスクが高いといえます。
- ・半年間に24回の遅刻と14回の欠勤(1回を除きすべて事前の届け出なし)をし、再三の注意や警告にも関わらず改善されなかったことを理由とする懲戒解雇が有効とされている裁判例があります(東京プレス工業事件 横浜地判 昭和57年2月25日)。
無断欠勤を続ける社員を
解雇する場合の手順
解雇を検討する際は事前の警告や指導を行ない、解雇理由を明確にしておくことが重要です。
<解雇する場合の手順>
①出社命令を出す
社員が出社に応じたら、会社としては無断欠勤の原因の確認、解雇の要件である「客観的かつ合理的な理由」を明らかにする必要があります。
②解雇予告をする
解雇する場合、遅くとも30日前までに社員に解雇予告を行ないます。
30日以上前に解雇予告を行わずに従業員を解雇する場合は、解雇予告手当を支払う必要があります。
③解雇通知書を送付する
解雇予告から一定期間が経過したなら解雇通知書を送付します。
解雇通知書は確実に従業員本人に届ける必要があるため、内容証明郵便などで送付します。
繰り返しになりますが、社員を解雇する場合は、次のポイントに注意してください。
- ・無断欠勤の事実を証明する証拠(タイムカードなどの勤怠データ)が必要。
- ・パワハラやセクハラなど会社側に原因がある場合や精神疾患がある場合、安易な解雇は「解雇権濫用」と判断される可能性が高い。
- ・適切な手順で解雇しなかった場合、不当解雇とみなされる可能性が高い。
社員の無断欠勤の問題は
弁護士に相談してください!
会社としては無断欠勤を続ける社員に対して制裁を加えたい、といった感情もあるかもしれません。
しかし、ここまでお話ししてきたように、安易に懲戒処分や解雇をしてしまうと、社員から訴えられてしまう可能性があります。
そのため、無断欠勤の問題が発生した場合はできるだけ早急に、労務問題に強い弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。
弁護士法人みらい総合法律事務所は全国対応で、随時、無料相談を行なっています(事案によりますので、お問い合わせください)。
顧問弁護士についてのご相談も、いつでもお受けしていますので、まずは一度、気軽にご連絡ください。