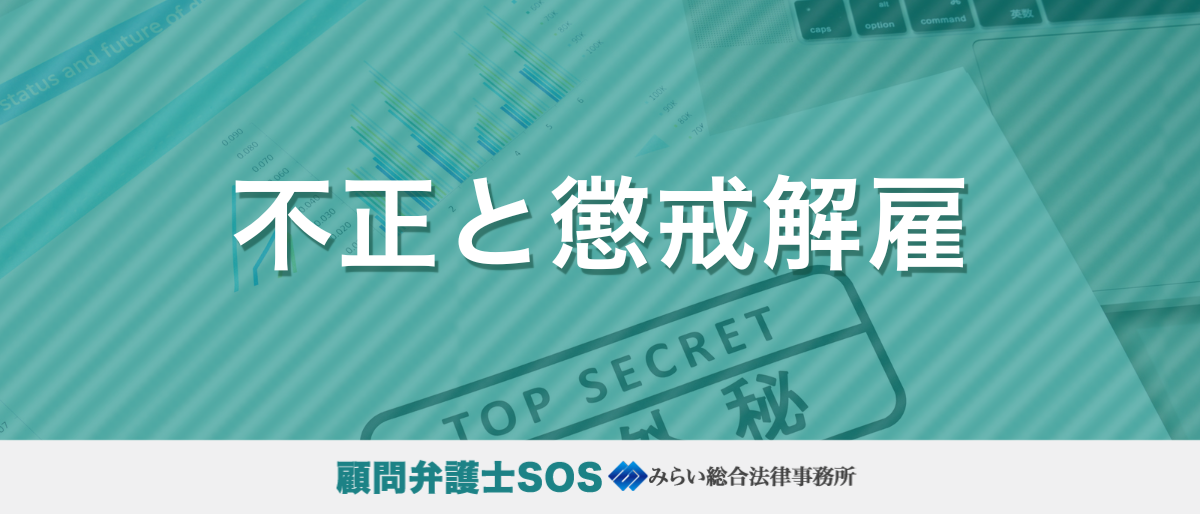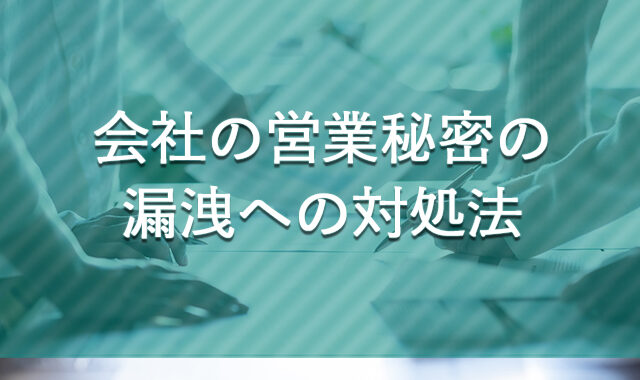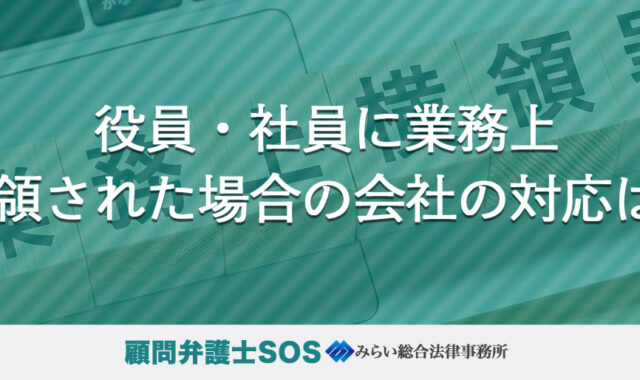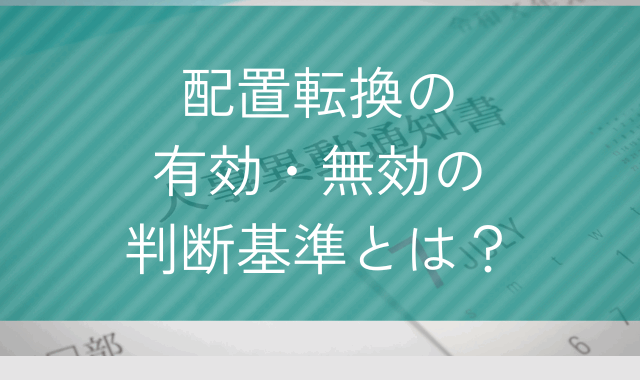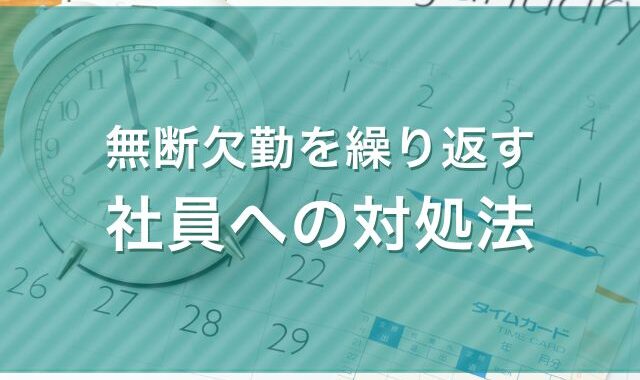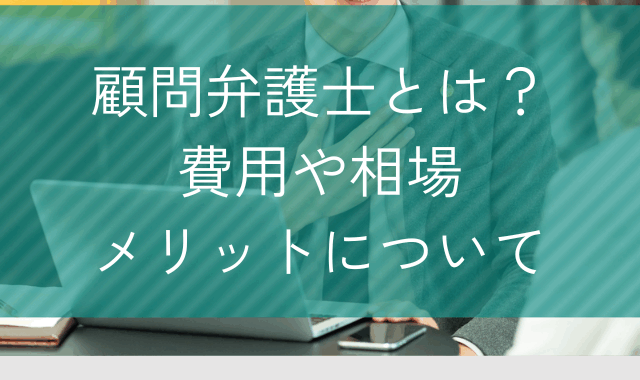不正と懲戒解雇
会社経営者や役員、人事担当者で、こんな事案に遭遇したことがある、もしくは現在進行形で対応しているという方もいらっしゃるかもしれません。
「依願退職をした元従業員に、あとから不正行為の事実が判明した……これから懲戒解雇処分を下すことはできるのだろうか?」
「懲戒処分の決定手続や不正行為の調査に時間を要している間に、対象の従業員が退職届を提出してしまった……懲戒解雇処分は間に合うのか?」
まず、懲戒解雇が有効となるためには、「就業規則に規定があること」、「当該就業規則が全従業員に周知されていること」「その内容が合理的であること」、「解雇権の濫用と判断されないように適切な手続きが行なわれていること」などが必要です。
そのうえで、懲戒解雇が可能かの検討に入りますが、この場合、退職届が提出されてから退職の効果が生じる期間は2週間(14日間)になることを覚えておいてください。
つまり、2週間のうちに検討して処分を下せるかがポイントになります。
なお、退職金の不支給・減額・返還請求は可能ですが、その従業員に強い不正・背信行為があり、それを会社側が証明する必要があります。
本記事では従業員の退職と懲戒解雇の問題について、次の項目を法的に解説していきます。
- ・懲戒処分の概要と種類
- ・懲戒解雇の概要と条件
- ・退職後の懲戒解雇は可能か?
- ・退職金の不支給・減額・返還は法的に
問題ないか? - ・懲戒解雇処分で会社が注意するべき
ポイント など
懲戒解雇は法的リスクが高いため、慎重な対応が求められます。
ぜひ最後まで読んでいただき、適切な対処をしていきましょう。
目次
懲戒処分の概要と種類について
懲戒処分とは?
使用者(会社)が、労働者(従業員)に対して行なう労働関係上の不利益措置のうち、企業秩序違反に対する制裁罰を「懲戒処分」といいます。
懲戒処分となる従業員の行為としては、「経歴詐称(さしょう)」、「職務懈怠(かいたい、けたい)」、「業務命令違背(いはい)」、「業務妨害」、「職場規律違反」、「従業員たる地位・身分にともなう規律違反」などがあげられます。
※懈怠 = ある義務を怠ること。
※違背 = 規則・法令・命令などに背くこと。
懲戒処分の種類
懲戒処分は軽いものから次のような種類があります。
- ・けん責・戒告
文書や口頭による注意。始末書の提出を求める場合もある。 - ・減給
賃金の一部を差し引くもの。ただし、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない
(労働基準法第91条)。 - ・降格
職位や等級を引き下げる。 - ・出勤停止
一定期間の就労禁止。その間の給与は支給されない。 - ・諭旨解雇
退職勧奨などにより自主退職を促す。応じなければ懲戒解雇へ。 - ・懲戒解雇
即時解雇となり退職金不支給や減額が一般的。
つまり、もっとも重い処分が「懲戒解雇」になります。
会社が懲戒解雇をできるケースを
確認
懲戒解雇とは?
懲戒解雇は、企業秩序違反の中でも重大な不正行為(横領、情報漏洩、暴力行為など)に対して科される、もっとも重い処分です。
懲戒として会社が労働契約を一方的に解消するもので、通常は解雇予告も予告手当もなしに即時になされ、就業規則等によって退職金の全部または一部が支給されないという処分になります。
懲戒解雇事由について
懲戒解雇の理由となる従業員の行為としては、次のことなどがあげられます。
経歴詐称
経歴詐称で従業員の懲戒解雇を行なうためには、その経歴詐称が採否の決定に重大な影響を及ぼすものである必要があるとされます。
裁判例では、「重大な経歴詐称といえるか否かについては、企業の種類、性格に照らして、詐称の事実が事前に発覚すれば、その者を雇用しなかったであろうと考えられ、客観的にもそのように認められるのが相当であるかによって決定される」としたものがあります。
(弁天交通事件 名古屋高判昭和51年12月23日)
なお、この裁判例では、従業員が職歴を詐称したことを理由とした懲戒解雇を有効としています。
ただし、重大な経歴詐称でない場合、懲戒解雇は権利の濫用として無効と判断される可能性があることに注意が必要です。
業務上の横領・着服
業務上横領については、金額や回数が多いか少ないかに関わらず、懲戒解雇が有効になる可能性が高いですが、無効になる可能性も想定して慎重に進めることが必要です。
特に、金融・経理担当者など業務の性格上、金銭的な規律を遵守することが強く要求される者が横領した場合には、一般的には懲戒解雇は妥当といえます。
裁判例には次のものがあります。
(大阪地判平成10年1月28日)
バス料金3,800円の着服行為に対する懲戒解雇を有効とした。
(長野地判平成7年3月23日)
一方、通勤手当の不正受給は業務上横領には該当しないという裁判例もあります。
しかしながら、不正受給の動機、額(合計34万円余り)などの事情に照らせば、懲戒解雇は重すぎるとして、解雇権濫用により懲戒解雇を無効とした。
(光輪モーターズ事件
東京地判平成18年2月7日)
そのため、会社としては不正受給をした経緯や動機を検討し、悪質性が高いと判断できるような場合にのみ懲戒解雇ができると考えます。
配置転換命令拒否
従業員が配置転換(配転)命令を拒否することは重大な業務違反となります。
会社としては、こうした事実を許容すると、その後の企業組織の維持にも影響を及ぼしかねません。
そのため、配転命令拒否を理由とした懲戒解雇は有効と判断される傾向にあります。
裁判例には次のものがあります。
(東亜ペイント事件
最二小判昭和61年7月14日)
(メレスグリオ事件
東京高判平成12年11月29日)
ただし、安易に懲戒解雇とすると、解雇権の濫用と判断される場合もあります。
会社としては、従業員への説得などの努力をする必要があります。
軽微な違反の繰り返し
無断欠勤や遅刻、勤務成績不良、仕事上のミスなどは軽微な労働提供義務違反として、軽い懲戒処分の対象になります。
しかし、何度も注意・指導しても改善されず繰り返す、反省が感じられない、反抗的な態度を取るといったケースでは懲戒解雇になり得るでしょう。
(東京プレス工業事件
横浜地判昭和57年2月25日)
その他
機密情報の漏洩、長期無断欠勤(概ね14日以上)、社外での犯罪行為なども懲戒解雇の理由になり得ます。
懲戒解雇が有効とされる
条件について
会社が従業員の懲戒解雇を実施し、それが有効とされるには次の条件を満たす必要があります。
- ①正当性がある
就業規則に懲戒解雇事由が明記されており、就業規則が従業員に周知されていること。 - ②合理性がある
処分が社会通念上相当であること。 - ③整合性がある
過去の処分との整合性などがあること。 - ④適正な手続きを踏んでいる
事実確認や証拠の収集などがなされていること。 - ⑤権利の濫用に当たらない
本人に弁明の機会が与えられている、指導・教育などがされていること。 - ⑥二重処罰になっていない
同一事由に対して複数の処分を科していないこと(二重処罰の禁止)。
第15条(懲戒)
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
第16条(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
退職後の従業員でも
会社が懲戒解雇をしたい理由とは?
依願退職をした元従業員、あるいは既に退職届を提出していて手続き待ち状況の従業員に不正があったことが後から発覚した場合に、会社が懲戒解雇をしたいと考える目的・理由には次のようなものがあります。
- 企業秩序の維持
不正行為を放置してしまうと社内の規律が崩れてしまうため、厳罰を科したい。 - 他の従業員への周知徹底
厳正な対応を示すことで従業員に周知徹底し、不正行為の再発防止につなげるため。 - 退職金の不支給・減額・返還請求
懲戒解雇であれば退職金を支払わずに済む可能性があるため。 - 社外への説明責任
株主や顧客などのステークホルダーに対しても適切な対応をしていることを示す必要があるため。
たとえば、元経理担当者が退職後に帳簿の不正操作や横領をしていたことが発覚した場合、会社としては懲戒解雇の処分を下すことで、退職金の支払いを回避し、社内外に厳正な姿勢を示したいと考えるのは自然だといえます。
退職後の元従業員の懲戒解雇は
可能なのか?
では実際、退職済みの元従業員に懲戒解雇の処分を下すことは可能なのか、確認ポイントなどを見ながら検討していきましょう。
退職届の提出から
2週間以内なら懲戒解雇は可能
退職届の提出 = 即退職とはなりません。
第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
法律上、従業員が退職届を提出してから2週間後に雇用契約の解約が成立します。
たとえ会社が退職届の受理を保留しても、労働者の意思表示が会社に到達した時点から2週間で契約は終了するわけです。
つまり、この2週間(14日)の間に従業員に対して懲戒処分を通知できれば、懲戒解雇にすることができます。
退職をしてしまっている場合
には懲戒解雇はできない!?
では、すでに退職してしまっている元従業員に対して懲戒解雇処分を科すことはできるのでしょうか。
- ・退職届を提出してから2週間経過した後
- ・不正を知らずに、会社が従業員の退職を承認し、合意解約が成立してしまった後
このような場合は、その時点で雇用契約が終了しているので、退職後に不正が発覚したとしても、原則として懲戒解雇できません。
そもそも、雇用関係にない者を解雇するということは意味のないことになるからです。
懲戒処分は難しくても
会社が対応可能な処分について
退職後、不正が発覚した元従業員を懲戒解雇などにできなくても、会社として何らかの処分を下したい場合、どのような対応ができるのかを考えてみます。
退職金の不支給・減額・
返還請求は可能か?
退職した元従業員に処分を下したいという会社側の目的の一つが、退職金に関係する場合、「退職金の不支給・減額」や「支払い済みの退職金の返還」は可能でしょうか。
原則として、退職後に不正が発覚した元従業員を懲戒解雇できないことと、退職金支給とは別の問題です
また、退職以前に懲戒解雇にしたからといって、退職金の不支給は、いつでも認められるわけではありません。
その従業員が、それまでの勤続による会社への功労を無にさせるほどの強い背信行為をした場合などでは不支給にできる可能性があります。
裁判例には次のようなものがあります。
(ピアス事件 大阪地判平成21年3月20日)
(ソフトウェア興業事件
東京地判平成23年5月12日)
懲戒処分に該当する行為を
行なったことを
社内外に公表する場合は?
退職後に不正が発覚した元従業員について、社内外に公表することに関しては、社内的な記録に懲戒解雇相当などとして残すことは可能であると考えます。
しかし、社外にもあわせて公表することは、公表の必要性や、内容の真偽、表現方法、公表範囲、当該従業員の名誉、信用に対する配慮などが必要だと考えます。
場合によっては、当該従業員から名誉毀損として慰謝料を請求される可能性もあるので注意が必要です。
従業員の懲戒解雇で
会社が注意するべきポイントまとめ
退職の効力発生日を確認/
懲戒処分の決定は迅速に行なう
前述したように、退職届の提出=即時退職ではありません。
退職届は提出後、2週間(14日間)経過後に効力が発生することに注意が必要です。
そのため、会社が承認して退職日が確定するまでの間に懲戒処分を通知できれば、有効とされる可能性があります。
懲戒処分の事由が退職前に
発生していたか確認
退職により、会社と従業員の労働契約は終了しているため、懲戒権は消滅し、退職後の懲戒処分は原則不可です。
しかしながら、従業員の不正行為が退職後に発覚したとしても、行為自体が在職中であれば損害賠償請求ができる可能性があります。
証拠の確保
処分の正当性を担保するために、不正行為の証拠を確保し、退職届なども保管しておく必要があります。
退職日の延期も検討する
調査中に退職された場合の対応策としては、本人の同意をとったうえで退職日を延長し、調査期間を確保することも検討するといいでしょう。
就業規則や退職金規程の整備
懲戒解雇ができない場合でも、就業規則や退職金規程に「懲戒解雇された場合は退職金を不支給・減額することができる」と明記していれば、退職金の支払いを制限できる可能性があります。
退職後の損害賠償請求も検討
不正行為によって会社に損害が生じた場合、従業員の退職後でも、会社は民事上の損害賠償請求ができます。
懲戒処分でお困りの場合は
弁護士に相談を!
従業員(元従業員)の不正行為対しては、企業としての毅然とした対応と、法的リスクへの慎重な判断が必要になります。
懲戒解雇は、前述のとおり懲戒処分の中でもっとも重く、労働者に大きな不利益を与えるものです。
そのため、裁判所から解雇権濫用の判断を受けるか否かは、普通解雇の場合よりも厳しく審査されることになります。
また、就業規則や退職金規程は内容に不備等がないか、改訂するべきかなど、リーガルチェックも欠かせません。
懲戒解雇などの処分でお困りの場合は、迅速に対応していくためにも労務問題に強い弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。
弁護士法人みらい総合法律事務所は全国対応で、随時、無料相談を行なっています(事案によりますので、お問い合わせください)。
顧問弁護士についてのご相談も、いつでもお受けしていますので、まずは一度、気軽にご連絡ください。