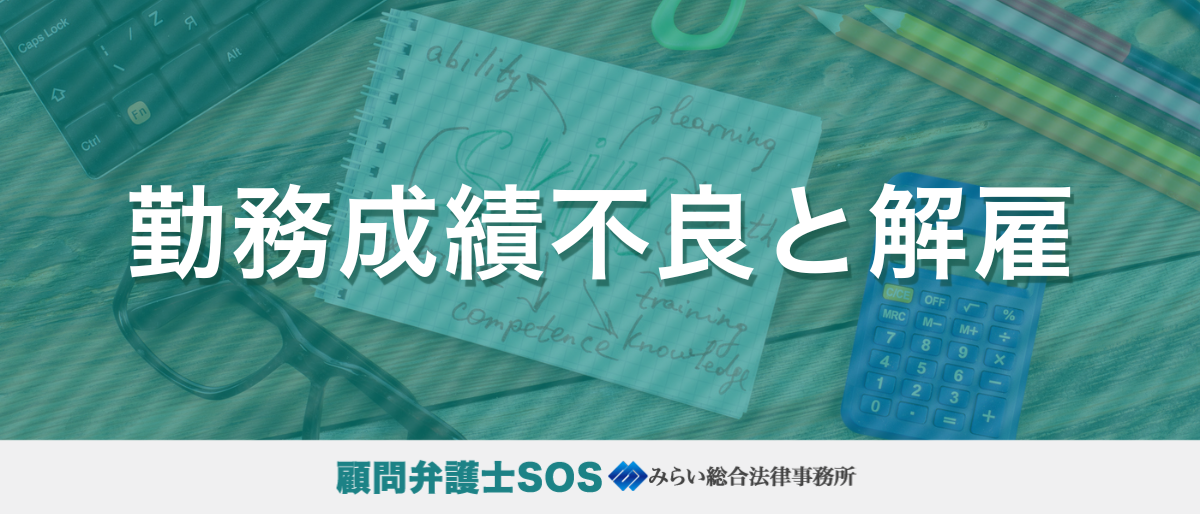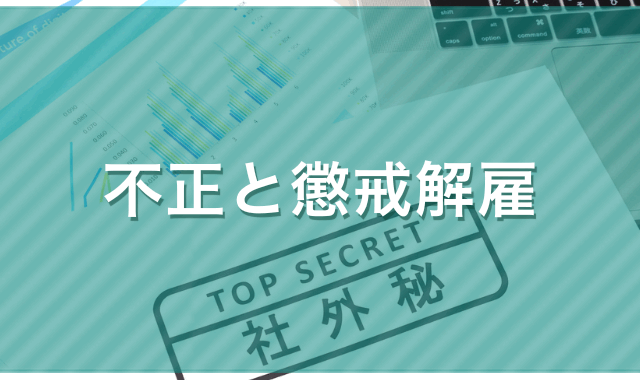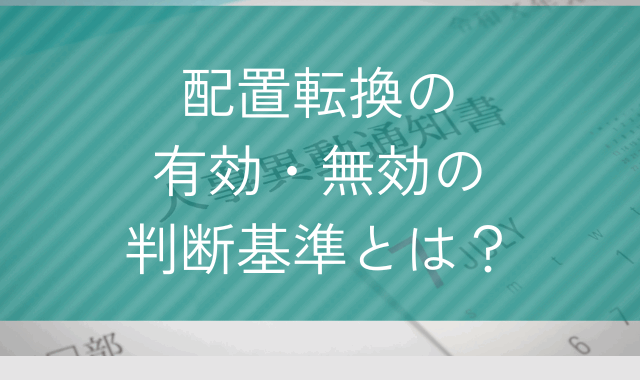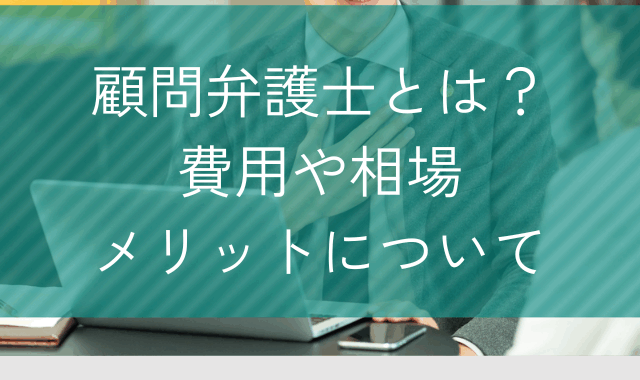勤務成績不良と解雇
勤務成績がよくない、能力不足、といった従業員は会社にとっては戦力にならず、また周囲の従業員への悪影響なども考慮すると、辞めてほしいと考えることもあるでしょう。
では、そうした従業員を解雇することはできるのでしょうか?
解雇すること自体は可能です。
しかし、解雇するとなると従業員の人生にも関わることなので、会社としては慎重に判断して、適切な対応をとる必要があります。
安易な解雇には労働トラブルに
発展するリスクが潜んでいます。
従業員側が「不当解雇」として提訴した場合、裁判では解雇が認められないと判断される可能性もあります。
解雇が認められるためには
条件があります。
- ・客観的・合理的な理由があり、
社会通念上相当であると判断され、
解雇権の濫用と認められないこと。 - ・勤務成績不良・能力不足の基準、
理由が明確であること。 - ・会社が、改善のための教育や指導、
配置転換などで解雇回避の努力を
行なったこと。
こうした条件、基準などを満たしていない場合、「解雇権の濫用」として解雇は無効とされる可能性が高くなります。
解雇が無効とされると
金銭の支払いリスクが
発生します。
裁判で解雇は無効と判断されると、従業員を解雇してから復職するまでの賃金や、慰謝料などの損害賠償金を支払わなければならなくなります。
本記事では、こうした内容を踏まえながら、勤務成績不良・能力不足の従業員の解雇問題について解説していきます。
目次
解雇とは?/基本的な知識を解説
解雇とは、企業(使用者)が従業員(労働者)との労働契約を一方的に終了(解約)させることをいいます。
なお、従業員からの労働契約の解約は、自己都合による退職になります。
解雇は法律によって制限されているため、簡単にできるものではないことをまずは知っておく必要があります。
なぜなら、解雇は従業員の生活に直結する重い処分であり、その影響は重大なものになる可能性が高いからです
解雇について、法的には次のように規定されています。
第16条(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
条文からも、解雇が認められるための前提条件としては次の2点があげられるわけです。
- ・客観的、合理的な理由があること
- ・社会通念上相当であること
解雇の種類は?/
基本的な4つの解雇について
解雇には、必要な条件や会社側の目的の違いなどにより次の4つの種類があります。
普通解雇
次のような従業員側の事情を理由として、労働契約の継続が困難な場合に行なう解雇です。
- ・従業員の勤務成績不良や能力不足
- ・心身の故障(病気や障害など)による
健康問題 - ・勤怠不良、協調性の欠如 など
整理解雇
経営悪化など、企業側の事情による人員削減のための解雇です。
懲戒解雇
企業秩序違反の中でも重大な不正行為、たとえば横領、情報漏洩、暴力行為などに対して科される、もっとも重い処分としての解雇です。
懲戒として会社が労働契約を一方的に解消するもので、通常は解雇予告も予告手当もなしに即時になされます。
就業規則等によって退職金の全部または一部が支給されないという処分になります。
諭旨解雇
懲戒解雇に相当する事由があるものの、従業員の反省の度合いや、これまでの功績などを考慮して、処分を軽減した解雇です。
一般的には、退職勧奨などで従業員に退職届の提出を促しますが、拒否された場合は解雇に切り替えます。
なお、退職金の不支給については、一部に限定する場合が多いといえます。
勤務成績不良や能力不足を理由に
従業員を解雇できるのか?
解雇が有効か否かの
判断材料について
従業員の解雇については、まず「就業規則」が重要になります。
就業規則とは、賃金や労働時間などの労働条件の詳細、職場の規律や労働者が就業上守るべきルールなどを定めた規則のことです。
【参考資料】:就業規則を作成しましょう(厚生労働省)
多くの企業では、就業規則に「勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等、就業に適さないと認められたとき」などと規定して、勤務成績不良や能力不足などを理由とした解雇を想定していると思います。
しかし、長期的な雇用が慣行となっている現状では、解雇は従業員に重大な不利益を負わせるものであるため、前述のように労働契約法第16条では、「客観的に合理的な理由を欠き」、「社会通念上相当であると認められない」場合は、その権利を濫用したものとして無効とするとして、解雇権の濫用を規制しています。
そのため、勤務成績不良や能力不足などを理由とした解雇が有効か否かについては、
- ①勤務成績不良などの程度や原因
- ②改善の余地はあるか
- ③企業による指導・教育などが
十分になされたか - ④配置転換など解雇を回避する措置を
尽くしたか
など個別具体的な事情を検討して判断されることになります。
起こりがちな労働トラブルの例
勤務成績不良や能力不足を理由とした解雇では、次のような労働トラブルが発生する可能性があります。
不当解雇
解雇理由が解雇要件を満たさない、手続き不備、改善の機会を与えなかった場合など。
退職強要
追い出し部屋など、自主退職を装った圧力をかけた場合など。
配置転換の濫用
解雇を目的の不当な異動命令を出した場合など。
評価制度の不備
主観的判断や相対評価などによるトラブルなど。
勤務成績不良や能力不足が争われた裁判例
次に、勤務成績不良や能力不足が争われた裁判例について紹介します。
解雇が無効と判断された裁判例
裁判例①:
セガ・エンタープライゼス事件
(東京地判 平成11年10月15日)
上司からの注意や顧客からの苦情が多く、勤務成績が悪い、仕事に対する積極性がない、協調性がないなどの理由から大学院卒の従業員を解雇した事案。
また、人事考課は相対評価であって絶対評価ではないから、その評価が低いからといって直ちに労働能力が著しく劣り、向上の見込みがないとまでいうことはできないとした。
そして、会社としては当該従業員に対し、さらに体系的な教育、指導を実施することによって、その労働効率の向上を図る余地もあるとして、解雇を無効とした。
裁判例②:エース損害保険事件
(東京地判 平成13年8月10日)
長期雇用してきた正規従業員を勤務成績や勤務態度の不良を理由として解雇した事案。
かつ、その他、是正のため注意し、反省を促したにも関わらず改善されないなど今後の改善の見込みもないこと、使用者の不当な人事により労働者の反発を招いたなどの労働者に宥恕(ゆうじょ)すべき事情がないこと、配転や降格ができない企業事情があること、なども考慮して濫用の有無を判断すべきであるとして、本件の解雇は解雇権濫用にあたり無効とした。
※宥恕=寛大な心で相手を許すこと、大目に見て見逃すこと。
解雇は有効と判断された裁判例
裁判例③:
日本ストレージ・テクノロジー事件
(東京地判 平成18年3月14日)
外資系企業が、英語、パソコンのスキル、物流業務の経験を買われて中途採用された従業員を、業務遂行能力が著しく低く、勤務態度不良として解雇した事案。
- ・業務上のミスを繰り返し、他部門や顧客から苦情が相次いだにも関わらず、上司の注意に従わなかった。
- ・異動後も上司の指示に従わず、報告義務を果たさず、顧客に不誠実な対応を取ったため苦情が相次ぎ、再三改善を求めたが改善されなかった。
- ・担当業務の習熟が遅く、業務処理速度の向上を促されていた。
- ・上司の指示に従わないとして譴責(けんせき)処分を受けたが、ミーティングへの出席を拒否した。
裁判例④:小野リース事件
(最三小判 平成22年5月25日)
勤務態度が悪い統括事業部長兼務取締役の地位にある労働者を解雇した事案。
また、懲戒処分の解雇以外の方法をとることなく解雇したとしても、解雇が著しく相当性を欠き不法行為にあたるとはいえない、とした。
勤務成績不良や能力不足の従業員を
解雇する際の条件について
では次に、解雇する際に問題になるポイントと、どういった条件があれば従業員を解雇することができるのかについて考えていきます。
問題となるポイント
解雇権濫用の有無
労働契約法第16条により、客観的合理性と社会通念上の相当性が必要とされます。
能力不足の定義
能力不足というのは抽象的で曖昧なため、具体的にどのような業務上の支障が起きたのか、またその因果関係が問われます。
教育・指導の履歴
問題のある社員に対して教育・指導を行なってきたか、また改善機会を与えたかどうか、などが重要な判断材料になります。
配置転換の有無
配置転換を実施することで、他職種での適性を検討したかどうかも問われます。
評価の客観性
相対評価ではなく、定量的・公平な評価が必要とされます。
解雇が認められるための
主な条件
会社が従業員を解雇する際に必要とされる主な条件をまとめてみました。
| 項目 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 就業規則に該当する 事由が あること |
勤務成績不良や能力不足が、就業規則に定められた解雇事由に該当している必要があります。 | 解雇事由として「勤務成績が著しく不良で、向上の見込みがない場合」などの項目を規定しておく。 |
| 客観的に 合理的な 理由が あること |
単なる主観的評価ではなく、客観的な事実に基づく必要があります (労働契約法第16条)。 |
「業務ミスの頻度」、「営業成績」、「顧客からの苦情」などの記録が重要。 |
| 社会通念上 相当と 認められる こと |
解雇が社会的に見て、妥当と判断される必要があります (労働契約法第16条)。 |
解雇を回避する努力がなされているかが問われる。 |
| 改善のための指導・ 教育を 行なった こと |
能力不足を理由にする場合、改善の機会を与える必要があります。 | 指導記録や面談履歴が証拠になるため、記録化しておく。 |
| 配置転換 などの解雇 回避措置を 講じたこと |
他部署への異動や職務変更など、解雇以外の選択肢を検討したかが問われます。 | 特に大手企業では配置転換の余地があると判断されやすいため注意が必要。 |
| 能力不足が 業務に 重大な 支障を 与えている こと |
単なる成績不良ではなく、業務遂行において深刻な影響があることが必要です。 | 会社に損害が生じている場合などの証拠が必要。 |
| 勤務態度が著しく 不良であること (場合に よる) |
能力不足に加えて、指示の無視や協調性の欠如などがある場合は、解雇の正当性の判断に影響します。 | こうした理由の場合は、懲戒解雇ではなく普通解雇として扱われることが多い。 |
これまでの裁判例から、新卒採用者の場合、指導の責任が会社側にあるため、解雇は厳しく判断される傾向があります。
一方、中途採用者の場合は、期待された能力を発揮できないのであれば比較的解雇が認められやすい傾向があるといえます。
企業側が実施するべき
不当解雇を避けるための対応策
勤務成績不良や能力不足を理由に従業員を解雇する場合、会社側は慎重かつ段階的な対応を取る必要があります。
会社が取るべき対応を項目ごとに一覧表にまとめたので確認していただきたいと思います。
<解雇が認められるために会社が取るべき対応一覧>
| 項目 | 対応内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 能力の 定義と 期待水準の 明確化 |
会社が求める業務遂行能力や成果を文書化し、従業員と共有する。 | 職務記述書や評価基準の提示が有効。 |
| 問題点の 具体的な 指摘と記録 |
成績不良や能力不足の具体的事例(ミス、苦情、成績など)を記録し、本人に伝える。 | 時系列で客観的に記録することが重要。 |
| 指導・教育の実施と 記録 |
改善のための指導や研修を継続的に行ない、その内容と反応を記録する。 | 指導履歴や面談記録が後の証拠になるため重要。 |
| 改善機会の付与と評価 | 一定期間内に改善が見られるかを評価し、改善の見込みがあるかを判断する。 | 改善の猶予期間を明示することが望ましい。 |
| 配置転換や職務変更の検討 | 他部署や職種への異動を試み、適性の有無を確認する。 | 特に新卒採用者には配置転換の余地が求められる傾向がある。 |
| 退職勧奨の実施 (必要に 応じて) |
解雇前に穏便な退職の選択肢を提示する。 | 退職強要にならないよう慎重な言動が必要。 |
| 解雇通知と理由の明示 | 解雇の際は、具体的な理由を記載した通知書を交付する。 解雇の30日前に予告、または30日分以上の予告手当を支給する。 |
就業規則の該当条項と事実関係を明記することが重要。 |
| 証拠の 整理と保管 |
指導履歴、評価表、面談記録などを整理し、万一の紛争に備える。 | 書面・メール・録音など多角的な証拠が有効。 |
【参考資料】:仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき(厚生労働省)
解雇に関する問題は
弁護士にご相談ください!
会社が従業員を解雇する場合、不当解雇と判断されるリスクは高いため、慎重な判断と対応が必要になります。
解雇は最後の手段とすべきで、安易に解雇してしまうと、さまざまなトラブルが起きてしまう可能性があります。
- ・解雇したい従業員がいるが、
適切な対応・判断が難しい。 - ・就業規則の見直しをしたいが、
社内ではリーガルチェックができない。 - ・解雇した従業員から裁判を起こされていて、早急に対応しなければいけない。
このような問題を抱えている場合は、できるだけ迅速に対応していくためにも労務トラブルに強い弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。
弁護士法人みらい総合法律事務所は全国対応で、随時、無料相談を行なっています(事案によりますので、お問い合わせください)。
また、顧問弁護士についてのご相談もいつでもお受けしていますので、まずは一度、気軽にご連絡ください。