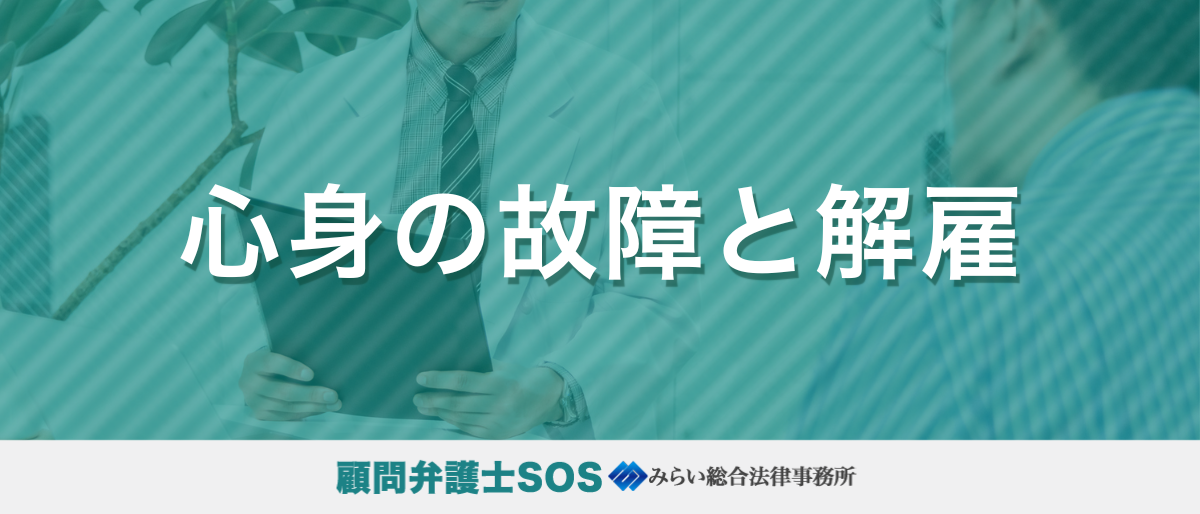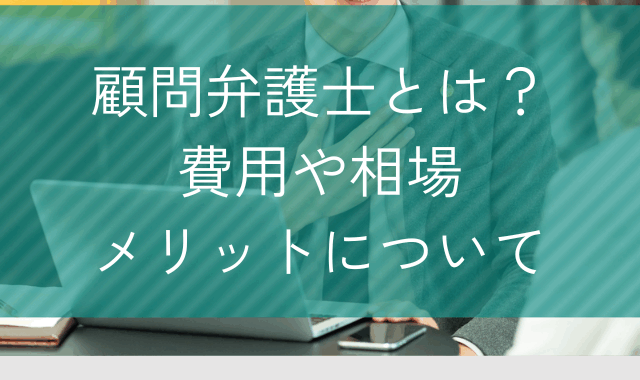心身の故障と解雇
本記事では、会社は心身の故障を抱える従業員を解雇できるか、という問題について解説していきます。
心身の故障とは、主に法律などで使用される語句で、特定の業務を行ううえで支障となる身体や精神の病気や障害のことを指します。
資格や免許の取得、公的な役職への就任、業務遂行など、心身の故障を抱えてしまうことでさまざまな制限を受ける可能性もあります。
心身の故障により、当の従業員としては苦労をしているという事情があるでしょう。
しかし会社としても、出勤できない、業務を遂行できない従業員を雇用し続けるわけにもいかず、解雇の検討に進む段階が来るでしょう。
だからといって、会社は従業員を簡単に解雇することはできません。
業務上のケガや病気が原因の場合に従業員を解雇するには、法律上の制限があることに注意が必要です。
また裁判では、解雇権の濫用と判断され、解雇が無効とされる場合もあります。
さらに問題になるのが、解雇した場合に訴訟トラブルに発展し、元従業員が会社を訴えるケースです。
裁判で会社が敗訴し、不当解雇の判断がされた場合は、慰謝料などの損害賠償金の支払いが発生してしまう可能性があるからです。
そこで、本記事では次の項目を中心にお話ししていきます。
- ・会社が行う解雇の概要と種類
- ・心身の故障を理由とした解雇が
有効かどうかの判断基準 - ・不当解雇と判断されないために
重要なポイントと対応策 など
心身に故障を抱える従業員の解雇は慎重に判断し、対応することが必要です。
ぜひ最後まで読んでいただいて、適切な対応を取っていくための知識を得ていただきたいと思います。
目次
解雇の概要と種類について
解雇とは?
企業(使用者)が従業員(労働者)との労働契約を一方的に終了(解約)させることを解雇といいます。
解雇は、会社側が一方的に行うもので、従業員側から行うものではありません。
従業員からの労働契約の解約は、自己都合による退職になります。
解雇は労働者の生活に重大な影響を及ぼすため、法律によって制限されています。
第16条(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
解雇の種類
解雇には、主に次の4種類があります。
| 普通解雇 | 能力不足、健康問題、勤怠不良など、 労働契約の継続が困難な場合に行う 解雇。 |
|---|---|
| 整理解雇 | 経営悪化など、企業側の事情による 人員削減のための解雇。 |
| 懲戒解雇 | 横領、暴力、重大な規律違反など、 企業秩序を著しく乱す 行為に対する 制裁的解雇。 |
| 諭旨解雇 | 従業員本人の反省や情状を考慮し、 退職勧奨などにより 自主的に退職届の提出を促す形の解雇。 |
重大な規律違反や不正などがなければ、心身の故障(身体や精神の病気や障害)の場合の従業員の解雇は、普通解雇になります。
心身の故障を理由に解雇することはできるのか?
通常、就業規則の普通解雇事由の条項に、「心身の故障のため業務に堪えないとき」といった文言を入れている会社も多いと思います。
そのため、心身の故障により勤務の継続が難しい場合、従業員が労働契約上の義務の履行ができなくなっているわけですから、解雇の理由になり得ます。
しかし、長期的な雇用が慣行となっている現状で、解雇は労働者に重大な不利益を負わせるものであるため、たとえ心身の故障がみられたとしても、安易な解雇は解雇権濫用(労働契約法第16条)として無効となる可能性が高いといえます。
これは業務上での心身の故障だけでなく、私傷病(私的な理由で傷病を負った場合)でも同様の判断がなされる可能性が高いといえます。
心身の故障で従業員を解雇する際の条件とは?
では、どういった条件があれば心身の故障で従業員を解雇することができるのか、見ていきましょう。
業務に耐えられない
状態であること
- ・病気や障害により、従業員が業務を
継続できないと客観的に判断できる程度に
達している場合。 - ・治療によっても回復する可能性がないと
判断される場合。 - ・その際は、医師の診断書や出勤状況などを判断材料にしながら
慎重に検討して
いきます。
休職制度の適用と
満了の手続きを踏んでいること
- ・業務上のケガや病気が原因の場合は、
就業規則に基づき、
一定期間の休職を
認めたうえで、その期間が満了しても
復職できない場合。
(※休職制度がない場合でも、合理的な猶予期間を設けることが望ましいとされる) - ・また、治療目的での休業期間だけで
なく、その後30日間は企業が
解雇をすることが
認められていないことに注意が必要。
(労働基準法19条1項)
復職の可能性を
検討していること
- ・業務内容の変更や軽減、配置転換など
復職の可能性を最大限検討したが
復職が難しい場合。 - ・なお、これらの配慮を怠ると
「解雇権の濫用」と判断される
可能性があります。
解雇権の濫用に当たらないこと
- ・解雇が客観的に合理的であり、
社会的にも妥当と認められる
(社会通念上の相当性)
場合
(労働契約法第16条)。
解雇予告または予告手当の
支払い規定に
違反していないこと
- ・少なくとも30日前に解雇予告をした
場合、または30日分以上の予告手当を
支払った場合
(労働基準法第20条1項)。
労働トラブルの実務において、解雇が有効か否かについては、
- ・就業規則の内容
- ・傷病の状況
- ・労務への支障の程度
- ・治癒の可能性
などの個別具体的な事情を検討して、判断していくことになります。
不当解雇を避けるための
企業の対応策について
ここまでの内容を踏まえて、会社が不当解雇の訴えを回避するための対応策について考えてみます。
就業規則の明確化
- ・「心身の故障により業務に耐えられない場合」など、具体的な解雇事由を明記しておきます。
- ・休職制度の内容(期間・復職判断基準など)も明文化しておきます。
休職制度の適用と満了の明確化
- ・一定期間の休職を認め、期間の満了後も復職できない場合に限り解雇を検討します。
- ・その場合、自動退職規定(自然退職)を設けることで、解雇リスクを軽減することも検討します。
※自動退職規定(自然退職)=会社や従業員の意思表示がなくても、特定の事由が発生した場合に自動的に労働契約が終了する退職のこと。
【参考資料】:仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき(厚生労働省)
復職の可能性を最大限に検討
- ・業務軽減、配置転換、短時間勤務などの選択肢を従業員に提示して、復職の可能性を検討します。
- ・その際は、従業員の意思を尊重しつつも、医師の診断も重要になるので、
主治医または産業医の診断書をもとに
復職の可否を判断していきます。 - ・また、後の法的トラブルを回避するためにも、記録を残しておくことも大切です。
解雇予告または
予告手当の支払い
前述したように、解雇の30日前に予告、または30日分以上の予告手当を支給します。
退職勧奨を行う
- ・会社が従業員を説得して退職を促し、
合意を得たうえで解約あるいは辞職としての
退職をさせるのが「退職勧奨」です。 - ・解雇とは違い社員の同意のうえなので
法的なリスクが少ないというメリット
があります。
不当解雇が争われた裁判例
ここでは不当解雇が争われた裁判例について、解雇が認められたものと不当と判断されたものの両方を紹介します。
裁判例①東京電力事件
(東京地判 平成10年9月22日)
体調不良でほとんど出勤できない状態が続いていた嘱託社員(身体障害等級1級)を、勤務に耐えられないことを理由に解雇した事例。
裁判例②K社事件
(東京地判 平成17年2月18日)
躁鬱病のため欠勤が多く、出勤しても業務をまっとうできないため休職。その後、復職したものの欠勤が多く、躁鬱病の症状が再発した従業員(原告)に対して、社外へも影響がおよぶようになったとして会社が解雇した事例。
裁判になった場合の
会社側の対応について
裁判で解雇が争われた場合、企業には次のような対応が求められます。
証拠の提示
解雇理由の正当性を示す記録(注意指導、業務評価、就業規則など)の提示。
手続きの妥当性の説明
解雇までのプロセスが適切だったことの説明。
弁護士への相談
労働問題に詳しい弁護士に相談・依頼し、アドバイスやサポートを受けることでリスクを最小限に抑える。
和解の検討
裁判の長期化や企業イメージへの影響を回避するため、和解による解決も検討。
解雇に関わる労働トラブルは
弁護士に相談・依頼してください!
ここまでお話ししてきたように、会社が従業員を、心身の故障を理由に解雇する場合、不当解雇と判断されるリスクは非常に高く、慎重な対応が求められます。
安易な解雇は、解雇権濫用と判断される可能性が高いことから、解雇は最後の手段とすべきです。
- ・自社では、解雇に対する適切な判断が
難しい。 - ・就業規則の見直しをしたいが、
リーガルチェックが不十分。 - ・解雇した従業員から不当解雇の裁判を
起こされている。
このような問題を抱えている場合は、迅速に対応していくためにも労務問題に強い弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。
弁護士法人みらい総合法律事務所は全国対応で、随時、無料相談を行なっています(事案によりますので、お問い合わせください)。
また、顧問弁護士についてのご相談もいつでもお受けしていますので、まずは一度、気軽にご連絡ください。