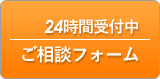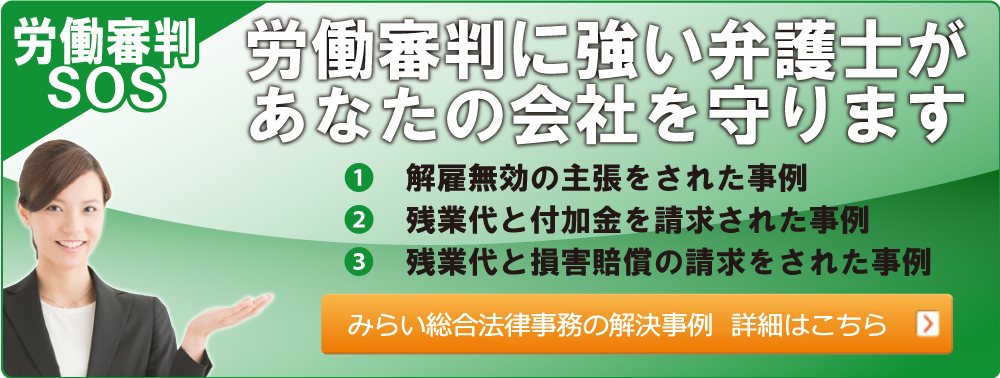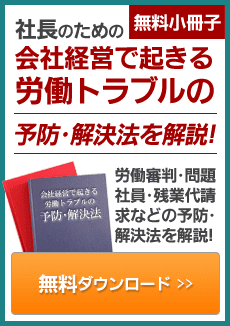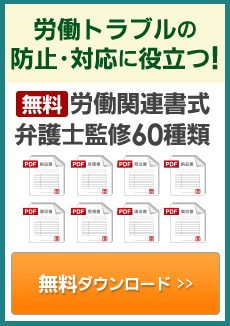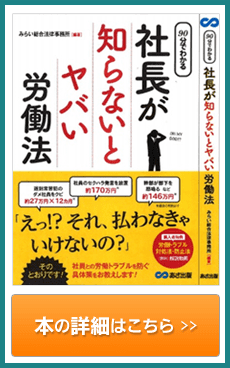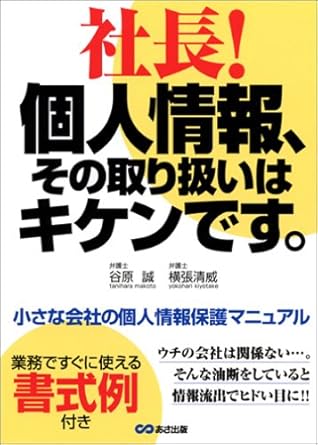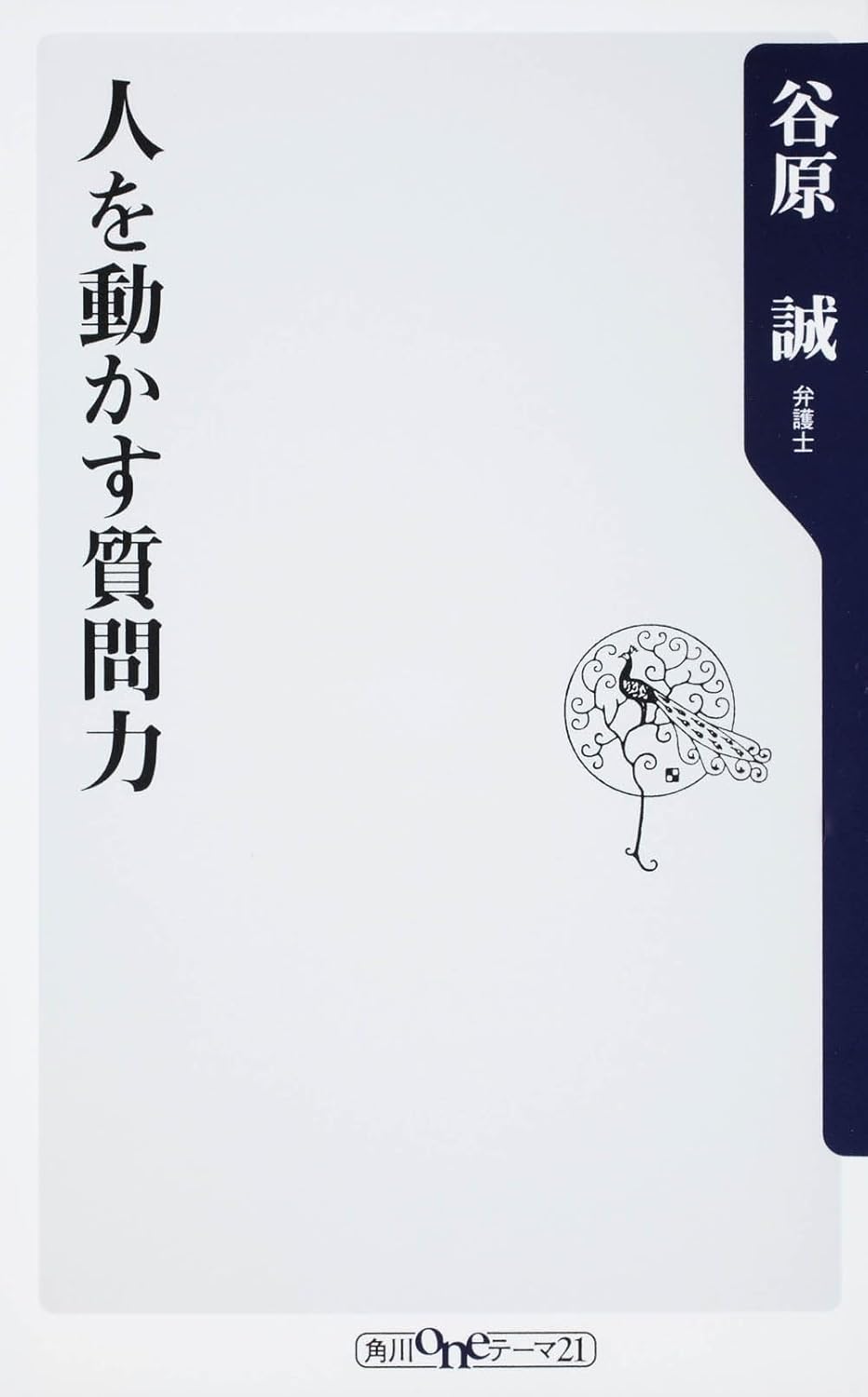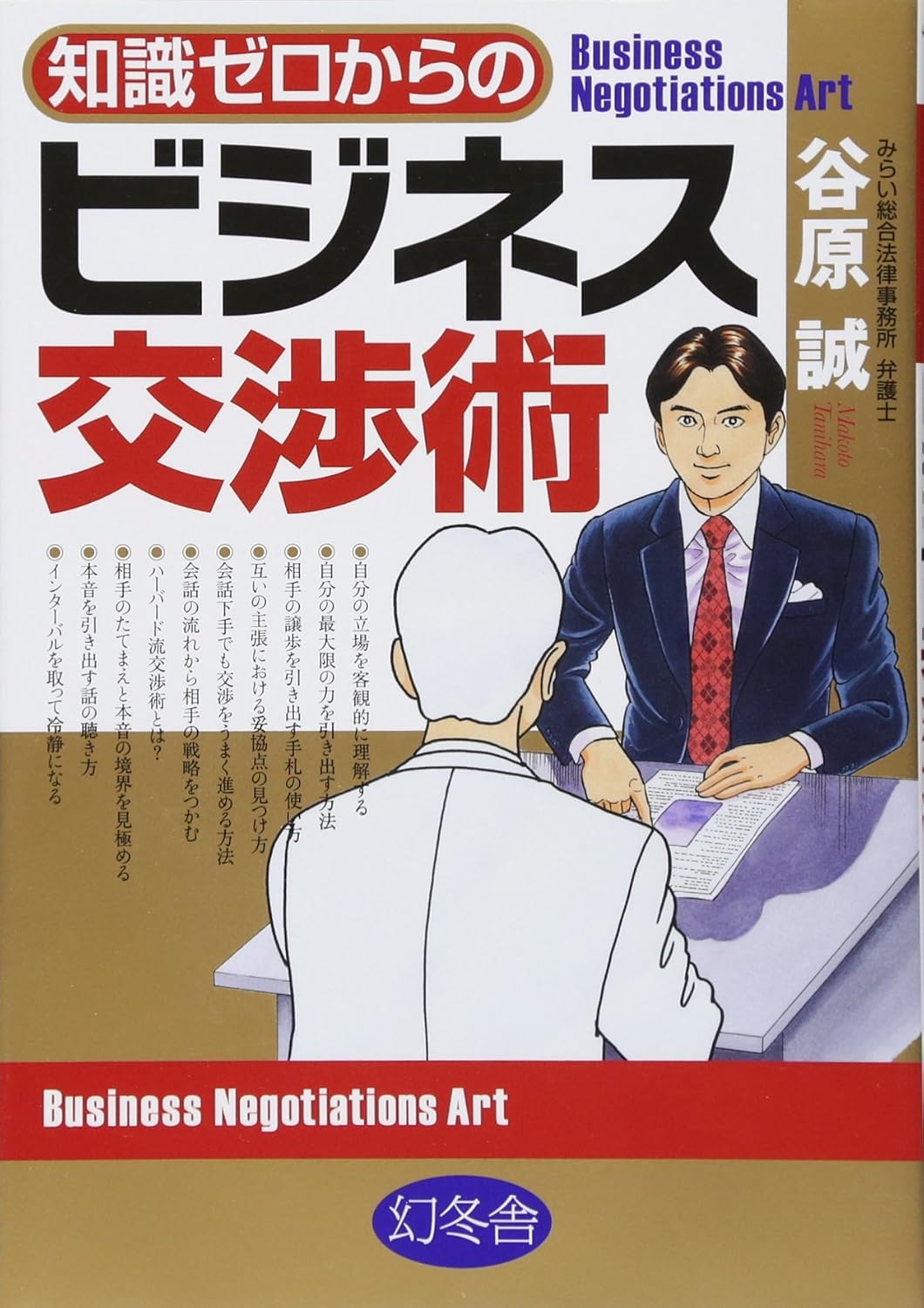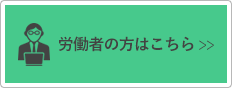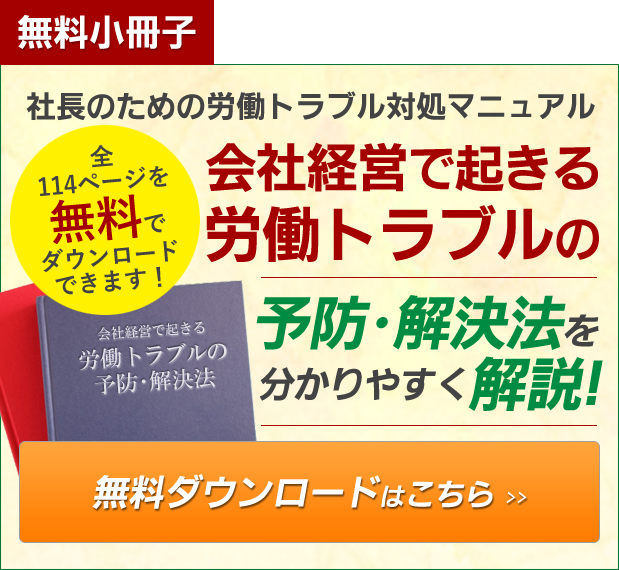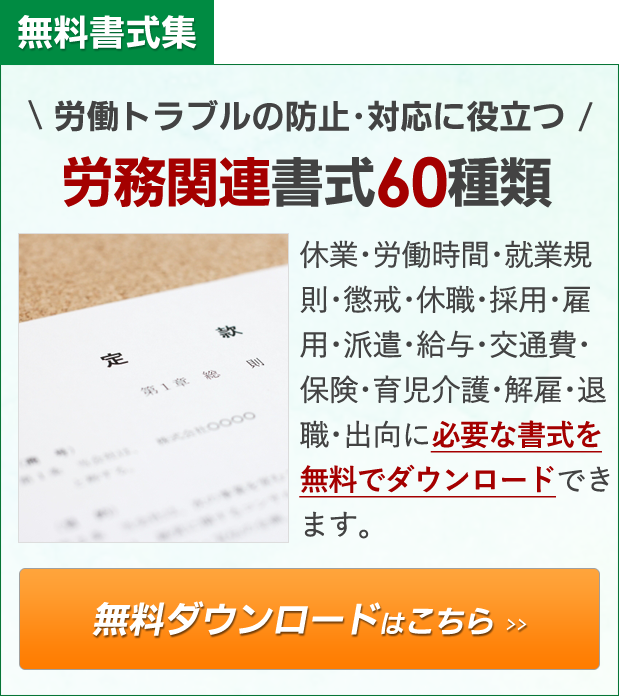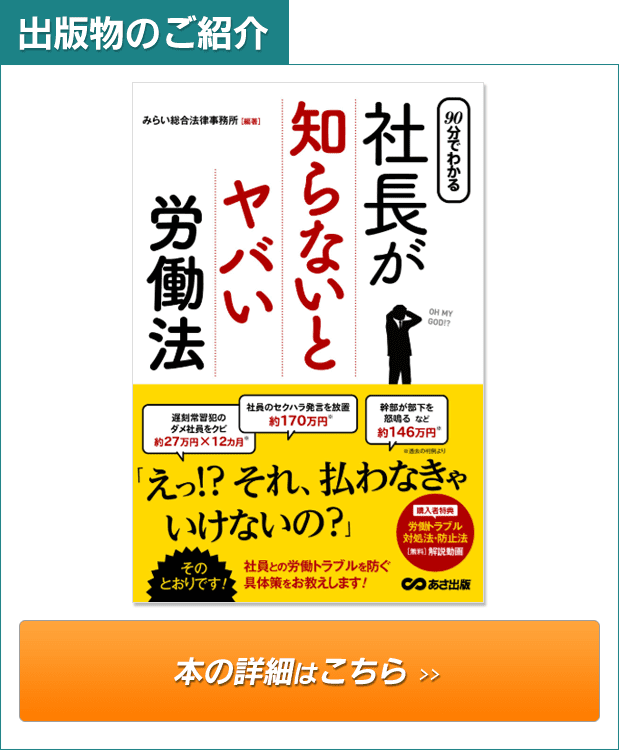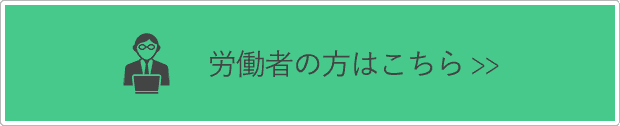労働審判対応の良い例・悪い例(会社側)
社員から労働審判を申し立てられた場合、会社側の対応次第で、結果が大きく違ってしまうことをご存じでしょうか。
労働審判は、原則として3回以内の期日において、審理を終結するとされていますが、第1回期日(申立後40日以内に指定される。)に申立書及び答弁書に基づいて争点整理がされます。
そして、出頭した当事者、関係者への審尋が行われ、その段階で形成された労働審判委員会の心証に基づき調停まで移行することがあるため、限られた時間の中で充実した答弁書等の作成、及び第1回期日の審尋に向けた準備を行うなどの対応が会社に求められます。
ここで会社側の対応の悪い例としては、まず、労働審判の申立てがあってからすぐに弁護士に相談しないということが挙げられます。
答弁書等の提出期限は、第1回期日の1週間~10日前に指定されることが多いので、労働審判の申立てがあってから1ヵ月弱で答弁書等の作成、及び証拠の提出を行わなければなりません。
弁護士への相談が遅くなると充実した答弁書等の作成、及び必要や証拠の提出ができなくなるだけでなく、第1回期日における関係者の審尋の準備が不十分になってしまいます。
それでは、労働審判の申立てがあったのですぐに弁護士に相談したという対応が最善かというと、そのような対応は一般的な対応に過ぎないといえます。労働審判の準備の負担は、相談を受けた弁護士が事前に相談を受けていた事件か、申立後に初めて相談を受けた事件かによって全く異なります。
事前に相談を受けていた事件であれば、事案の概要を事前に把握し、必要な証拠の収集についてあらかじめ助言しておくことで事前に証拠収集を行っておくことができるからです。
したがって、使用者と労働者との間のトラブルを把握したら、できる限り早い段階で弁護士に相談しておくことが、会社としてのより良い対応だと思います。
次に、会社側の対応の悪い例としては、答弁書等の提出が遅いということが挙げられます。
充実した答弁書等を提出することはもちろんですが、いかに充実した答弁書等を提出したとしても、それを労働審判官や労働審判委員が読む時間がなければ、労働審判委員会が会社側に有利な心証を抱くことはありません。
先ほども述べましたが、答弁書等の提出期限は、労働審判の申立てから1ヵ月弱とほとんど時間がありませんが、第1回期日に会社側に有利な心証を形成してもらうには、充実した答弁書等を提出期限内に提出し、労働審判官や労働審判委員に答弁書等を読む時間を確保させることが重要です。
また、第1回期日当日における会社側の対応の悪い例としては、第1回期日に関係者を一切同行させないということが挙げられます。第1回期日は、申立書及び答弁書に基づいて争点整理をした上、当事者や関係者の審尋となることがあります。
その際に、事実関係を説明できる人物を同行させていないということとなると、労働審判委員会の心証を害する結果となりかねません。当日出頭できない関係者については、その者の陳述書を提出することで対応することはありますが、関係者のなかでも最重要な者については、その者から直接供述が聞けない場合には、事案の内容と供述内容次第では、不利になる危険性があります。
そのため、第1回期日には、事実関係をよく把握している関係者を同行させておく必要があります。
最後に、話し合い(調停)における会社側の対応の悪い例としては、譲歩ラインを一切検討していないということが挙げられます。
労働審判を申し立ててきている以上、会社が全く譲歩しないで紛争を解決させることは不可能です(会社が話し合い(調停)による解決をそもそも望んでいなのであれば話は別ですが)。
そして、先にも述べましたように、第1回期日から調停に移行することもあるので、会社側としても第1回期日に臨むに当たり譲歩のラインを決めておかなければ、いざ話し合い(調停)になったときに、当該期日での解決が不能となり、不必要に期日を重ねることになり、会社の負担が増えることになります。
会社側の対応としてより良い例としては、譲歩ラインを検討しておくとともに、第1回期日に決裁者の同行(少なくとも、当日、電話連絡がとれるようにしておくこと)をさせておくということが挙げられます。
決裁者を同行させておくことで、当初予定していた譲歩ラインをわずかに超えていた場合にも速やかに対応することが可能となり、早期に話し合いがまとまる可能性が高くなります。
第1回期日に提示された調停案に相手方が応じる姿勢を見せていたにもかかわらず、こちらに決裁者がおらず、回答が第2回期日に持ち越された場合、第2回期日のときには相手方の考えが変っているということもあります。
以上、労働審判対応の良い例・悪い例(企業側)をご説明致しましたが、労働審判において特に重要なのは、第1回期日までの準備、及び第1回期日当日の対応かと思います。
そのためには、労働トラブルを把握したら、早期に顧問弁護士等に相談することが大切だと思います。