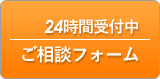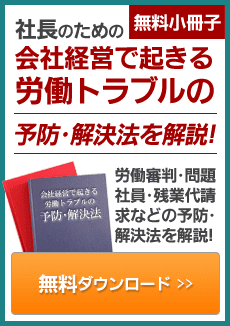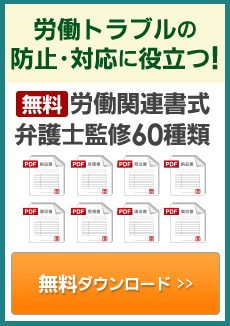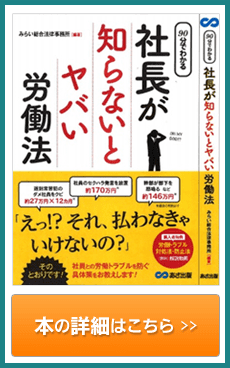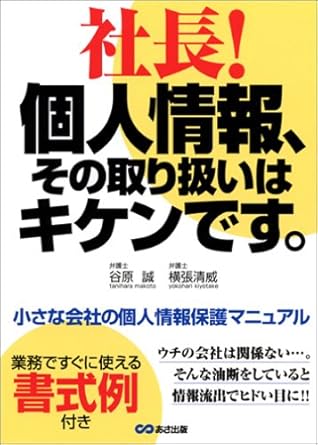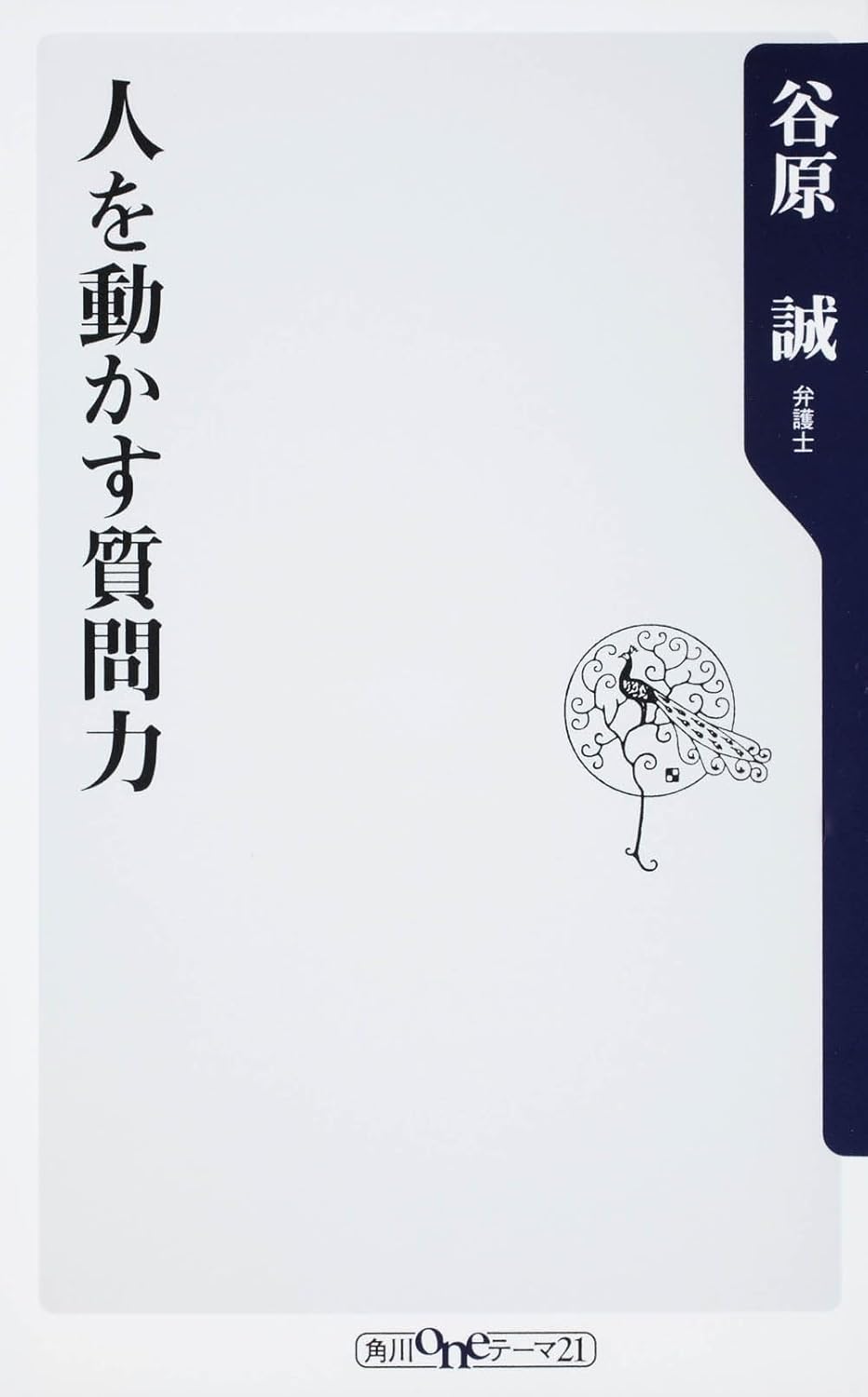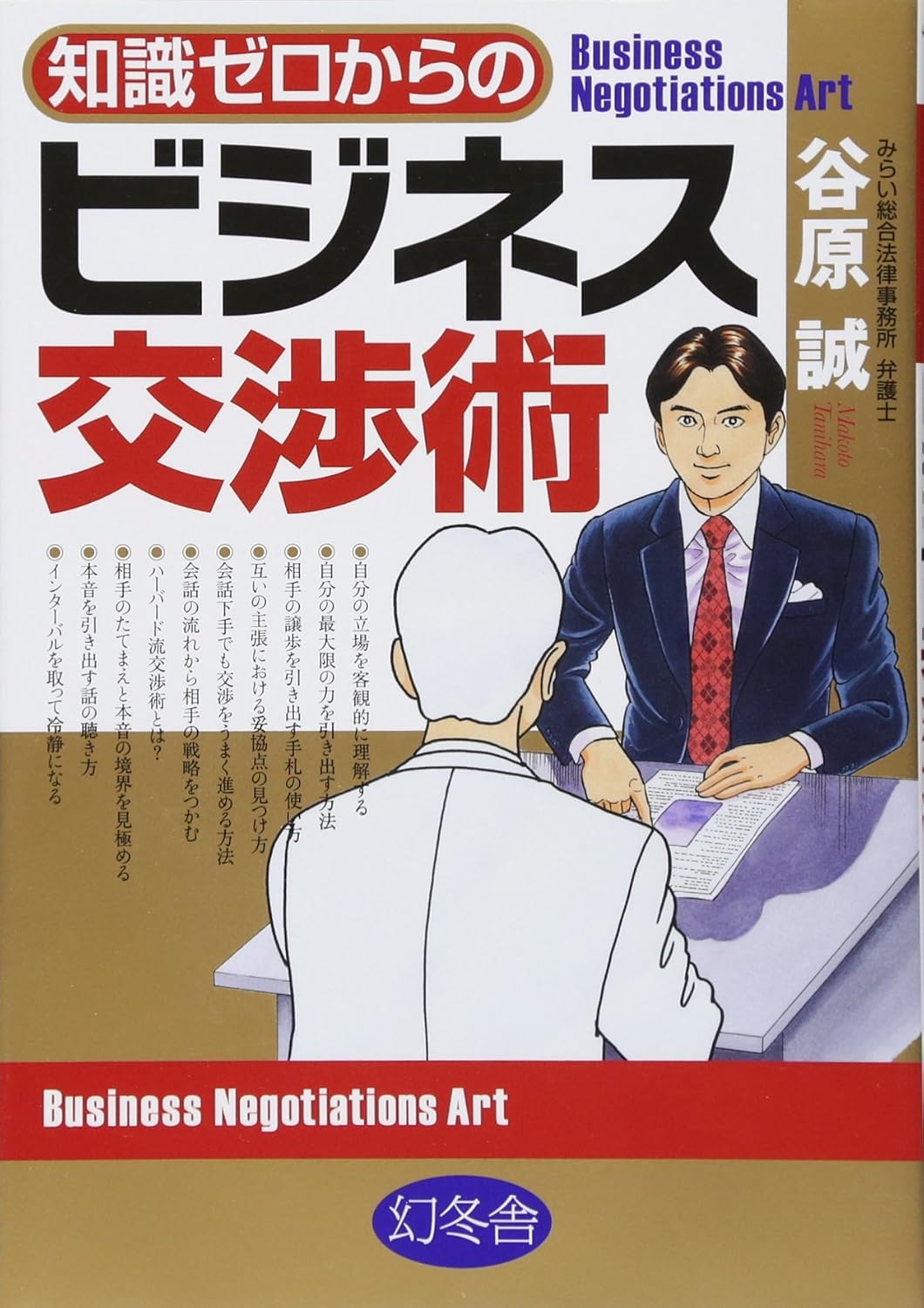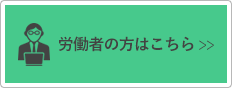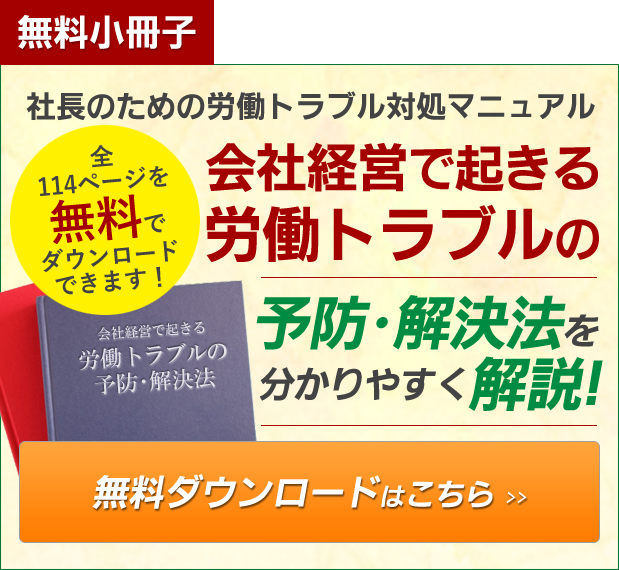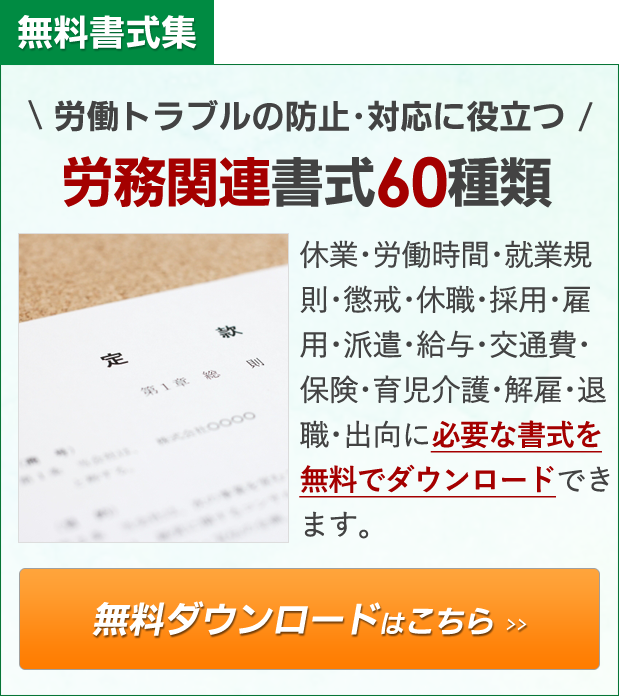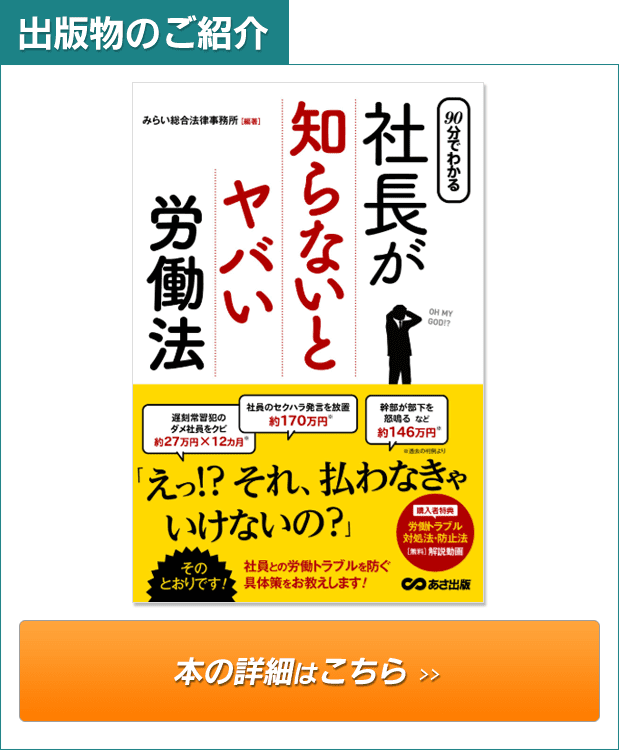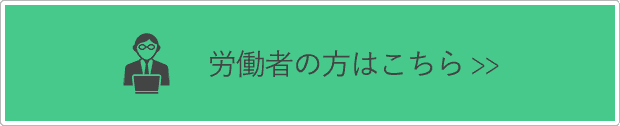労働審判の呼出状が来てから第1回期日までの注意点
労働審判は裁判と違い、呼出状が来てから、すぐに準備を始めないと、会社に大変不利に展開されてしまいます。
というのも、労働審判では第1回期日が最も重要な期日であるにもかかわらず、呼出状が来てから第1回期日までの期間が短く、かつ、会社として準備しておかなければならないことが膨大であるため、適切な準備をして第1回期日に臨むことが極めて難しいのです。
まず、なぜ労働審判においては第1回期日が最も重要な期日なのかをご説明します。
労働審判では、裁判官を含む3名の労働審判官が、原則として3回という限られた期日で審理を終結することとなっているため、第1回期日までにすべての主張及び証拠を提出するよう努めることとされています。
そのような第1回期日において、しっかりとした法律的な主張ができないと、申立人の主張が認められてしまったり、会社側に対する審判官のイメージが悪くなってしまう可能性があるのです。
労働法の規定を前提としない主張や、会社の言い分に終始し争点を的確に把握していない主張などは、審判官に、「この会社は労働法を順守する気がないのではないか」と思われる危険があるからです。
また、多くても3回しか期日が開かれない労働審判では、審判官は第1回期日において、どのような判断を下すかの大まかな印象を決めてしまうため、その印象を残り2回の期日で覆すことは極めて難しいと言えます。
通常の裁判であれば、半年から、長いものでは数年かかりますから、その間に裁判官の心証が変化することはよくあることですが、労働審判においては、そのようなことはほとんどないと言っていいでしょう。
そして、労働審判では第1回期日において審判官から調停案が示されることもあります。
このとき、示された調停案に対して会社としての意思を明確に伝えられないと、会社に解決意思がないと判断されてしまう可能性があります。
そのため、会社として最終的にどのような解決を求めるのか、申立人の請求に対してどの程度までは譲歩できるのかを、事実関係を前提に、第1回期日までに決めておく必要があるのです。
このように、労働審判においては、第1回期日が最も重要な期日なのです。
この第1回期日は、多くの場合、申立日から40日以内に指定され、答弁書の提出期限が、第1回期日の5~7日前に指定されます。
第1回期日では提出した答弁書の内容を前提として主張していくことになりますから、実質的な第1回期日までの準備期間は、答弁書提出までの、約1カ月しかありません。
そして、この間、会社がやらなくてはならない準備は、膨大です。大まかにみても、次のような準備をする必要があります。
① 裁判所から送付されてくる申立書を検討し、その内容を法的に分析する。
労働審判は裁判所が関与する司法手続きですから、申立人が裁判所に提出する申立書は、ほとんどの場合申立人から委任を受けた弁護士が作成しています。そのため、その申立書の内容を分析するには、労働法についての正確な理解が必要です。また、申立書には様々な事実が書かれていますが、その中にも大事な事実とそうでない事実とがあり、その見極めが会社の戦略を立てる上で非常に重要になります。
② 申立人の主張する事実が存在するのかを調査する。
会社は、申立人が主張する事実が存在したのかを調査することになります。しかし、申立書においては様々な事実が主張されますから、やみくもに調査をしていては到底第1回期日に間に合いません。そのため、重要なポイントを見極めたうえで調査をする必要があります。
③ 申立書とともに送付されてくる証拠を検討し、立証の程度を分析する。
労働審判において審判官は、申立人が提出する証拠を見て、審判を進めていきます。裁判所に提出される証拠と同じものが会社にも送られてきますが、それらがどのような意味を持ち、どれだけ強い証拠なのかの判断には、専門的な訴訟知識が必要です。
④ 申立人の主張に対する反論を法的に構成する。
申立人に対する、法律的な反論を考えます。有効な反論は一つではありませんし、多数にわたることも多いです。そしてそのどれを主張するのか、また複数を主張するのかも、判断する必要があります。主張できるものを全て主張することが、必ずしも適切な戦略とは限りません。判断を下す審判官に対して、法律的に最も説得的な主張をする必要があります。
⑤ 会社側の主張や反論を支えるにはどのような証拠が必要かを検討したうえで、それらの証拠を収集、作成する。
会社の法律的な主張を審判官に納得させるためには、その主張を支える具体的な事実を不足なく主張する必要があります。そしてどのような事実が会社の主張を支えるのかの判断には、専門的な知識が必要です。
⑥ 会社側の主張や証拠を、説得的な法律文章として書面化し、答弁書を作成する。
ここまでで検討したことを、裁判官を含む審判官に理解してもらい、会社の主張に沿った判断がなされるように、説得的な文章で答弁書を作成しなければなりません。
⑦ 申立人の主張と会社の主張を検討し、審判やその後の裁判においてどのような判断が下されるのかを想定する。
労働審判では、審判官が示す調停案や、審判の内容を想定して審判に臨むことが、会社の利益を最大化するための戦略を立てるには必要不可欠です。また、審判が裁判に移行してしまった場合に、裁判においてどのような判断が下されるのかということも、審判に臨む段階から、検討しておく必要があります。
多くの労働審判を経験し、日々新しい労働審判例を研究する弁護士であれば、申立人と会社側の両者の主張の分析することにより、審判や裁判において、裁判所からどのような判断が下されるのかを、高い精度で想定することができます。
⑧ 想定される判断を踏まえ、会社としてどのような解決を求めるのか、どの程度までは譲歩できるのかを検討する。
審判官の判断とかけ離れた主張は、意味がないだけでなく、審判官に不信感を与えるなど、会社にとって不利益となってしまう恐れもあります。
審判官の判断を想定し、会社として現実的な妥協点を想定したうえで、第1回期日に臨む必要があります。
労働審判を申立てられた会社は、通常の業務を行いながら、これだけの作業をわずか1カ月で行う必要があるのです。
また、通常の業務を犠牲にし、審判の対応に時間をかけたとしても、申立人の主張の法律的な分析や、相手方の立証の程度の分析、会社に最適な法的主張の構成、必要となる証拠の検討、法律文章の書面化、審判や裁判で示されることになる判断の想定、そしてその想定を前提とした、会社としての戦略の判断等には、専門的な法的知識、そして労働審判についての経験や最新の労働判例の研究が不可欠です。
通常の会社の労務問題の担当者が、1カ月という期間で、これらに適切に対応することは、極めて困難と言わざるを得ません。
このように、弁護士の力を借り、適切な戦略を構築し、しっかりとした答弁書を作成することが、労働審判を申立てられた会社にとって、自社の利益を最大化する方法といえるのです。
労働審判の呼出状が来てしまった場合には、速やかに労働問題に精通した弁護士に相談しましょう。