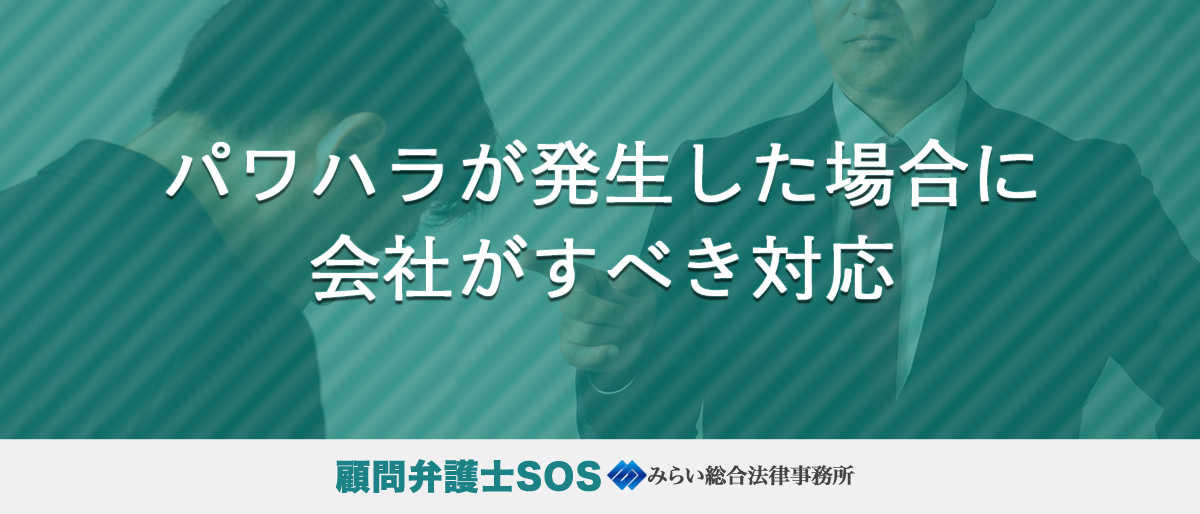パワハラが発生した場合に会社がすべき対応
職場で起きるパワハラを、ただの社内トラブルとして済ませていませんか?
パワハラそのものを規制する法律はありませんが、犯罪行為として加害者が刑事責任を追及される可能性もあることは知っておくべきです。
さらに、パワハラを放置したり、不適切な対応をしていると、会社も「使用者責任」(民法715条)や、労働契約上の「安全配慮義務違反」による「債務不履行責任」(民法415条)に基づいて、損害賠償責任を負う場合があります。
厚生労働省は「職場におけるパワハラ防止のための指針」として、次の10種の措置を明示しています。
(1)事業主の方針の明確化および、
その周知・啓発
①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行なってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること。
②行為者について厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること。
(2)相談に応じ、適切に対応するために
必要な体制の整備
③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。
④相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。
職場におけるパワハラの発生のおそれがある場合や、パワハラに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応すること。
(3)職場におけるパワーハラスメントに
かかる事後の迅速かつ適切な対応
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
⑥速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行なうこと。
⑦行為者に対する措置を適正に行なうこと
⑧再発防止に向けた措置を講ずること。
(4)(1)から(3)までの措置と併せて
講ずべき措置
⑨相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
⑩相談したこと等を理由として不利益な取扱いを行なってはならない旨を定め、労働者に周知・ 啓発すること。
本記事では、これらの内容を中心に、「パワハラの定義や3つの要素」、「典型的な6つの類型」、「会社がとるべき対応」などについて詳しく解説していきます。
目次
パワハラの定義とは?どういった
行為が当てはまる?
主に、社会的な地位が高く、強い者が、自らの権力や組織内の優位性を利用して行なう、いじめや嫌がらせ行為を「パワーハラスメント(パワハラ)」といいます。
ここでは、職場におけるパワハラを中心に見ていきます。
パワハラを定義する「3つの
要素」とは?
厚生労働省は、職場におけるパワハラを次の3つの要素をすべて満たすもの、と定義しています。
優越的な関係に基づいて
(優位性を背景に) 行なわれる
もの
嫌がらせや暴力行為を受ける労働者が、行為者に対して抵抗または拒絶することができない。
蓋然性(真実として認められる確実性の度合い)が高い関係に基づいて行われる言動であること。
※優越的な関係を背景とした言動には、事業主から従業員、上司から部下、同僚同士だけでなく、経験・知識・人間関係などによって相手より優位な立場にある者の言動も含まれます。
- ・職務上の地位が上位の者からの行為。
- ・業務上、必要な知識や豊富な経験を有している同僚や部下などからの行為。
(彼らの協力を得なければ業務の円滑な遂行を行なうことが困難な場合など) - ・同僚や部下からの集団による行為で、抵抗や拒絶するのが困難なもの。
業務の適正な範囲を超えて
行なわれるもの
社会通念に照らして、労働者が受けた行為(指示や命令)が、明らかに業務上の必要性がない、またはその態様が相当でないものであること。
- ・業務上明らかに必要性のない行為。
- ・業務の目的を大きく逸脱した行為。
- ・業務を遂行するための手段として不適当な行為。
- ・行為の回数、行為者の数などの態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える行為。
身体的・精神的な苦痛を与えるもの、 または就業環境を害するもの
当該行為を受けた者が身体的もしくは精神的に圧力を加えられ、負担(不快・不安・恐怖など)と感じること。
当該行為を受けた者の職場環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、当該労働者が就業するうえで見逃すことができない程度の支障が生じること。
- ・暴力により傷害を負わせる行為。
- ・著しい暴言を吐くなど、人格を否定する行為。
- ・何度も大声で怒鳴る、厳しい叱責を執拗に繰り返すなど、恐怖を感じさせる行為。
- ・長期にわたる無視や能力に見合わない仕事をさせるなど、就業意欲を低下させる行為。
※なお、判断にあたっては、「平均的な労働者の感じ方を基準とする」としています。
パワハラに該当する典型的な
行為(6類型)
厚生労働省は、次の6つのタイプを典型例としてあげています。
身体的な攻撃(暴行・傷害
など)
叩く、蹴る、物を投げつけるなど。
<パワハラに該当する例>
上司が部下に対して、殴打、足蹴りをする、物を投げつける、など。
<パワハラに該当しない例>
・業務上の関係のない、ただ単に同じ企業や職場の同僚間でのけんか、など。
精神的な攻撃(脅迫・侮辱・
名誉毀損など)
人格否定、長時間の叱責、大声で怒鳴るなど。
<パワハラに該当する例>
- ・休暇中に出勤を命令し、それを拒んだ部下に対して人格を否定する発言をする、 辞職を強いるような発言をする。
- ・他の従業員の前で横領行為の犯人扱いをする。
- ・上司を中傷、人格否定するビラを配布する。
<パワハラに該当しない例>
- ・顧客からの苦情を受けて、テレアポ業務の担当者に対して声を大きくすること、電話の件数をこなすのではなくアポイントの取得を目指すべきこと、などを指導する。
- ・販売担当者が販売実績を知らないことに対して、「その程度のことは把握しておくように」と注意する。
- ・社会的ルールやマナーを欠いた言動(遅刻や服装の乱れなど)をしていた従業員に、上司が再三注意したが改善されなかったため、強く注意する。
人間関係からの切り離し
業務上で必要な会話をしない、隔離、無視をする、など。
<パワハラに該当する例>
- ・産休を取得したことなどを理由に仕事を外して、数年間、別室に隔離したり、自宅研修させる。
- ・社長の意に沿わない従業員を退職に追い込むために配転命令を発令し、他の従業員を扇動して退職勧奨する。
<パワハラに該当しない例>
- ・新入社員の育成のために短期間集中的に個室で研修などの教育を実施する。
過大な要求
明らかに達成不可能なノルマを課す、本来の業務と関係ない仕事を強制する、など。
<パワハラに該当する例>
- ・上司が部下に、勤務に直接関係のない、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での作業を長期間にわたり命じる。
- ・他の従業員より高いノルマを1年以上にわたって課し、達成できないことを人前で叱責する。
- ・接触事故を起こした運転手に、1か月間の炎天下での除草作業を含む下車勤務命令を出す。
- ・販売目標が未達成の罰として、研修会でコスチュームの着用を強要する。
<パワハラに該当しない例>
- ・社員を育成するために、現状よりも少し高いレベルの業務を任せる。
- ・上司が至急の業務を命令した後、進捗を確認しなかったにもかかわらず、部下が進捗を報告しなかったことを責めるメールを送信し、帰宅する。
過小な要求
能力や経験に見合わない簡単すぎる業務だけをさせる、仕事を与えない、など。
<パワハラに該当する例>
- ・管理職である部下を退職させるため、上司が誰でもできるような業務に配置転換する。
- ・内部通報した従業員を新入職員と同じ職務に配置転換する。
<パワハラに該当しない例>
- ・経営上の理由により、従業員を一時的に、能力に見合わない簡易な業務に就かせる。
- ・経営上の理由により、多数の管理職を一斉に権限のない役職に降格させる。
個の侵害
私生活への過度な干渉(恋愛、家族、宗教など)、個人情報の暴露など。
<パワハラに該当する例>
- ・個人の思想や信条を理由に、他の従業員に接触しないように働きかける、職場内外で継続的に監視する、ロッカーなどを無断で開けて私物の写真撮影をする、など。
- ・リフレッシュ休暇取得後、すぐに有給休暇取得の申請をした従業員に申請の取下げをさせる。
<パワハラに該当しない例>
- ・社員への配慮を目的として、家族の状況などについてヒアリングを行なう、など。
職場/労働者の判断について
職場とは?
通常、事業主が雇用する労働者が、業務を遂行する場所(会社や事務所など)を職場といいます。
ただし、労働者が業務を遂行する場所であれば、就業している場所以外の場所も職場に含まれると判断されます。
- ・取引先の会社、事務所
- ・取引先との打ち合わせや接待などで使用する飲食店
- ・出張先
- ・顧客の自宅
- ・業務で使用する車内
- ・社員寮
- ・勤務時間外の懇親会 など
労働者とは?
- ・正規雇用の労働者(正社員)
- ・非正規労働者(パートタイマー、契約社員など)
※事業主が雇用するすべての労働者が該当します。
※派遣労働者については、派遣元の事業主だけでなく、派遣先の事業主も自らが雇用する労働者に対してと同じように措置を講じる必要があります。
【参考資料】:パワーハラスメントの定義について
(厚生労働省)
知っておくべきパワハラに関連する法律
パワハラ防止に関連する法律に「労働施策総合推進法」があります。
もともとは、1966(昭和41)年7月に施行された「雇用対策法」が、2018(平成30)年に改正されて、労働施策総合推進法になったという経緯があり、その目的は、次のように規定されています(第1条第1項)。
労働市場の機能が適切に発揮され、
労働者の多様な事情に応じた雇用の安定、職業生活の充実、労働生産性の向上を促進して、
労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、
労働者の職業の安定と経済的、社会的地位の向上を図り、
経済および社会の発展と完全雇用の達成に資することを目的とする。
なお、2019年の法改正(2020年6月施行)で、パワハラ防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となっています。
第30条の2(雇用管理上の措置等)
1.事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2.事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
上記に違反した場合は、行政指導や企業名の公表などの対象となるため注意が必要です。
【参考資料】:職場におけるパワーハラスメント対策が 事業主の義務になりました!(厚生労働省)
パワハラが発生した場合に会社が
すべき対応と流れ
職場で起きたパワハラを放置するなど不適切な対応していると、会社も「使用者責任」(民法715条)や、労働契約上の「安全配慮義務違反」による「債務不履行責任」(民法415条)に基づき、損害賠償責任を負う場合があります。
そこで次に、従業員などの労働者からパワハラの相談を受けた場合に、事業主(会社)が対応すべきことについて詳しく見ていきます。
事実調査の開始
パワハラ相談があったなら、まずは調査担当者を決定します。
相談窓口を設置しているなら、その担当者を調査の担当者に任命するか、あるいはパワハラ調査委員会などを設置するのが望ましいです。
そのうえで、次の手続きと流れで調査を進めていきます。
ヒアリング
- ・相談者へのヒアリング
- ・関係者(目撃者)へのヒアリング
- ・行為者へのヒアリング
※関係者(目撃者)や行為者へのヒアリングは、相談者の承諾を得たうえで実施します。
※ヒアリングでは、聞き取った内容を記録・録音などして、文章でまとめて整理し、保全します。
※ヒアリング後は、対象者に内容の確認をしてもらい、署名(サイン)をもらっておきます。
※必要があれば、再度のヒアリングを実施します(相談者と行為者の言い分が食い違う場合など)。
証拠の収集
メールやSNSなどの履歴と内容、音声の録音データなどがあれば、パワハラの証拠として収集します。
<コラム①ヒアリングで注意したい
ポイントについて>
ヒアリングを行なう場合は、次のポイントに注意しながら、慎重に対応していくことを基本とします。
「相談者への対応」
・プライバシーの尊重
相談を受ける際は、他者に聞かれない、見られない場所やツールで実施。
・対象者の希望・意向を確認。
同意がないかぎりは社内での情報共有をしないでほしい、加害者と引き離してほしい、などの希望を確認。
・対象者の秘密保持義務
ヒアリング対象者には、ヒアリングの内容を口外しないという秘密保持義務を徹底。
・中立性の保持
ヒアリングは、対象者とは中立の立場の者が実施。
・否定や断定の禁止
対象者の発言などを否定したり、断定的な質問の禁止。
・今後の対応やプランの説明
対象者が安心できるよう、これからの対応の流れなどについてわかりやすく説明。
「行為者への対応」
相談者への対応と同様の配慮が必要になりますが、特に次の点には注意が必要です。
・相談者が主張する内容は必ずしも事実とは限らないため、中立的な立場であることを意識して、先入観をもたずにヒアリングを行なう。
・行為者の名誉や不利益の問題もあるので、パワハラの調査対象になっていることが社内に漏れないようにする。
パワハラに該当するかの検討・判断
調査内容などをもとに、前述のパワハラの定義や3つの要素などと照らし合わせて、パワハラがあったかどうかの検討・判断を行ないます。
- ・相談者、行為者双方の言い分で不自然な点はないか。
- ・相談者、行為者双方について、虚偽の供述をする動機があるかどうか。
- ・これまで相談者がパワハラの訴えなどの行動を取らなかった理由(ハラスメントがあったと主張する日から長期間が経過している場合)。
- ・他の被害者の有無。
被害者へのメンタルケア
相談者と行為者の隔離
パワハラの事実が確認できた場合、必要であれば被害者と加害者を引き離して隔離する措置をとります。
また、調査結果が出るまでは双方を自宅待機にしたり、別々の事業所、部署、店舗等に配置転換することも検討・実施するべきです。
セカンドハラスメントの防止
セカンドハラスメントなどが起こらないよう、産業医や外部カウンセラー等も利用し、被害者の体調や精神状態などにも十分配慮しながらメンタルケアを行なっていくことも必要です。
会社の対応の説明
配置転換や休職制度の活用に関する支援を行ない、報復的な人事など不利益な取り扱いの禁止について説明を行ないます。
なお、「パワハラ防止指針」(厚生労働省)では、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行なうこととして、次のような取り組み例が明示されています。
- ・被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助
- ・被害者と行為者を引き離すための配置転換
- ・行為者の謝罪
- ・被害者の労働条件上の不利益の回復
- ・メンタル不調への相談対応などの支援
加害者への措置(処分)
加害者に対しては、次のような措置を検討し、実施します。
- ・加害者と被害者の関係回復の援助
- ・加害者への再発防止指示
- ・人事異動
- ・パワハラ防止研修の実施
なお、パワハラの程度に応じて、職務執行停止や解任、懲戒処分などの実施も検討します。
懲戒処分には次のような種類があります。
- ① けん責・戒告
- ② 減給
- ③ 降格
- ④ 出勤停止
- ⑤ 論旨解雇
- ⑥ 懲戒解雇
なお、重すぎる処分などは無効と判断される場合もあるので、注意する必要があります(労働契約法第15条、16条)。
調査報告書の作成
加害者への懲戒処分の決定、取締役会等への報告、社内での処分の公表、再発防止策の実施などのために必要があれば、調査報告書を作成します。
<コラム②調査報告書の記載項目に
ついて>
調査報告書に記載する主な項目には、次のものがあります。
- ・調査担当者や調査委員会のメンバーとその独立性
- ・調査を実施した期間と調査方法
- ・調査を実施した項目
- ・パワハラ被害の訴えの経緯と内容
- ・加害者の主張内容
- ・調査で判明した事実関係
- ・事実認定と結論
- ・パワハラ再発防止策 など
パワハラの再発防止策の検討と実施
今後、職場でパワハラ事案が発生しないよう、再発防止策を検討し、実施していきます。
パワハラ発生の原因の分析・
究明
パワハラ発生の原因や防止できなかった理由を究明し、今後の再発防止に生かしていく必要があります。
そのためには、社内のシステムや体制などに問題があるのであれば改善策を講じていきます。
就業規則や社内ルールの整備
パワハラを明確に禁止する旨を就業規則などに明記し、パワハラが発生した場合の懲戒規定を設定します。
役員や従業員への研修制度の
立ち上げと実施
「パワハラに該当する行為について」、「パワハラが起きた場合のリスク」、「どのような刑事責任に問われるのか」といった内容について定期的な研修会の実施などを通して、職場全体の意識向上を図ります。
管理体制の改善・構築・運用
パワハラ防止の周知徹底のために、社内規程、行動規範、業務マニュアル等を明確化します。
管理体制に不備があれば改善策や、新たな管理体制の構築と運用も重要です。
内部通報窓口の設置など
パワハラなどのハラスメント行為を通報できる制度・環境を整えていくことも大切です。
具体的には、「内部通報制度」の整備や構築、内部通報窓口を社内に設置するなどを検討し、実施していきます。
【参考資料】:内部通報制度(公益通報制度)の整備・運用に関する 民間事業者向けガイドライン
(消費者庁)
・内部通報窓口・公益通報窓口を弁護士に依頼するメリットとデメリット
社内での周知の徹底
パワハラを行なってはいけないこと、行為者に対して厳正に対処することなどの方針を、あらためて社内報、パンフレット、社内ホームページ等に掲載し、周知を行ないます。
パワハラは犯罪になる可能性も!
パワハラ行為そのものを規制する法律はありません。
しかし、社内トラブルでは済まされずに、パワハラが犯罪として加害者が刑事責任を追及される可能性もあることは知っておくべきです。
ここでは、パワハラが刑事上の責任を問われる可能性のある刑事罰について解説します。
名誉毀損罪(刑法第230条)
何らかの事実を摘示して被害者の名誉を傷つけた場合、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
(※2025年6月1日より前の刑法では、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金になります)
・SNS・ネットで名誉毀損された時の法的対応
侮辱罪(刑法第231条)
事実を摘示せずに被害者を侮辱した場合、侮辱罪が成立する可能性があります。
(※2025年6月1日より前の刑法では、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金になります)
脅迫罪(刑法第222条)
生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した場合、脅迫罪が成立する可能性があります。
(※2025年6月1日より前の刑法では、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金になります)
傷害罪(刑法第204条)
人の身体を傷害した(けがを負わせた)場合、傷害罪が成立する可能性があります。
(※2025年6月1日より前の刑法では、15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金になります)
暴行罪(刑法第208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった場合、暴行罪が成立する可能性があります。
刑事事件の裁判手続きの概要については、こちらのページが参考になります。
【参考資料】:刑事事件(裁判所)
パワハラ問題の解決・防止は
弁護士にご相談ください!
職場のパワハラは、判断や対応が難しい問題です。
また、被害者への対応やケア、加害者への処分、社内の環境整備、再発防止策の実施なども必要です。
被害者からの刑事・民事両方への告訴により、裁判や損害賠償といった問題が発生する可能性もあり、法的な対応が必要な場合もあります。
パワハラ問題が発生してお困りの場合や、再発防止策を検討している場合は、まずは一度、弁護士にご相談ください。
なお、会社の危機管理において、いつでも相談・対応できるよう、顧問弁護士を持つことも検討していただきたいと思います。
・顧問弁護士とは?|費用や相場・メリットについて
弁護士法人みらい総合法律事務所は全国対応で、随時、無料相談を行なっています(事案によりますので、お問い合わせください)。