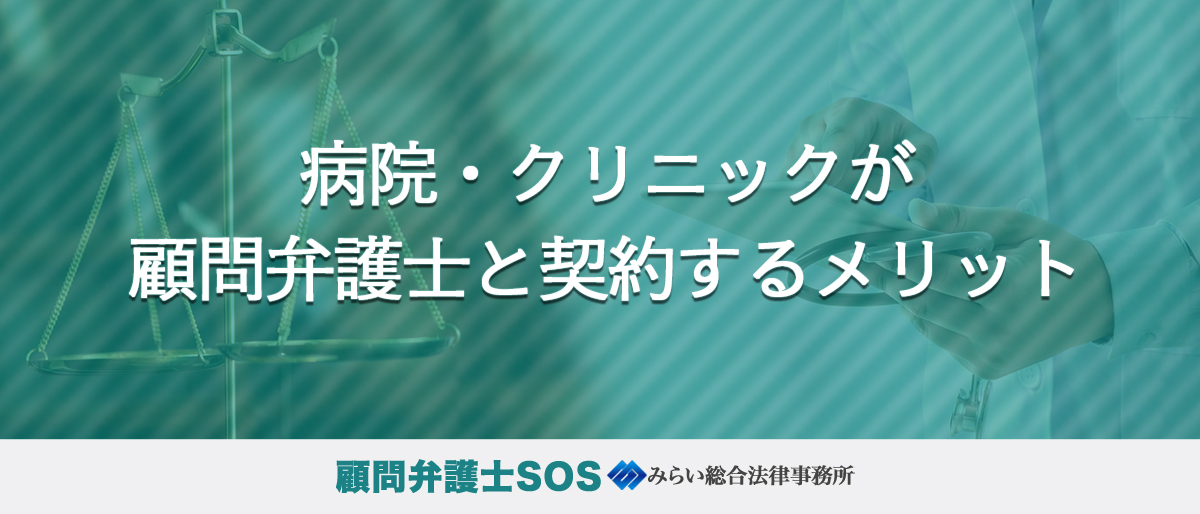病院・クリニックが顧問弁護士と契約するメリット
病院やクリニックでトラブル発生…その時、どう対応しますか?
これから、本記事では次のポイントを中心に、お話をすすめていきます。
- ①弁護士の顧問契約とスポット契約の違い
- ②病院・クリニックで起きがちな法的トラブルと顧問弁護士の必要性
- ③病院・クリニックが顧問弁護士と契約するメリット
- ④頼れる顧問弁護士の探し方
顧問弁護士については、クライアントからこんなお話を聞くことがあります。
「これまで必要性を感じたことがなかった」
「顧問弁護士は大げさな感じがしていた」
「何を頼めるのか、メリットは何なのかわからなかった」
「トラブルがなくても毎月の顧問料を支払うのは、もったいないと思っていた」
しかし、医療機関にとっては患者との間の法的リスクは、つねに背中合わせであり、医師や職員との間の労働問題も同様です。
たまたま、これまでは問題が発生していなかっただけかもしれません。
トラブル解決は時間との戦いでもあります。
いざトラブルが発生してから弁護士を探して依頼していると時間がかかってしまうため、被害の拡大も懸念されます。
その点、顧問弁護士は通常の案件よりも契約先の案件を優先的に対応していくため、迅速に問題解決をすることができます。
「備えあれば憂いなし」という、古代中国に由来する故事成語があります。
いざトラブルが発生してからでは、遅きに失する事態に直面してしまう可能性もあります。
その点、顧問弁護士と契約していれば、前もってトラブルの芽を摘みながら、リスクの管理ができるのです。
たしかに毎月の顧問契約料を支払う必要がありますが、それを補ってあまりあるメリットを顧問弁護士から得ることができます。
じつは顧問弁護士との契約はリーズナブルだといえるのです。
本記事を最後まで読み終えたなら、顧問弁護士との契約の必要性やメリットについて、リアルで明確なイメージが湧いてくるはずです。
目次
弁護士との顧問契約とスポット
契約の違いとは?
病院やクリニック(診療所)を経営・運営していると、さまざまなトラブルに直面する可能性があります。
院内・所内で解決できる問題であればいいのですが、なかなか解決できず長期化して、状況が悪化してしまう場合もあるでしょう。
特に、法律が関係する問題の場合、院内では対処できないケースも多いと思います。
そうした時は、できるだけ早期に、法律の専門家である弁護士に相談・依頼する必要があります。
しかし、いざ弁護士に相談・依頼するとなると、どのような契約をすればいいのか、よくわからないという方もいらっしゃるでしょう。
そこで、まずは弁護士との契約には「スポット契約」と「顧問契約」があることから解説していきたいと思います。
通常の弁護士とのスポット契約とは?
たとえば、病院で発生したトラブルについて、法的に解決する必要がある場合、①弁護士を探して、②トラブル解決の相談・依頼をし、③契約を交わして、④弁護士が着手、⑤解決して終了、という流れになります。
このように、継続した契約ではなく、その案件のみの短期、あるいは単発の契約を、弁護士のスポット契約といいます。
スポット契約の特徴・
メリット・デメリット
弁護士とのスポット契約の特徴、メリットやデメリットとしては次の点があげられます。
弁護士費用
- ・月額の費用は発生しない。
- ・ただし、相談・依頼のたびに費用が発生する。
- ・依頼した場合の弁護士費用は、顧問弁護士より割高になる。
対応
- ・初動対応が遅れるため、被害拡大の懸念もあり得る。
※まず弁護士を探して面談することからスタートし、事業内容の説明などを経て契約してから弁護士が案件に着手、というプロセスをたどる必要があるため。 - ・初めてのつきあいとなると、相互理解を得るためのコミュニケーションに時間がかかってしまう可能性もある。
- ・弁護士との関係は信頼関係を前提とするが、すぐに信頼関係を築ける弁護士に出会えるとは限らない。
得られる結果
- ・病院やクリニック業界の慣例や法令に詳しくないスポット弁護士の場合、一般的な解決策になってしまい、本当に必要としていた結果が得られない可能性がある。
- ・コミュニケーションや理解が不足していたために、病院側の理事長や院長、管理責任者などの真意がつかめず、最適な結果が得られない場合がある。
顧問弁護士の役割と契約すると得られるメリット
顧問契約を結び、毎月の顧問料を受け取る支ことで、病院やクリニックが直面するさまざまなトラブルを法的に解決していくのが顧問弁護士です。
顧問弁護士と契約することで、スポット契約では得られないメリットを手に入れることができます。
弁護士費用
- ・毎月の顧問料が発生する。
- ・ただし、相談・依頼の案件が増えるほどコストは抑えられるので、リーズナブルでもある。
- ・訴訟になった場合に別途支払う弁護士報酬は、通常の正規料金から割引になることが多い。
対応
- ・いつでも、気軽に、電話1本、メール1通で相談できる。
- ・顧問先の案件は優先的に対応するので、迅速な問題解決が可能。
得られる結果
- ・業界のビジネスの慣例や、病院やクリニックの内情を理解してくれているので対応がスムーズで、ニーズに合った適切な結果を得ることができる。
顧問弁護士と契約するべき5つの
理由とメリット一覧
ここでは、顧問弁護士と契約するべき理由について、さらに深掘りしていきたいと思います。
いつでも気軽に相談できる
利便性
特に、初めて弁護士に相談・依頼するとなると、気が引けてしまうところがあり、躊躇してしまう方もいます。
その点、「いつでも」「気軽に」「電話やメールで」「継続的に」相談でき、案件を依頼できるのが、顧問弁護士のメリットです。
これは、スポット契約で必要な手続きなどの手間が省けるという点においてもメリットになるでしょう。
病院・クリニックのことを
わかってくれている安心感
顧問弁護士は、病院やクリニックの「かかりつけ医」ともいえます。
少し混乱しそうですが、どういうことかというと、あなたの病院・クリニックの経営理念やビジネスモデル、職員の構成、抱える問題点などの内情をよく知ってくれているのが顧問弁護士という存在だ、ということです。
また、業界に関連する法令もあるため、病院やクリニックの経営・運営に精通している、問題となるポイントと解決策がわかっている顧問弁護士であれば、「任せて安心」ということになると思います。
優先で迅速に対応して
くれるのが顧問弁護士
顧問弁護士は、顧問契約先とつねに委任関係にあります。
そのため、通常の依頼案件よりも顧問契約先の業務を優先で行ないます。
また、緊急性の高いトラブルかどうかを法的に判断して対応できるのは弁護士だけです。
早めの対応が肝心なトラブル解決において、いかに迅速に対応できるかは非常に重要なポイントになるため、顧問弁護士と契約するメリットは大きいのです。
トラブルの予防・リスク管理もできる
病院やクリニックにとっては「予防法務」も重要です。
予防法務とは、法的なリスクを管理することで、起こり得るトラブルを未然に防ぐことをいいますが、これができるのも顧問弁護士を持つことの大きなメリットになります。
たとえば、就業規則の修正・変更、契約書のリーガルチェック、法律の改正情報など、トラブルが起きる前に対処することが「転ばぬ先の杖」となるわけです。
結果として顧問弁護士は
リーズナブル
コンプライアンスの遵守も含め、法的な問題に対応するために院内に法務部を設置したり、法的知識のある有資格者を雇用するとなると大きな支出になります。
また、相談・依頼件数が増えれば、弁護士とのスポット契約では費用がかさんでしまいます。
その点、結果としてリーズナブルに安心を得ることができるのが、顧問弁護士を持つことだともいえるのです。
なお、各法律事務所によってシステムは違いますが、多くの場合、
- ・通常の法律相談や簡単な書類作成などは一定量までは無料。
- ・訴訟にまで発展した場合の弁護士報酬は正規料金から割引される。
といったメリットも顧問弁護士にはあるので、一度問い合わせてみることをおすすめします。
【参考資料】:顧問弁護士(日本弁護士連合会)
病院やクリニックでよくある
トラブルと顧問弁護士に相談できる
内容とは?
一般の企業とは違った、病院やクリニックに特有の問題・トラブルがあります。
ここでは、病院やクリニックで起きがちなトラブルを中心に、顧問弁護士に相談・依頼できる内容について解説していきます。
ペイシェントハラスメント
医師や看護師など病院の職員が適切な対応をしていても、患者やその家族から理不尽ともいえるクレームを受けることがありますが、これを「ペイシェントハラスメント」といいます。
- ・患者に対するスタッフの対応への
クレーム - ・治療方針へのクレーム
- ・入院中の待遇へのクレーム
- ・医療ミスを主張するクレーム など
こうしたクレームを放置していたり、初期対応を間違ってしまうと、トラブルが肥大化、長期化しかねません。
また、病院のスタッフが対応に追われてしまうことで、他の患者への対応や病院の運営にまで影響を及ぼす場合もあります。
このような場合は、顧問弁護士に初期対応から解決までを依頼することができます。
未払い医療費の回収
病院やクリニックでは医療費の未払い問題も発生しています。
医師や歯科医師が診療行為を求められたときは、医師法(第19条1項)および歯科医師法(第19条1項)により、正当な理由がない限り、これを拒んではならないとされています。
これを「応召義務」というのですが、であれば医療費の未払いがある患者に対しても、それを理由に診療を拒めないことになります。
ただし、「令和元年12月25日厚生労働省通達」において、次の明示がされています。
- ・以前に医療費の不払いがあったとしても、そのことのみをもって診療しないことは正当化されない。
- ・しかし、支払能力があるにもかかわらず悪意を持ってあえて支払わない場合等には、診療しないことが正当化される。
- ・具体的には、保険未加入等医療費の支払い能力が不確定であることのみをもって診療しないことは正当化されないが、医学的な治療を要さない自由診療において支払い能力を有さない患者を診療しないこと等は正当化される。
- ・また、特段の理由なく保険診療において自己負担分の未払いが重なっている場合には、悪意のある未払いであることが推定される場合もある。
【参考資料】:「応招義務をはじめとした診察治療の
求めに対する適切な対応の在り方等について」
(令和元年12月25日厚生労働省通達)
診療費の未払いは法的な問題にもなってくるため、顧問弁護士に相談・依頼することが解決の近道になります。
職員(スタッフ)との間の
労使トラブル
一般企業と同様に、病院やクリニックでも労使間におけるトラブルは発生頻度が高いもののひとつです。
特に小規模のクリニックなどでは、人事労務の部署がない、担当者がいないということもあるでしょう。
そうすると、法務面の整備ができておらず、就業規則や労働条件通知書が不完全、ハラスメントの相談窓口が設置されていないなどの問題から、次のようなトラブルが発生しがちです。
- ・未払い残業代を主張してきて請求された。
- ・不当解雇を主張され訴訟を起こされた。
- ・パワハラ、セクハラなどで損害賠償を請求された。
- ・労災申請に関するトラブル。 など
こうした労使間のトラブルは病院やクリニックの運営に大きな影響を及ぼす可能性もあるため、できる限り早急に対処していくこと、また未然に防いでいくことが大切です。
【参考資料】:労働基準法のポイント(厚生労働省)
労働基準法に関するQ&A(厚生労働省)
・普通解雇はどんな場合にできるか?
・勤務成績不良、能力不足を理由とする普通解雇とは?
・労働審判は、なぜ早期に対応しなければならないのか? 【弁護士解説】
(別サイト 労働災害SOS)
・労災保険給付の手続と給付の内容
SNSなどの誹謗中傷への対応と対策
SNSなどのインターネット上で企業が第三者から誹謗中傷を受けるケースも、近年では増加傾向にあります。
病院やクリニックが誹謗中傷を受けた場合、次のようなリスクが生じる可能性があります。
- ・社会的な信頼度や医療機関としての価値の低下
- ・売り上げの低下・業績の悪化など経営への悪影響
- ・患者や取引先からの信用の低下や契約解除
- ・職員(スタッフ)のモチベーションの低下
- ・今後の採用活動への悪影響
- ・さらなる炎上リスク など
投稿内容の削除請求、発信者の情報開示請求などは、できるだけ早急に、法的措置が必要になってくるため、顧問弁護士に依頼するのが最善の対応になります。
行政の個別指導・監査への対応
病院やクリニックには、厚生局から「個別指導」や「監査」が行なわれます。
個別指導とは、医療機関や保険医に対して適切な診療を促し、ルールの周知徹底を図るために行なうもので、ここで要監査と判断された場合は、監査が実施されます。
監査とは、保険診療や診療費の請求で不正などを行なっていないかチェックするもので、結果によっては保険指定を取り消される場合もあります。
顧問弁護士には、これらへの適切な対応も依頼することができます。
顧問弁護士に相談・依頼できる内容一覧
上記以外にも、病院やクリニックの経営・運営ではさまざまな問題が起きる可能性があります。
たとえば、次のような問題を抱えておられる方もいらっしゃるでしょう。
- ・情報漏洩トラブル
- ・広告に関わる問題
- ・M&Aによる買収・合併
- ・事業承継
- ・遺産相続
- ・理事や院長、医師の方などの
プライベートな問題 など
顧問弁護士に依頼できる内容は、それぞれの法律事務所によって変わってくるため、ここでは、みらい総合法律事務所でお受けしている相談内容の一部について、ご紹介します。
労働問題
- ・従業員から残業代請求(労働審判・裁判)をされた時の対応。
- ・従業員が逮捕・拘留された場合の雇用関係、解雇などに関する対応。
- ・従業員の加入する労働組合からの団体交渉の申入れに対する対応。
契約書・就業規則などの作成やリーガルチェック
利用者または取引先・行政との間の契約書、院内の就業規則など作成、内容のリーガルチェック。
会社法関連
- ・会社法に関する経営全般へのアドバイス。
- ・新規事業を始める際の法的問題の有無等のアドバイス。
損害賠償問題
利用者との間の損害賠償問題、また誹謗中傷などによる第三者との間の損害賠償問題への対応。
事業承継・M&A
- ・後継者への事業承継やM&Aに関する法的問題の相談。
- ・M&AにおけるDD(デューデリジェンス)の実施。
債権回収
利用者や取引先との間の債権の早期回収対応。
不動産取引
購入した不動産や賃借物件に関するトラブルへの対応。
税務訴訟
税務で起きた訴訟への手続きや解決実務。
相続紛争
相続問題で起こった争いの解決など。
職員向けの各種研修・
セミナーの開催
労務問題、コンプライアンス(企業倫理)、ハラスメントなどについて、職員向けの研修やセミナーの実施。
【参考資料】:医療法における病院等の広告規制に
ついて(厚生労働省)
医療法における広告規制の現状について
(厚生労働省)
顧問弁護士を選ぶ際に
おさえておくべきポイント
顧問弁護士を探して契約する際、当然ですが、弁護士であれば誰でもいいわけではありません。
そこで、顧問弁護士を選ぶ際の注意ポイントについて、お伝えしたいと思います。
弁護士のランキングや
口コミサイトを簡単に
信用してはいけない
インターネットで検索すると、弁護士のランキングサイトや口コミサイトが出てきますが、これらは民間企業が営利目的で運営していることが多く、掲載者から広告費を得ているため金額によって順位が決まっていて、都合の悪い内容は書かれません。
つまり、こうしたサイトは、実際はあてにならないということです。
弁護士と実際に会って面談してみる
これから病院の顧問弁護士を依頼するのですから、やはり契約の前には実際に会って、面談をすることをおすすめします。
その際、医療業界や病院・クリニック経営について質問をしてみてください。
納得のいく回答があるなら、業界の知見があることがわかりますし、実際に会うことで弁護士の人となりもわかると思います。
契約するに相応しい弁護士を
判断する4つのチェック
ポイント
有名無名を問わず、弁護士を選ぶ際には、自院のニーズに合致しているかどうかを確認するべきです。
その際に重要なポイントは、次の4つです。
- ①業界の知見があり、自院のことを理解して
くれるか。 - ②自社のニーズに合った実績があるか。
- ③対応が速く、説明がわかりやすいか。
- ④人間的な相性が合うか。
詳しい内容は、こちらの記事でも解説していますので参考にしてください。
・顧問弁護士とは?|費用や相場・メリットについて
顧問弁護士の費用の相場は?
実際のところ、顧問契約料はそれぞれの法律事務所によって違ってきますが、平均的な月額は5万円程度の場合が多くなっています。
電話でもメールでも、ファーストコンタクトの際に、まずは確認してみるといいでしょう。
【参考資料】:弁護士報酬について(日本弁護士連合会)
なお、顧問弁護士にかかる費用は必要経費や損金として控除の対象になることを知っておいてください。
税務申告では、「支払手数料」「業務委託料」「支払顧問料」などの勘定科目で処理します。
国税庁のサイトで確認されるといいでしょう。
【参考資料】:No.2798 弁護士や税理士等に支払う
報酬・料金
No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・
料金等 (税理士法人等に報酬を支払った場合)
顧問弁護士と契約するメリット
まとめ
最後に、顧問弁護士と契約するメリットについてまとめますので、参考にしていただければと思います。
- ・法的な問題が発生した場合、必要な時にいつでも、継続的・優先的に相談できる。
- ・実際に起きたトラブルの緊急性を法的に判断して、迅速に解決できる。
- ・トラブルの都度、弁護士を探して依頼するなどの労力やコストを省ける。
- ・起こり得る法的トラブルを事前に予防し、リスク管理ができる。
- ・自院のニーズに合った法務サービスを受けることができる。
- ・院内に法務部を設置したり、専任者を雇用するなどのコストを削減できる。
- ・経営者が普段気づかない会社の問題点を指摘してもらい、早急に改善できる。
- ・経営者自身や職員が抱える法的な問題についても相談できる。
- ・通常の法律相談や簡単な書類作成は無料になる場合が多い。
- ・訴訟に発展した場合などの弁護士報酬は割引になることが多い。
- ・法改正など最新の法律情報に関するアドバイス・サポートも受けられる。
- ・トラブルの相手方に精神的、実務的なプレッシャーをかけることができる。
みらい総合法律事務所は全国対応です。
関東圏だけでなく、地方の事業者の方からのご相談も随時お受けしていますので、まずは一度、お気軽に、ご連絡いただければと思います。