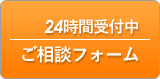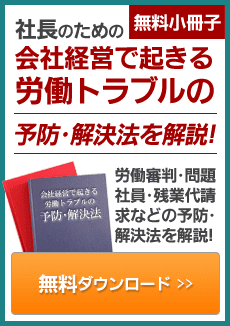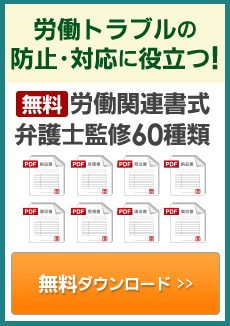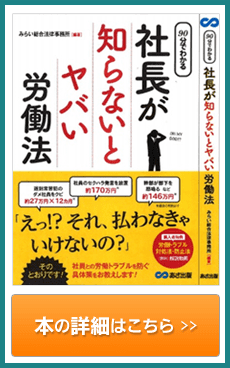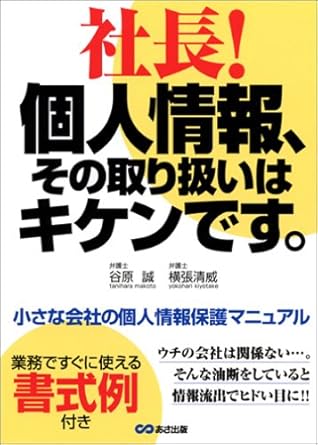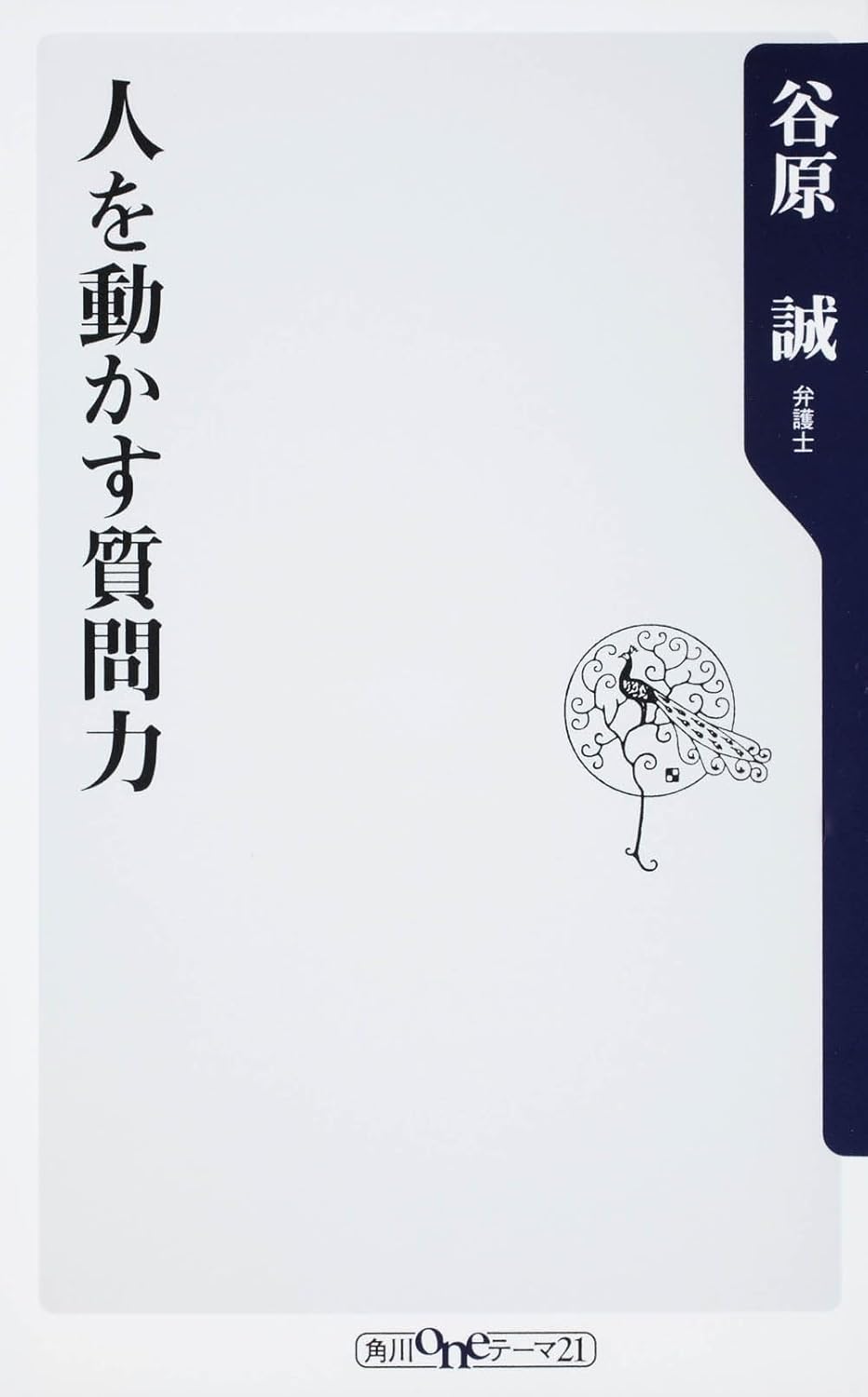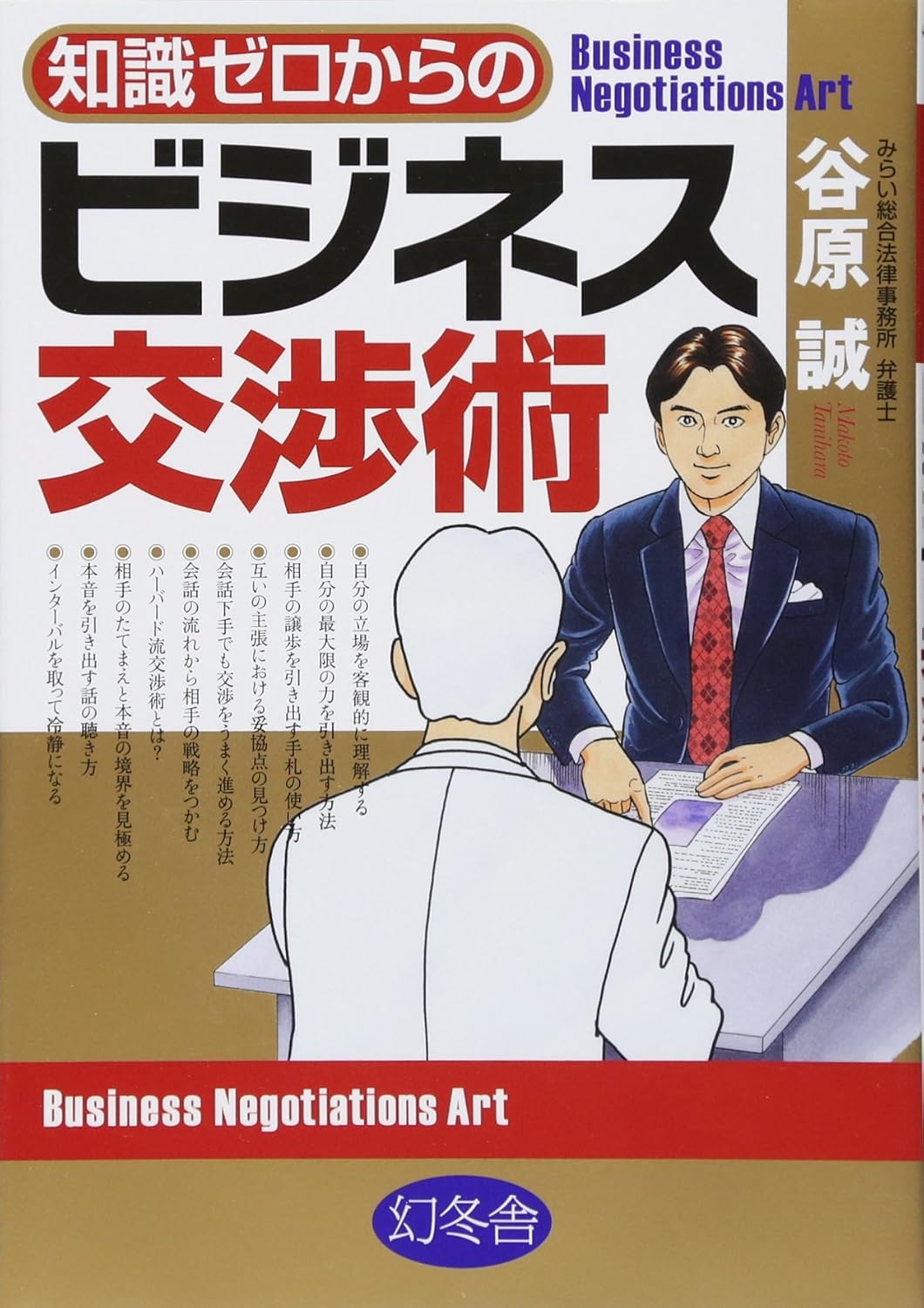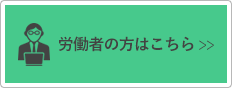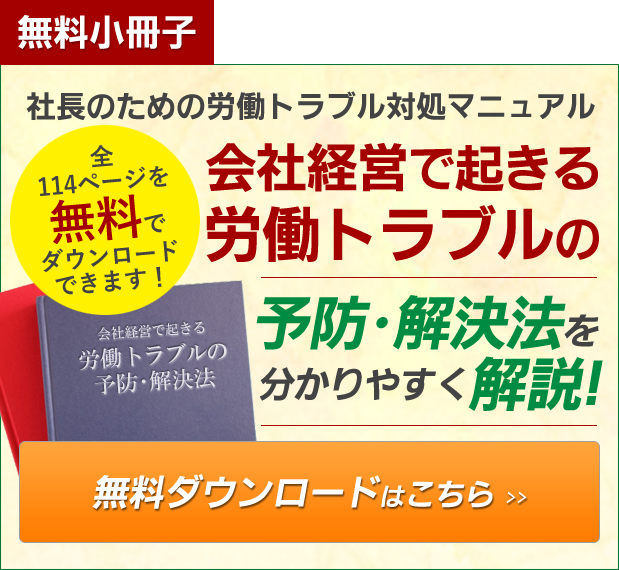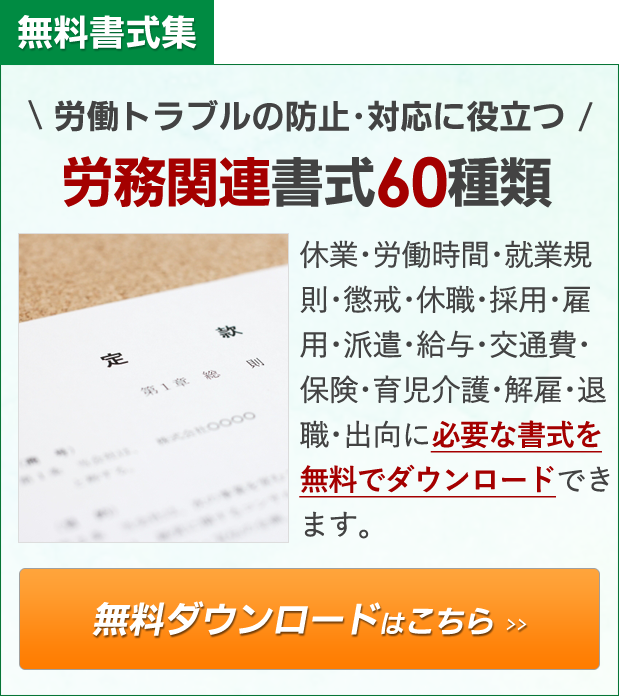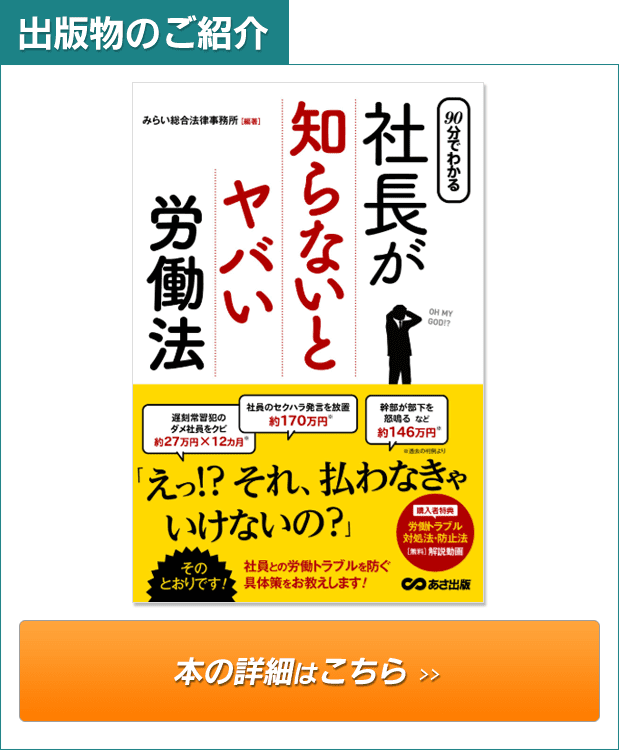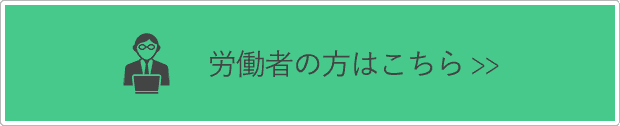労働審判で調停を決裂させ不利な決定が出たときはどうすればいい?
目次
はじめに
労働審判で調停を決裂させた場合には、裁判所によって審判がなされます。この審判が、会社にとって不利なものであった場合には、会社は、速やかに裁判所に異議を申立て、その後に続く訴訟に対しての準備を行う必要があります。
弁護士に委任していない場合には、大至急弁護士を探し、訴訟に対応する必要があります。
労働審判で調停が決裂した場合について
労働審判とは、企業と個々の労働者との間の個別労働紛争について、裁判官1名と労働関係の専門的な知識経験を有する者2名によって構成される労働審判委員会が、原則として3回以内の期日で審理し、調停による解決を試み、調停が成立しない場合には労働審判を行うという手続です。
労働審判も裁判所が介在する手続とはなりますが、両当事者の話合いによって紛争を解決できないか、労働審判委員会によって調停が試みられますので、柔軟な紛争解決が可能です。
しかしながら、両者の意見が折り合わず、合意が成立しない場合には、それまでに裁判所にあらわれた事実をもとに、労働審判委員会が、審判という形で裁判所としての判断を下します(労働審判法20条1項)。
この労働審判においては、当事者間の権利関係が確認され、金銭の支払い、物の引渡しその他の財産上の給付を命じ、その他個別労働関係民事紛争の解決をするために相当と認める事項を定めることができることとされています(同条2項)。
労働審判は主文及び理由の要旨等を記載した審判書で行われることとされていますが(同条3項)、両当事者がそろう審判期日において、労働審判官が口頭で告知することが法律上認められており(同条6項)、口頭で告知される方法で行われるのが通常となっています。この場合、審判の前の調停の段階において理由が説明されます。
審判の効力
労働審判手続きの当事者は、期日において労働審判の告知がされた日の翌日から、2週間の不変期間内に、裁判所に異議の申立てをすることができますが(法21条1項)、異議を申立てないで不変期間を徒過してしまうと、審判が確定してしまいます。
口頭での告知がなされた場合には、裁判所から書面が届く、などの手続きはないので、期限を徒過してしまわないよう、最大限に注意する必要があります。
どちらの当事者からも異議申立がなく、不変期間が経過し、労働審判が確定すると、その労働審判は裁判上の和解と同一の効力を有することとなります(同条4項)。
裁判上の和解とは、訴訟手続きの進行中に裁判官が関与して当事者間で和解を締結させ、これにより継続している訴訟を終了させる手続きをいいます。
和解という言葉が付いていますが、裁判所において、裁判所の関与の下になされるため、その効力については、確定判決と同一の効力を有すると法律上定められています(民事訴訟法267条)。
確定判決と同一の効力ですので、その効力により、法律関係を変化させる効力を持ち、また、金銭等を給付させることを内容するものについては、これを債務名義として、強制執行をすることが可能です(民事執行法22条7項)。
このように、裁判上の和解は大きな効力を持っており、労働審判も確定してしまうとこれと同じ効力を持つのです。
異議申立をする
そのため、会社にとって不利な審判がなされた場合、会社は異議申立を行う必要があります。異議申立期間は労働審判の告知がされた日から2週間であり、これは不変期間であって延長されることはありませんので、必ずこの期間内に異議申立を行う必要があります。
そしてこの異議申立は、書面により行うこととされています(労働審判規則31条1項)。
異議申立をした場合には
労働審判に対し適法な意義の申立てがあったときは、労働審判手続の申立てに係る請求については、当該労働審判手続の申立てのときに、当該労働審判が行われた際に労働審判事件が継続していた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなすとされています(労働審判法22条1項)。
これは、労働審判が申立てられたときにさかのぼり、民事訴訟が提起されたものと扱われるということです。
民事訴訟となれば、その裁判が、最終的な司法判断の場となります。労働審判においては、柔軟な紛争解決が目指され、話合いによる合意形成で紛争を解決する調停が試みられましたが、民事訴訟となれば、原則として、お互いに民事訴訟の規則、ルールに則り、法律的に主張を構成し、法的事実の主張を緻密に行っていかなければなりません。
会社として主張したい事柄をいくら主張しても、それが民事訴訟のルールに則らないものであったり、法律的に構成されていないものであったりすれば、裁判所がその主張を認めることはありません。
そして、この訴訟に至る段階においては、相手方には弁護士が付いていることが通常であって、相手方の弁護士が行う法的主張に対応することは、弁護士以外には困難です。
したがって、労働審判に異議を申立て、民事訴訟となった場合には、早急に弁護士に訴訟代理人として弁護士を立てなければ、会社は圧倒的に不利な立場で訴訟を遂行することになってしまいます。
弁護士を選任するタイミングについて
しかし、この異議申立のタイミングで弁護士を選任することは、簡単ではありません。異議申立期間は2週間しかなく、異議申立をすればすぐに訴訟手続きへと移行しますので、ゆっくりと弁護士探す時間がないのです。
会社を労働問題から守るには、労働問題に強い弁護士を選任する必要がありますが、そのような弁護士をすぐに見つけ、委任することができるとは限りません。
また、仮に弁護士に委任できたとしても、その弁護士がベストな弁護活動を行うには、訴訟のタイミングからでは準備期間が圧倒的に足りません。訴訟の段階から弁護士に委任をした場合に、その弁護士が労働審判の段階から関与した場合と比べて、会社にとって良い結果となることはほとんどないといえるでしょう。
したがって、労働審判が起こされてしまった場合には、一日でも早く弁護士を選任することが、会社を守るために大事なのです。