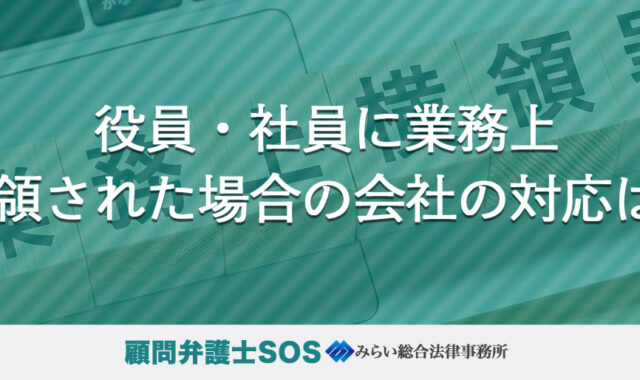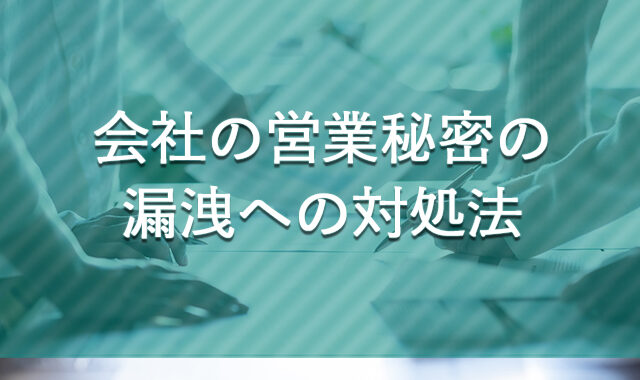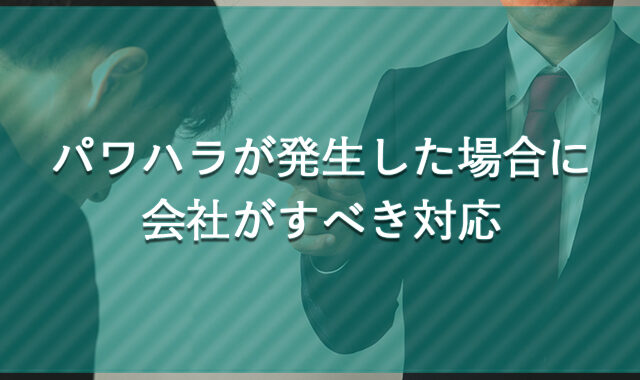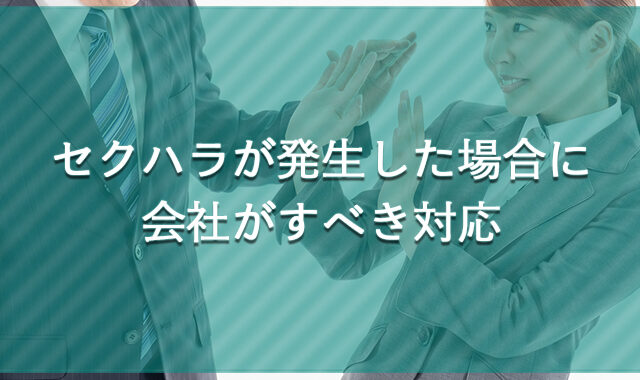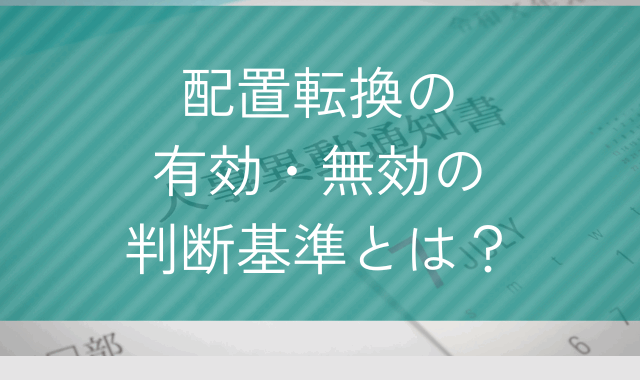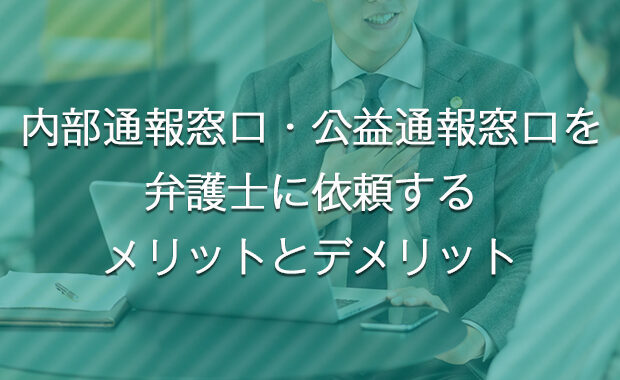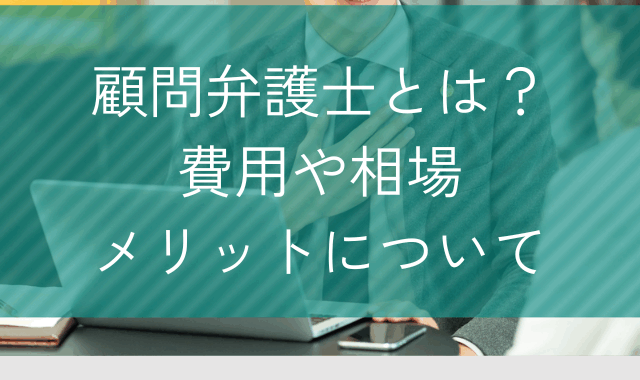退職勧奨のやり方は?
「能力不足や勤務態度不良などの問題があり、辞めてほしい従業員がいる」、「業績不振などにより人員整理をしたい」……こうした場合に、会社が従業員に退職を促す手続きに「退職勧奨(たいしょくかんしょう)」があります。
解雇の前段階として行なわれるのが退職勧奨で、会社が従業員を説得して退職を促し、合意を得たうえで解約あるいは辞職としての退職をさせるのが一般的だといえます。
メリットとしては、解雇とは違い社員の同意のうえなので法的なリスクが少ないという点があげられます。
ただし、デメリットもあるので注意が必要です。
退職するかどうかは社員の自由意思のため、会社が強制した場合、裁判では不当な退職強要として違法と判断される可能性が高いといえます。
違法とされた場合は、「退職の合意の取消し」、「退職となってから無効とされるまでの賃金の支払い」、「相手方への慰謝料の支払い」が認められてしまう可能性があります。
そこで本記事では、退職勧奨について次の項目を中心に包括的に解説していきます。
- ・退職勧奨の概要
- ・退職勧奨の条件と交渉項目
- ・会社にとってのメリットとデメリット
- ・退職勧奨のやり方・進め方
- ・トラブルになりがちな事例
- ・退職勧奨に関する裁判例
- ・従業員に拒否された場合の対応 など
目次
退職勧奨についての基礎知識
退職勧奨の概要/
解雇との違いは?
退職勧奨とは、企業(使用者)が従業員(労働者)に対して退職を促す行為を指します。
これは、あくまで「双方の合意による退職」を目指すものであり、解雇とは異なり、従業員の同意が必要です。
企業の経営上の都合や従業員の勤務態度、能力などを理由に行なわれることが多く、整理解雇の前段階として活用されるケースもあります。
勤務不良などで解雇が検討されている労働者に対し、解雇をめぐるトラブルを防止する目的で退職を促したり、中高年層に勇退を促す場合などに行なわれることも多く、俗に「肩たたき」と呼ばれることもあるでしょう。
一方、解雇というのは従業員の同意なく、企業からの一方的な通知により雇用契約を終了させることで、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇があります。
<退職勧奨と解雇の主な違い>
| 項目 | 退職勧奨 | 解雇 |
|---|---|---|
| 同意の有無 | 必要 (合意退職) |
不要 (企業の 一方的意思) |
| 法的リスク | 比較的低い | 高い (解雇無効のリスク) |
| 退職理由 | 会社都合 退職 |
解雇理由が必要 |
退職勧奨に至る理由とは?
企業が従業員に退職勧奨をするに至るには、次のような理由があげられます。
- ・従業員の能力不足
- ・従業員の勤務態度の問題
- ・周囲の人間(上司や同僚など)とのトラブル(協調性不足やハラスメント行為など)
- ・信頼関係の喪失(企業秘密の漏洩・横領・経歴詐称・名誉毀損など)
- ・経営上の理由(経営悪化・不採算部門の統合や廃止など)
退職勧奨を行なう企業側の
メリットとデメリット
企業が従業員に退職勧奨する場合、次のようなメリットとデメリットが考えられます。
メリット
- ・解雇よりも労働トラブルのリスクが低い。
- ・円満退職により、職場の雰囲気や他の従業員の士気を保てる。
- ・会社都合退職として従業員にも一定のメリットがある。
デメリット
- ・合意が得られなければ成立しない。
- ・交渉に時間とコストがかかる可能性がある。
- ・条件次第では金銭的負担が大きくなる。
- ・適切に行なわないと労働トラブルに発展する可能性もある。
解雇により従業員を辞めさせると「不当解雇」として訴えられ、裁判では金銭の支払いを命じられる場合があります。
しかし退職勧奨の場合、法的リスクは少なくなるのは大きなメリットです。
いずれにせよ、退職勧奨は企業と従業員の双方にとってデリケートなテーマです。
法的リスクを回避しつつ、誠実かつ丁寧に進めることが何より重要です。
退職勧奨の条件提示と交渉項目
会社が退職勧奨を行なうことは自由であり、そのやり方について法律上の定めなどはありません。
また、労働者が退職勧奨に応じるかどうかは任意であり、応じる義務はありません。
つまり、退職勧奨は会社側と従業員側の双方の任意で行なうことを前提としているわけです。
ただし、雇用における力関係は会社側が上位に立っていることを考えると、退職勧奨のやり方によっては労働者が退職を強要されていると感じてしまうケースもあり、労働トラブルに発展する可能性もあります。
そこで、退職勧奨に応じてもらうためには、従業員にとって納得できる条件提示などが必要な場合があります。
- ・退職勧奨の理由の明示
- ・退職時期の調整
- ・未消化有給休暇の買取
- ・退職金の上乗せ
- ・再就職支援(アウトプレースメント) など
労働者に退職に応じてもらうために、一般的には退職金に数か月分の賃金を上乗せした特別退職金などを支給するといった方法がとられます。
退職勧奨の進め方と注意するべき
ポイント解説
退職勧奨はどのように
進めていくか?
退職勧奨は、慎重かつ計画的に進める必要があります。
一般的には、次のようなステップを踏みながら進めていきます。
退職勧奨の方針を決定し
社内で共有
退職勧奨が会社の総意であることを従業員に認識してもらうためにも、対象者・理由・条件などを明確にし、会社の幹部や直属の上司などで共有しておきます。
面談の準備
退職理由や条件を整理し、記録を残すなどして面談の準備を進めます。
「どのような問題があるのか」、「どういった影響が出ているのか」なども明確にしておき、対象者に説明できるようにしておきます。
初回面談
対象者と面談を行ない、問題点の説明と退職の提案をします。
退職強要にならないよう、ここでは即答は求めないようにします。
なお、状況によっては、面談内容は録音をしておき、議事録として証拠化しておきます。
録音せずに、議事録のみを残すという方法もあります。
検討期間の付与
数日〜1週間程度の検討期間を与え、再面談の日程を伝えます。
再面談と条件交渉
従業員が退職に応じる意向を示した場合は、退職時期や金銭条件を調整して決定していきます。
退職届の受理・合意書の取得
あとになってトラブルが発生しないように「退職届」は必ず提出させるようにします。
退職届は本人の意思で退職すること、解雇ではないことの証明になるものだからです。
また、単なる退職ではなく、退職の条件がある場合は、書面で合意内容を明確化した「合意書」を作成し、取り交わしておくといいでしょう。
合意書には、双方合意のうえでの退職であること、退職時の条件、清算条項、守秘義務条項などを規定しておきます。
退職勧奨でやってはいけない
4つの注意ポイント
企業側は、退職勧奨を行なう際は次の点に注意する必要があります。
即答を求めたり
強要してはいけない
従業員が退職する意思がないことを表明した場合には、新たな退職条件を提示するなど特段の事情がない限り、その場での勧奨を一度中断して時期を改めます。
退職勧奨は何度も
長期間行なわない
勧奨の回数、時間については、説明や交渉に通常必要な限度に留め、ことさらに多数回あるいは長期にわたらないようにします。
退職させるために
配置転換などしてはいけない
従業員を退職させるために、配置転換や仕事を取り上げて閑職に回す、他の従業員から隔離するといった対応をしてしまう会社も見受けられますが、これは訴訟など大きな法的リスクと直結するため行なってはいけません。
労働者に精神的苦痛を
与えないように配慮する
労働者の名誉感情を害することがないように十分な配慮をし、労働者に精神的苦痛を与えるなど自由な意思決定を妨げるような言動をしないようにします。
従業員の尊厳を損なわない対応が、のちのトラブル防止にもつながります。
問題となる退職勧奨とトラブル事例
パワハラ・退職強要…
退職勧奨が違法とされるリスク
企業側が退職勧奨を適切に行なわないと、「退職強要」や「不当解雇」、「パワハラ」として従業員側から訴えを起こされる可能性があります。
裁判例には、勧奨退職の方法が執拗で半強制的なものであった場合、違法行為として使用者(企業)の不法行為責任を認めたものが多くあります。
退職勧奨が違法とされると、次のような問題が降りかかってくる可能性があります。
- ・退職の合意を無効とされた
- ・退職となってから無効とされるまでの賃金支払いが認められた
- ・相手方への慰謝料の支払いを命じられた
違法と判断されるおそれのある退職勧奨とは?
企業側が次のような理由で従業員に退職勧奨をすると違法と判断される可能性があります。
- ・会社の不正を公益通報窓口などに通報した
- ・パワハラ・セクハラを内部通報窓口などに相談している
- ・労働組合への加入
- ・労災申請をした
- ・妊娠や出産など性別による差別
- ・メンタル不調で治療中 など
退職強要・パワハラと
判断される
可能性がある言動とは?
退職勧奨を行なう際、次のような言動は退職強要やパワハラと判断される可能性があるため避けるべきです。
- ・「退職しなければ解雇する」
- ・「お前は給料泥棒だ」
- ・「他の従業員の迷惑だ」
- ・「退職に応じなければ退職金は支払わない」
- ・「会社に残っても仕事はないよ」
- ・「産休や育休を取るならやめてくれ」
- ・退職に応じるまで帰宅させない
- ・多数で取り囲んで圧迫する など
裁判になった場合、「従業員は会社の説明や発言により、解雇されると誤信して退職届を提出した」として、退職の合意の無効の判断をされる場合などもあるので注意が必要です。
退職勧奨が違法と判断された
裁判例
ここでは、企業が行なった退職勧奨について、従業員の自由意思を侵害するような言動や心理的圧力が問題視された裁判例を紹介します。
<違法と判断された退職勧奨の裁判例>
| 裁判所・ 判決日 |
退職勧奨の内容 | 結果 |
|---|---|---|
| 大阪地裁・ 平成11年 10月18日 |
大声を出したり、机を叩いたり。8時間の面談。 | 慰謝料 50万円 |
| 金沢地裁・平成13年 1月15日 |
退職勧奨を拒否するも、従業員の親族に説得するよう働きかけた。 | 慰謝料 20万円 |
| 神戸地裁 姫路支部・平成24年 10月29日 |
執拗な退職勧奨。「ラーメン屋でもしたらどうや」などの発言。 | 慰謝料 100万円 |
| 横浜地裁・令和2年 3月24日 |
侮辱的発言による名誉感情の侵害 | 慰謝料 20万円 |
これらの判例から、退職勧奨が違法と判断されるポイントとしては次の点があげられます。
- ・退職勧奨が「対等な話し合い」から逸脱している。
- ・心理的圧力や人格否定となる威圧・侮辱・脅迫的な言動。
- ・退職の意思表示が錯誤・強迫に基づく場合。
従業員に拒否された場合の
対応について
退職勧奨はあくまで任意のため、従業員に拒否された場合、企業側は次の点に注意する必要があります。
注意指導・教育の継続
再度、退職勧奨に至った経緯(従業員側の問題点)をしっかり伝え、本人に改善を促します。
なお注意するべきは、注意指導が退職に応じなかったことへの報復と捉えられないように配慮することです。
懲戒処分の検討
注意指導を繰り返しても改善がみられない場合は、懲戒処分を検討します。
就業規則に基づき段階的に行なうことが大切で、まずは戒告やけん責など軽い処分から課していき、最終的に解雇を検討するのがいいでしょう。
なお、「退職に応じなければ解雇する」というようなペナルティ的な話をするのではなく、会社として「なぜ退職してほしいのか」という「退職してほしい理由」に焦点を当てて説明することも重要になります。
最終的には解雇も視野に入れる
最終的は解雇を検討し、就業規則に基づき解雇手続きを進めます。
ただし、解雇権の濫用で不当解雇と判断されないためには「客観的・合理的な理由」と「社会通念上、相当であると認められる理由」が必要(解雇権濫用法理)となります。
退職勧奨でお困りの場合は
弁護士に相談してください!
ここまでお話ししてきたように、退職勧奨は企業と従業員の双方にとって非常にデリケートなものです。
法的リスクを回避しつつ、誠実かつ丁寧に進めることが何より重要で、従業員の尊厳を損なわない対応が後のトラブル防止にもつながります。
- 「退職勧奨について適切な進め方をもっと詳しく知りたい」
- 「合意書のリーガルチェックを依頼したい」
- 「従業員から不当として訴えられてしまったので対応をお願いしたい」
このような場合は、早急に対応していくためにも労務問題に強い弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。
弁護士法人みらい総合法律事務所は全国対応で、随時、無料相談を行なっています(事案によりますので、お問い合わせください)。
顧問弁護士についてのご相談も、いつでもお受けしていますので、まずは一度、気軽にご連絡ください。