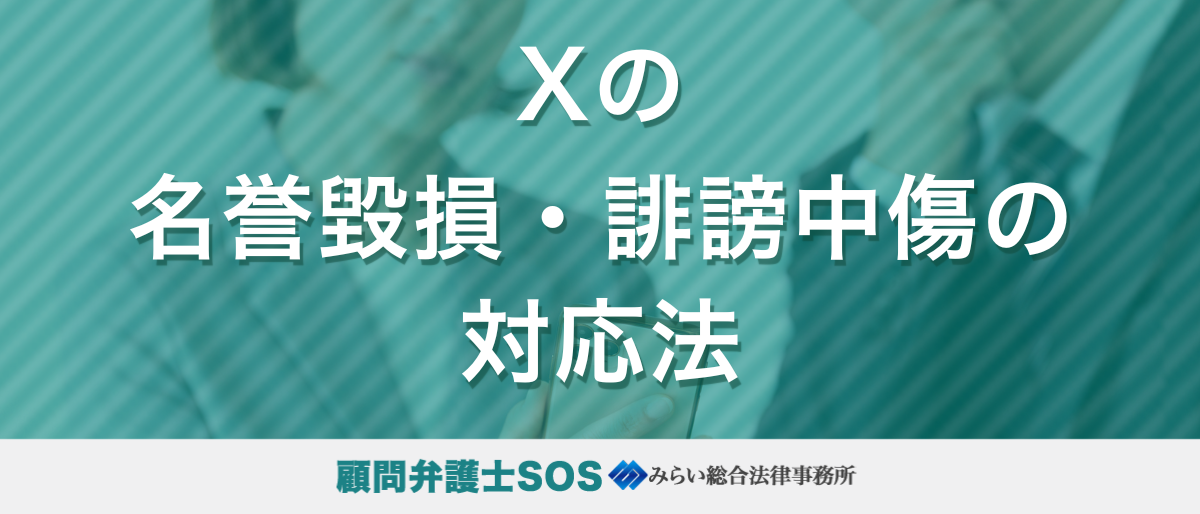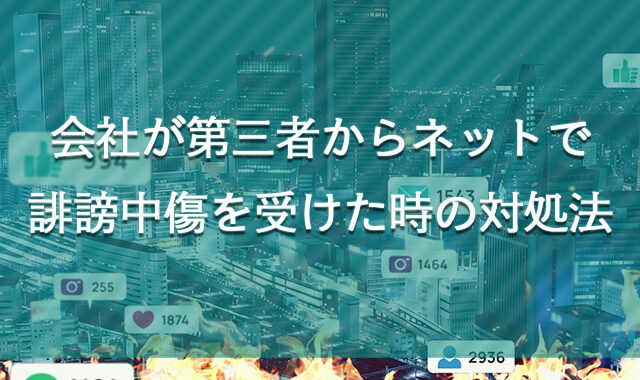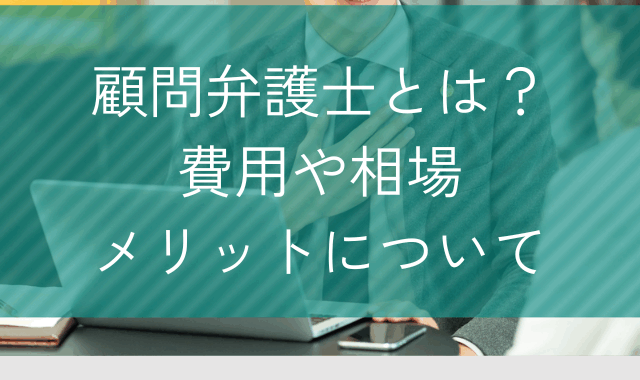X(旧Twitter)の名誉毀損・誹謗中傷の対応法
SNSで広がる誹謗中傷投稿による被害
世界で、もっとも利用されている(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)のひとつである「X(旧Twitter)」。
短文で投稿でき、画像や動画を共有できる手軽さがあり、匿名性が高いこともあって人気の高いコミュニティサイトです。
しかし、その利用頻度に比例して、さまざまなトラブルが増加しています。
その1つが、誹謗中傷の問題です。
Xでの誹謗中傷は、その拡散性の高さから、想像以上の被害と悪影響を、あなたに及ぼす可能性があります。
会社が誹謗中傷を受けた場合は、正常な企業運営に支障をきたし、大きな損害を被ってしまいかねません。
また、誹謗中傷を受けた場合に正しい対応をしないと、二次被害などさらなる損害を被ってしまうリスクもあります。
名誉毀損による法的措置
Xの誹謗中傷投稿をやめさせ、繰り返させないためには、投稿者の身元を特定し、刑事と民事の両方で法的責任を追及していくことを検討します。
誹謗中傷で加害者に科されるものには「名誉毀損罪」があります。
刑事告訴をして、刑事裁判で犯罪と認められれば、加害者には3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。
また、民事では相手方に損害賠償請求をすることができます。
そこで本記事では、SNSの中でも日本での利用人口が多い「X(旧Twitter)」にフォーカスして、次の項目を中心にお話ししていきます。
- 誹謗中傷の内容や被害の実例
- 誹謗中傷への正しい対応策(法的措置)と手順
- 刑事事件で適用される罪名と罰則
- 民事裁判で相手方に対して
請求できること - 被害者がやってはいけないことと
注意ポイント
ぜひ最後まで読んでいただき、適切な判断、対応を行なっていただきたいと思います。
目次
SNSでの誹謗中傷による被害を考察
X(旧Twitter)が設けている
ガイドラインの内容
X社は、独自のルールとポリシーのガイドラインを設定しています。
項目について、主なものをピックアップしてみます。
安全性
- 暴力的な発言
- 攻撃的な行為/嫌がらせ
- ヘイト行為 など
プライバシー
- 個人情報
- アカウントの乗っ取り など
信頼性
- プラットフォームの操作およびスパム
- 誤解を招くアイデンティティや虚偽のアイデンティティ
- 合成または操作されたメディア など
【参考資料】:ルールとポリシー(Xヘルプセンター)
【参考資料】:Xルール(Xヘルプセンター)
攻撃的なコンテンツの共有、特定の人物を標的とした嫌がらせへの関与、他者への嫌がらせの扇動などを禁止しているわけですが、実際に誹謗中傷などの投稿を根絶できているかというと、難しい現実があるといえるでしょう。
誹謗中傷による被害事例
根拠のない悪口やデマなどを言いふらして、他者を傷つけたり、個人や企業の社会的評価を低下させることを誹謗中傷といいます。
気軽に短文で投稿(ポスト、旧ツイート)できるXでは、リポスト(他人のポストをフォロワーなどに再ポストすること)機能があることから簡単に誹謗中傷投稿が拡散され、被害が拡大しやすい傾向があります。
ここでは、誹謗中傷があった場合に被害者が受ける被害のケースについて見ていきます。
プライバシーの侵害
誹謗中傷とともに、本人の同意なく住所、電話番号、顔写真などの個人情報が無断でネット上に公開されることで、ストーカー被害、家族への嫌がらせ、引っ越しを余儀なくされるなど、現実世界での危険が生じます。
- 被害者の自宅住所が投稿され、
「ここに嫌がらせをしよう」と
呼びかけられる。 - 顔写真や無断で加工した侮辱的画像が
投稿され、拡散される。 - 子どもの学校名や家族構成などまで
晒され、家庭にも影響がおよぶ。
精神的被害
誹謗中傷は、被害者の自尊心や心の安定を著しく損ないます。
匿名の攻撃であっても、繰り返されることで深刻な精神的苦痛を引き起こします。
うつ症状、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などの発症のほか、最悪の場合は自殺に至るケースも報告されています。
- 「〇〇は社会のゴミ」「死ね」などの
暴言が連日投稿され、
被害者が不眠や食欲不振などに陥る。 - 容姿や性格を侮辱する投稿が拡散され、外出や人と会うことが怖くなる。
- 学校や職場で
「ネットで叩かれている人」として
噂され、孤立する。
社会的信用の毀損
事実か否かにかかわらず、社会的評価を下げる投稿がされ、その後に拡散されることで、個人も会社も信用や信頼が失われます。
- 「〇〇は過去に万引きで逮捕された」「〇〇は不倫している」などの投稿が
拡散され、職場での立場が危うくなり、
家庭崩壊の危機に陥る。 - 「〇〇株式会社はブラック企業」
「〇〇社は社内のパワハラ、セクハラで
社員が自殺した」などの投稿が
拡散され、取引先や顧客が離脱、
企業ブランドが毀損される。
経済的損害
誹謗中傷によって業務が妨害され、個人の収入や会社の売上に直接的な影響がおよび、実損が発生する可能性があります。
- 飲食店に対して、「腐った食材を
使っている」、「虫が入っていた」、
「店員が暴力的」などと虚偽の口コミが
投稿され、客足が激減。 - 会社に対する誹謗中傷が投稿され、
営業妨害により売上げが減収、
赤字に転落。 - フリーランスやインフルエンサーが
「詐欺師」「無能」などと投稿され、
仕事の依頼が途絶える。
人間関係の悪化
誹謗中傷の内容が周囲に知られることで、家庭や職場の人間関係や友人関係などの信頼感が損なわれ、社会的孤立や家庭不和につながるケースがあります。
- 家族にまで誹謗中傷がおよび、
二次被害を受ける。 - 職場で「問題社員」、
「要注意人物」などと扱われ、
業務から外され、評価を落とす。 - 友人から距離を置かれ、
交友関係が断たれる。
深刻化する誹謗中傷による被害
誹謗中傷の被害は、単なる言葉の暴力だけにとどまりません。
精神的苦痛や社会的信用の低下を招き、さらに経済的損害や人間関係の悪化など、被害は複合的に連鎖しているケースも多いといえます。
特に、Xのような拡散力の高いSNSでは、被害の範囲が短時間で日本全国・全世界に広がってしまいます。
また、「デジタルタトゥー」と呼ばれるように、インターネット上に投稿されたコメントや画像などは、たとえそれが事実無根の情報でも、一度拡散してしまうと半永久的に残ってしまい、完全に削除するのは難しいという現実もあります。
このように、被害者の生活や企業活動の全体に深刻な影響をおよぼす可能性があることは見逃してはいけない事実です。
誹謗中傷投稿への初期対応から
具体的な対処法について
誹謗中傷投稿への対応が遅れてしまうことは非常に大きなリスクとなるため、次の4つの重要ポイントを中心に確認していきます。
- X(旧Twitter)社に、投稿(ポスト)
された誹謗中傷の削除依頼をする。 - X社に発信者情報開示請求を行ない、
IPアドレスを取得。 - IPアドレスからアクセスプロバイダ
(インターネット接続事業者)を
特定し、発信者情報開示請求を行なう。 - 発信者が特定できたら、警察への通報や刑事告訴、民事での損害賠償請求などを検討する。
まずはX社への対応から見ていきましょう。
最優先!投稿内容の記録・保存
自分自身や会社への誹謗中傷投稿を確認した場合は、すぐに投稿内容について事実調査・確認を行ないます。
そのうえで、今後の法的責任追及のために、投稿内容などを証拠として記録・保存しておきます。
スクリーンショットで保存、紙にプリントアウトするなどして保存しておくのがいいでしょう。
- 投稿日時
- 投稿者のアカウント名
- 投稿のURL
- 投稿内容
- 投稿者のアカウント情報(トップページ、URL、前後の投稿、リプライなど)
※アカウント = X上で自分の情報を入力して作ったページのこと。自分がユーザーになってメッセージを投稿(ポスト)したり、他のユーザーと交流したりするための基盤になる。
削除依頼
早急に、X社に通報して、該当の投稿の削除依頼をします。
主には次の方法があります。
Xの「報告」機能を使う
問題となる投稿から直接報告する場合は、次の手順で行ないます。
- 1. 投稿の上部端の「三点リーダー」を押す。
- 2. [ツイートを報告]を選択。
- 3. ツイートの問題点を報告。
Xの「ヘルプページ」を経由
「違反の報告」(Xヘルプセンター)のページの該当する項目から報告して、削除を求めます。
【参考資料】:「違反の報告」(Xヘルプセンター)
投稿の削除に応じない場合の
法的な対応
投稿削除の仮処分申請
X社への削除依頼では金額は発生しないため、被害者にとってはメリットといえます。
しかし、投稿の削除に応じないケースがあることに注意が必要です。
その場合は、法的に「投稿削除の仮処分申請」を行なうことも可能です。
裁判所に暫定的な措置を求めることを仮処分といい、申請が認められた場合、裁判所はサイト管理者や運営会社に対して削除命令を発令します。
送信防止措置依頼書の送付
まず、X社に対して「送信防止措置依頼書」を送付するという方法もあります。
名誉毀損などの被害を受けた場合は、被害者がプロバイダやサイト運営者に対して誹謗中傷投稿の削除(送信防止措置)を求める権利が求められているからです。
いずれにしても、法的に適切に対処するには、まずに弁護士に相談してみることをおすすめします。
削除依頼の際に注意するべき
ポイント
証拠の記録・保存
Xの場合、違反報告は誹謗中傷の被害者だけでなく、その投稿を見た第三者からもできます。
すると、X社の判断で誹謗中傷をしたアカウントを凍結する場合があるため、その後は投稿を見ることができなくなってしまう可能性があります。
被害者は早急に証拠を記録・保存しておくことが大切です。
アカウントの削除と凍結依頼
証拠を記録・保存したうえで、投稿の削除依頼をする際は、アカウントの削除や凍結の依頼も検討しましょう。
アカウントが凍結されれば、誹謗中傷投稿が繰り返されることを防ぐことができます。
なお、アカウントの凍結と削除の違いを理解しておくといいでしょう。
凍結というのは一時的なアカウントの利用停止で、審査や解除申請によって復旧し、元に戻る可能性があります。
削除はアカウント情報や投稿データが完全に消去される状態となるため、復元はできません。
IPアドレスのログ情報の消去
後ほど詳しく解説しますが、誹謗中傷投稿の被害にあった場合は、できるだけ迅速にX社に対して加害者のIPアドレスの開示を請求し、同時にIPアドレスのログ情報の消去禁止も求める必要があります。
なぜなら、IPアドレスのログ情報が消去されてしまってからでは、加害者の身元を特定することは非常に困難になってしまうからです。
通常、サイト管理者はIPアドレスのログ情報(利用履歴を記録したデータ)を3~6か月間は保存しているようです。
投稿の削除依頼と
投稿者の情報開示請求は別もの
削除依頼は投稿内容の削除を求めるだけのもので、投稿者の情報開示は請求できないことに注意が必要です。
刑事・民事の両方で法的措置を検討しているなら、情報開示請求をして加害者の身元を把握しておくことが必要です。
加害者を特定する/
発信者情報開示請求とは?
発信者情報開示請求について
誹謗中傷投稿が削除されただけでは、また誹謗中傷投稿を繰り返される可能性があるので、根本的な解決にはなりません。
さらに、加害者(発信者)が匿名の、どこの誰なのかわからない状況では、刑事告訴や損害賠償請求といった法的措置をとることができません。
そこで重要になるのが、加害者の身元を特定するためにIPアドレスの開示を求めて「発信者情報開示請求」を行なうことです。
IPアドレス(Internet Protocol Address)は、インターネットに接続しているデバイス(パソコン、スマートフォン、タブレットなど)に割り当てられる、インターネット上での住所を示すものといえます。
【参考資料】:発信者情報開示命令申立て(裁判所)
発信者情報開示請求での注意点
発信者情報開示請求では次の点に注意する必要があります。
権利侵害の明白性
「権利が侵害されたことが明らかであること」が問題とされ、「権利侵害の事実」と「違法性阻却事由の存在をうかがわせるような事情が存在しないこと」の2点がポイントになります。
法的に、「違法性阻却事由」というのは、通常であれば違法である行為が違法にならないような特別の事情のことです。
発信者情報開示請求では、特別な事情が存在しないことを、請求者側が主張立証することが求められます。
これは、情報を開示される側(発信者側)のプライバシーや表現の自由が考慮されるためです。
正当な理由の存在
開示請求者に発信者情報の取得が認められるためには、「開示請求者が次のような法的手段をとるにあたり」、「正当な利益として」、「発信者本人を特定する必要性がある」ことが求められます。
- 発信者に対する削除要請のため
- 民事上の損害賠償請求権の行使のため
- 謝罪広告などの名誉回復の要請のため
- 差止請求権の行使のため
- 刑事告発のため など
具体的な発信者情報の内容
総務省令により、次の項目が発信者情報として定められています。
- 氏名
- 住所
- メールアドレス
- 発信者のIPアドレス/IPアドレスと
組み合わされたポート番号 - 携帯端末のインターネット接続サービス利用者識別番号
- SIMカード識別番号
- 発信時間(タイムスタンプ)
発信者情報開示請求の盲点
X(旧Twitter)社(コンテンツプロバイダ)への発信者情報開示請求では、特定できる情報とできない情報があることに注意が必要です。
たとえば、通信が行なわれた国(都道府県)やIPアドレスの保有者はわかりますが、保有者の実際の氏名・住所・その他の個人情報はわかりません。
そこで、もう一段階、アクセスプロバイダに対して、該当するIPアドレスを利用していた者の個人情報の開示を請求する必要があります。
発信者情報開示請求の手続きについて
任意開示手続き
発信者情報開示請求は、「任意開示」と呼ばれる手続きにより裁判を起こさなくても行なうことが可能です。
任意開示を求める方法としては、弁護士会照会(弁護士法23条の2に基づく照会)などの方法があります。
ただし、アクセスプロバイダが応じることは多くないのが現実です。
裁判による請求手続き
上記の通り、任意開示に応じるアクセスプロバイダは多くないため、裁判による請求手続を行なうのが一般的なのですが、ここでまず覚えておいていただきたいのが「情報流通プラットフォーム対処法」です。
この法律では、プロバイダ等の損害賠償責任の制限、発信者情報の開示請求、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続などについて定めています。
以前は「プロバイダ責任制限法」であったものが、2024(令和6)年の法改正で名称が「情報流通プラットフォーム対処法」に変更され、2025(令和7)年4月1日から施行されています。
「プロバイダ責任制限法」ではコンテンツプロバイダとアクセスプロバイダそれぞれに対して、別々の手続きをとる必要があり、さらに被害者が加害者に損害賠償請求する裁判手続も含めると、計3回の裁判手続が必要でした。
しかし現在では、「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」によって、発信者情報の開示請求を1つの手続で行なうことが可能になっています。
なお、海外の事業者への発信者情報開示請求についても訴状の送達などにかかっていた時間が短縮され、手続きが簡易になっています。
【参考資料】:インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)(総務省)
裁判となると、やはり専門家のサポートが必要になるので、発信者情報開示請求をする場合は、SNSの問題に強い弁護士に相談・依頼をすることをおすすめします。
刑事事件で誹謗中傷に適用される
罪名と罰則を解説
刑事告訴で加害者の刑事責任を問う
加害者が特定できた場合、被害者は、捜査機関(警察や検察など)に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めるため告訴(刑事告訴)することができます。
X(旧Twitter)への誹謗中傷投稿は刑法上の犯罪に該当する可能性があり、適用される罪名と罰則には次のようなものがあります。
名誉毀損罪
不特定多数の人が閲覧することができる投稿で、その事実の有無にかかわらず、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者に科される罪です。
または50万円以下の罰金(刑法第230条)
※拘禁刑(第12条) = 身体の自由を制限される自由刑の1つで、従来の懲役刑と禁錮刑を統合する形で創設された新しい刑罰。
2022(令和4)年6月17日に公布された「改正刑法」で新たに定められた。
侮辱罪
名誉毀損罪とは違い、事実ではなくても投稿の内容が侮辱にあたる場合は侮辱罪が成立する可能性があります。
たとえば、「〇〇はバカだ」といったような具体的な事実を示さない誹謗中傷には侮辱罪が成立する可能性があるわけです。
もしくは30万円以下の罰金、
または拘留、もしくは科料
(刑法第231条)
脅迫罪
生命、身体、自由、名誉、または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者に科される罪です。
脅迫罪は、名誉毀損罪とは違い公然性を求められません。
または30万円以下の罰金(刑法第222条)
信用棄損罪・業務妨害罪
うその情報を投稿して企業や店舗などの業務を妨害した場合は、信用棄損罪や業務妨害罪が成立する可能性があります。
または50万円以下の罰金(刑法第233条)
【参考資料】:インターネット上の誹謗中傷等への対応(警察庁)
名誉毀損罪が認められる
条件は?
次の条件を満たす場合、Xへの誹謗中傷投稿が名誉毀損として認められる可能性があります。
公然性
不特定または多数の人に閲覧され、認識される状態であることが必要です。
なお、被害者個人に送られた誹謗中傷投稿は、不特定多数の人には見られないため公然性は満たさない、ということになります。
事実摘示性
名誉毀損罪における「事実の摘示」とは、人の社会的評価を害するに足りる事実を具体的に指摘することをいいます。
Xの投稿内容が真実かどうかではなく、その摘示された事実の真偽を確認できるかどうかがポイントになります。
具体的には、「〇〇は会社の経費を横領している」、「〇〇は会社の営業秘密を他社に売った」といった投稿内容は、真実かどうかわからないが、事実を摘示していると判断されます。
一方、「〇〇はバカだ」といった投稿は、真実かどうかはともかく、事実かどうかを確認する証拠がないため、事実摘示が認められないと判断されます。
名誉毀損性
Xの投稿内容が、人の社会的評価を低下させるものであることが必要です。
「〇〇は〇〇をした犯罪者」など、社会通念上その人の名誉を傷つけ、評価を低下させるような内容は名誉毀損性があると判断されます。
相手の特定
名誉毀損罪が成立するには、氏名や住所などの発信者情報から投稿者の身元が特定できていることも必要です。
時効が成立していない
一定の時間が経過してしまい、効力や権利がなくなってしまうことを「消滅時効」といいます。
時効が成立していなければ名誉毀損罪に問うことができます。
「告訴時効」
犯人を知った時から6か月(刑事訴訟法第235条)
※名誉毀損罪は親告罪のため刑事告訴をする必要があるため。
「公訴時効」
3年(刑事訴訟法第250条2項6号)
※犯罪が発生してから一定期間が経過すると、検察官がその犯罪について起訴する権限が消滅してしまうため。
損害賠償請求の流れと注意ポイント
損害賠償請求の流れ
X(旧Twitter)での誹謗中傷投稿で名誉を棄損された場合は、民事上の責任を問うために「損害賠償請求」をすることができます。
基本的な流れは、次のようになっています。
⇓
②交渉を開始
⇓
③交渉が決裂した場合は損害賠償請求訴訟を提起
⇓
④裁判所の判決
加害者側が交渉に応じない、直接交渉をしたくないといった事情がある場合も含めて、損害賠償請求は弁護士に相談・依頼するのがいいでしょう。
損害賠償請求でも時効に注意
民事において、損害賠償請求ができる期間(時効期間)は次のようになっています。
- 名誉毀損の相手を知ったときから「3年」
- 名誉毀損の事実から「20年」
実際的には、発信者情報開示請求をして投稿者を特定できた時から3年、名誉毀損の投稿がされた時から20年で時効が成立すると考えておくといいでしょう。
誹謗中傷投稿でお困りの場合は
弁護士に相談してください!
X(旧Twitter)の誹謗中傷投稿への対応については、ここまでお話してきたように複雑で時間がかかることを理解していただきたいと思います。
また、適切な対応をすることは時間との闘いでもあるため、できるだけ早急に弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。
4つのメリット>
- 発信者の特定手続きを依頼できる。
- 刑事告訴や損害賠償請求を任せられる。
- 自分で進めていくより、問題を早期に
解決できる。 - X社とのやりとり、加害者との交渉での
精神的な負担・ストレスを
大幅に軽減できる。
弁護士法人みらい総合法律事務所は全国対応で、随時、無料相談を行なっています(事案によりますので、お問い合わせください)。
さらに、いつでも相談・依頼できる顧問弁護士についてのご相談もお受けしています。
誹謗中傷投稿をされた時は一人で悩まず、まずは一度、気軽にご相談ください(秘密厳守)。