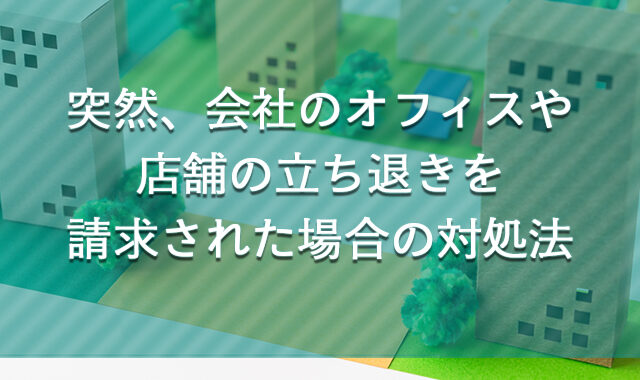賃料増額請求をされた場合の対処法(テナント側)
テナント側(賃借人)のもとに、ある日突然、貸主(賃貸人)や管理会社から「賃料を上げたい」との通知が届くことがあります。
物価上昇や経済状況の変化など、賃貸人側にも事情があるでしょうが、テナント側にとって賃料増額は生活や事業に直結する重大な問題です。
では、こうした場合、どのように対処すればいいのでしょうか?
賃料の値上げを拒否することはできるのでしょうか?
賃料は、当事者間の合意によって自由に増額できるのが原則です。
ということは、合意がなければ勝手に賃料増額はできないということになります。
つまり結論からいうと、原則としてですが、テナント側は賃貸人や管理会社がいうとおりに賃料増額に応じる必要はないのです。
根拠となる法律は「借地借家法」です(後ほど詳しく解説します)。
大きな流れ、ポイントは次のようになります。
1. 増額の理由を確認する
賃貸人や管理会社は、一方的に賃料増額を決定できるものではないので、確認する必要があります。
たとえば、経済状況の変化や固定資産税の増加、近隣相場との乖離などにより賃料額が不相当な金額になったと認められなければいけません。
テナント側としてはまず、これらの理由を確認する必要があります。
2. 契約内容を確認する
賃貸借契約書に「賃料不増額特約」などがある場合、増額請求が制限されている可能性があるので契約書をよく確認しましょう。
3. 増額請求に応じる義務はない
賃貸人などからの通知や口頭での請求だけでは、賃料は自動的に上がりません。
テナント側が合意するか、裁判所により認められない限り、賃料は現行のままです。
合意に至らない場合、賃貸人は調停や訴訟を提起することができるので、テナント側も対応する必要があります。
4. 調停・訴訟のプロセスや
ポイントも知っておく
話し合いで解決しない、交渉が決裂したといった場合、簡易裁判所に調停を申し立てることになります。
それでも解決しない場合は訴訟に進みます。
訴訟中は、テナント側が「相当と考える賃料」を支払っていれば、債務不履行にはなりません。
5. 弁護士に相談する
法的な根拠や交渉の進め方に不安がある場合は、早めに弁護士に相談するのが安心です。
特に訴訟に発展した場合は、専門家のサポートが必須といえます。
本記事では、賃料増額請求をされた場合の対処法について、テナント側の立場から法的根拠と実務をまじえて解説します。
ぜひ最後までお読みになって、正しい知識を身につけてください。
目次
賃料増額請求の法的根拠とは?
賃料の増減については、「借地借家法」に明確な規定があります。
1.建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
条文を要約すると、賃貸人は次のような事情がある場合に限り、賃料の増額を請求できるということになります。
- ・固定資産税などの租税の増加
- ・建物の維持費、修繕費の増加
- ・土地・建物の価格上昇
- ・物価の上昇(インフレなど)
- ・周辺相場との乖離
- ・一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約(不増額特約)がない場合 など
ただし、これらの事情があっても賃貸人が一方的に賃料を上げることはできません。
原則として、テナント側(賃借人)の合意が必要になるのです。
そこでテナント側としては、まず家賃増額請求の根拠が明らかだと証明できる説明や資料の提出を求める必要があります。
テナント(借主)は賃料増額請求を拒否できるか?
賃料増額請求を拒否できる
ケースとは?
前述したように、テナント側(賃借人)は原則として賃料増額請求を拒否することができます。
テナント側が合意しない限り、賃料は現行のまま据え置かれるわけです。
では、拒否が認められるのはどういう場合かというと、主に次のようなケースがあります。
- ・増額の理由が不明確、または合理性に欠ける
- ・周辺相場と比較して、現行賃料が妥当
- ・契約書に「不増額特約」がある(一定期間賃料を上げない旨の特約)
- ・建物や設備の老朽化など、むしろ減額が妥当な場合 など
拒否する際の注意点と対応手順
ステップ①:請求内容と根拠を確認する
まずは、賃貸人からの通知書や説明資料で、前述の増額要件などを確認します。
ステップ②:安易に合意しない
「値上げは仕方ないか……」とすぐに応じるのではなく、まずは冷静に検討しましょう。
一度、合意してしまうと、後から交渉することは困難になります。
ステップ③:書面で拒否の
意思を伝える
拒否する場合は口頭ではなく、書面(内容証明郵便が望ましい)で明確に意思表示を行ないます。
次のような文面が一般的です。
「貴殿より通知のあった賃料増額請求について、当方としては現行賃料が妥当であると考えており、現時点では応じかねます。」
ステップ④:現行賃料を
供託する(必要に応じて)
賃貸人が増額後の賃料しか受け取らないとして受取を拒否した場合は、法務局に「供託」することで支払い義務を果たしたことになります。
これにより、滞納扱いを回避できます。
※供託:金銭、有価証券などを国家機関である供託所に提出して、その管理を委ね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度。
なお、供託金は裁判所の判断が出るまで供託所に保管されます。
最終的に勝訴すれば、借主に返還されるか、貸主に引き渡されます。
【参考資料】:供託(法務局)
賃料増額に応じなくても
契約更新できるか?
賃料増額に同意せずに契約更新が認められる要件とは?
一般的に、テナント賃料の値上げが通知されるタイミングは賃貸契約の更新時だと思います。
そのため、賃料増額に応じなければ契約更新ができないと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはないことが「借地借家法」で規定されています。
賃貸人からの通知が必要
建物の賃貸借(期間の定めがある場合)については、賃貸人が契約期間の満了の1年前から6か月前までの間にテナント側(賃借人)に対して、①更新をしない旨の通知、または②条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、これまでの契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(第26条1項)。
これを「法定更新」といい、更新後は契約期間の定めはないものとされます。
正当事由がなければ
解約は認められない
また、賃貸人側の更新拒絶に「正当事由」がなければ、更新について合意が成立しなくても(更新後の賃貸借契約書を取り交わさなくても)、法律上当然に賃貸借契約が同一条件で更新されるものとしています(第28条)。
つまり、これらの条件を満たさなければ、賃貸人は解約の申入れができないわけです。
立退料の提示の有無もポイント
なお、正当事由があるといえるには、賃貸人側が建物の使用を必要としていることを前提として、ほとんどのケースで立退料の提示・提供をする必要がある場合がほとんどです。
そのため、賃貸人が立退料の提供もせずに、ただ単に更新時に賃料の増額を求めてきたとしても、テナント側が増額に応じずに賃貸借契約書も取り交わさなければ、法律上はこれまでの賃料額で賃貸借契約は更新されるのです。
また賃貸人は、テナント側が賃料増額を拒否したことを理由に契約解除や退去を求めることはできません。
賃料増額請求訴訟の
判決確定前後の賃料支払いに
ついて
判決の確定前
賃料増額請求について、賃貸人が裁判を起こした場合、賃料の増額を正当とする判決が確定するまでは、テナント側は相当と認める額の賃料額(通常は従前の賃料額)を支払えば足りるとされます(借地借家法32条2項)。
判決の確定後
賃料増額を正当とする裁判が確定した場合、増額請求の意思表示がなされてから支払った賃料の合計額が、増額後の賃料の合計額(増額請求があった時点から増額の効果が生じることに注意)に対して不足する部分があるなら、年10%の利息をつけて賃貸人に支払う義務が生じます(借地借家法32条2項ただし書)。
調停・訴訟に発展した場合の流れ
テナント側(賃借人)が賃料増額を拒否した場合、賃貸人が調停や訴訟を提起してくる可能性があります。
その場合は次のような流れになります。
調停(簡易裁判所)
賃貸人が「賃料増額調停」を申し立てると、簡易裁判所が間に入って話し合いを行ないます。
調停は、裁判官のほか調停委員を加えた調停委員会によって、民事上の紛争を話し合いで解決しようとするものです。
ここでは賃料増額請求の要件を満たしているのかの確認、要件を満たすならどの程度の増額が相当かの協議となります。
ここで合意に至れば、調停調書に基づいて新賃料が決定されます。
訴訟
調停が不成立の場合、賃貸人は訴訟を提起することができます。
裁判所は次の要素などから総合的に判断することになります。
- ・周辺相場
- ・建物の築年数や設備等
- ・契約内容
- ・経済事情の変動 など
訴訟では、当事者の合意による直近の賃料額が、その後の事情の変更により不相当になっているかどうかが争点になります。
そのため、現時点で建物賃貸借契約を結ぶ場合、賃料はいくらが相当かということではなく、現在の賃料が合意された時点からの経済情勢の変化、地価や賃料相場の上昇などに応じた増額が認められることになります。
たとえば、仮に賃貸人が20万円の賃料が現在の相場だと主張しても、もともとの家賃が10万円であれば、その賃料からいくら増額するのが妥当かが判断されるわけです。
通常、 訴状や答弁書、 準備書面による応答を数回行なった後、 当事者の申し出により賃料の鑑定がなされ、その鑑定結果に基づいて裁判上の和解や判決がなされることになります。
訴訟で注意するべきポイント
判決が出るまでには数か月~1年以上かかることもあるので、ご自身の状況を考え合わせながら対応する必要があります。
なお、裁判で賃料増額が認められた場合、訴訟を起こした側(賃貸人)は裁判所が行う鑑定の費用の全部または一部を相手方(テナント側)に負担させることができることに注意が必要です。
テナント側(賃借人)が
注意するべきポイントまとめ
テナント側としては、次のポイントに注意しながら交渉などを進めていく必要があります。
感情的にならず
冷静に進めていく
賃料増額は貸主にとっても経営上の判断です。
感情的な対応は避け、冷静に事実と法的根拠に基づいて対応しましょう。
家賃の支払いは継続する
賃料増額を拒否しても、現行賃料の支払いは継続する必要があります。
支払いを止めると、滞納扱いとなり、契約解除や明渡請求のリスクが生じます。
証拠を残しておく
交渉などのやり取りは、できる限り書面で行ない、メールや通知書などの記録を保管しておきましょう。
後に調停や訴訟になった際の重要な証拠となります。
専門家に相談する
不安がある場合は、不動産や契約に強い弁護士に相談するのが安心です。
交渉の代理や供託手続きのサポートなども受けることができます。
賃料増額請求を受けたら
弁護士にご相談ください!
賃料増額請求は、賃貸人の一方的な通告では成立せず、テナント側(賃借人)の合意が必要です。
納得できない場合は拒否することができます。
ただし、ここまで解説したように、書面での意思表示や供託など、法的に適切な手続きを踏むことが必要です。
不安があるなら早めに弁護士に相談・依頼し、戦略的に対応していくことをおすすめします。
そもそも、賃貸契約は双方の信頼関係に基づくものです。
法律の専門家である弁護士なら正しい対応ができ、円満な解決を実現することができます。
弁護士法人みらい総合法律事務所は全国対応で、随時、無料相談を行なっています(事案によりますので、お問い合わせください)。
まずは一度、気軽にご連絡ください。








タイトル.jpg)