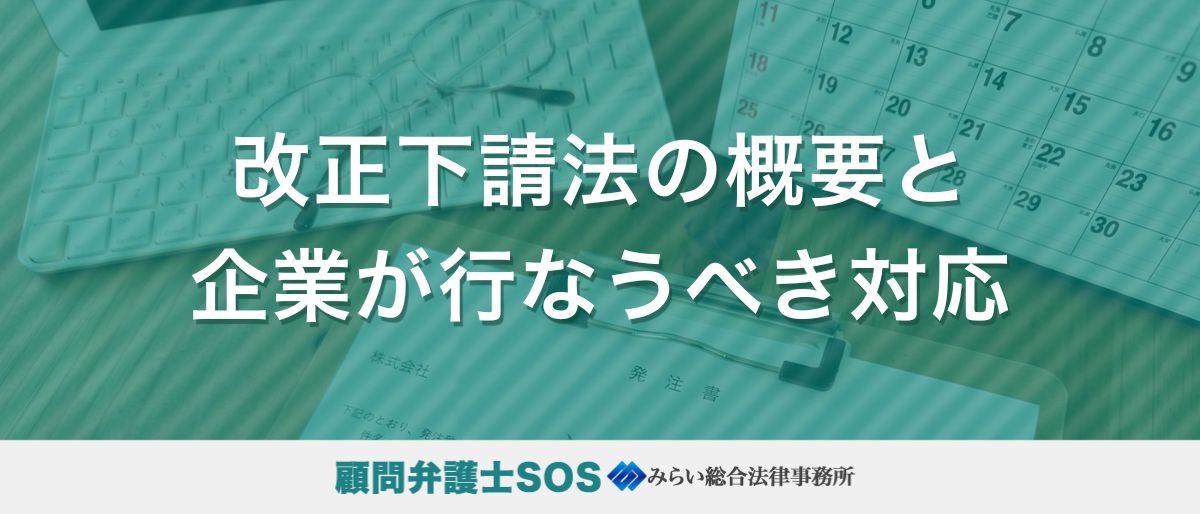改正下請法の概要と企業が行なうべき対応
「改正下請法」が2025(令和7)年5月23日に公布され、2026(令和8)年1月1日に施行されます。
近年の急激な物価上昇や人件費・原材料費・エネルギーコストの高騰などにより、企業間取引における価格転嫁が進まず、特に中小企業や物流事業者が厳しい経営環境に置かれています。
こうした状況を受けて、政府が抜本的な改正に踏み切ったという背景があります。
そもそも「下請法」は、1956(昭和31)年に公布・施行された法律で、その主な目的は「下請取引の公正化」と「下請事業者の利益を保護すること」です。
下請法では、強い立場にある親事業者(発注元)が、弱い立場にある下請事業者(委託先)に対して、「下請代金の減額」、「支払遅延」、「買いたたき」などの行為をしないよう規制をしています。
今回の下請法の改正では、「下請などの用語の見直し」、「従業員基準の追加」、「価格据置取引への対応」、「手形払等の禁止」、「運送委託の対象取引への追加」、「面的執行の強化」などが規定される予定です。
同時に、法律名も変更されます。
正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」となります。
略称・通称として、「中小受託法」、「中小受託取引適正化法」、「取適法」などが想定されていますが、本記事では「改正下請法」と表記していきます。
そこで本記事では、主に次の項目などについて解説していきます。
- ・下請法を改正する意図
- ・下請法が改正されて変わること
- ・改正内容の概要
- ・改正下請法で注意するべきポイント
など
重要な改正となるため、事業者(企業)の経営陣の方などは本記事を読んで、理解を深めていただきたいと思います。
※本記事は、2025年7月現在の情報をもとに作成しています。
目次
下請法の基本データを再確認
下請法とは?
1956(昭和31)年に公布・施行された法律で、正式名称を「下請代金支払遅延等防止法」といいます。
通称「下請法」と呼ばれており、「下請事業者の利益を保護」し、「下請取引の公正化を図る」ことを目的としています。
【参考資料】:ポイント解説 下請法(公正取引委員会)
【参考資料】:知って守って下請法(中小企業庁)
親事業者(現:委託事業者)の義務と禁止行為
下請法には、下請取引を行なううえでの親事業者の義務や禁止行為などが定められています。
親事業主の4つの義務
- ・下請代金の支払期日を定める義務
親事業者は、下請代金の支払期日を定める義務があり、発注した物品等の受領日から60日以内の、できるだけ短い期間内が支払期日となります。 - ・書面の交付義務
口頭発注によるトラブルを未然に防止するため、親事業者は発注の際には法律で定められた書面(三条書面)を交付する必要があります。 - ・遅延利息の支払い義務
親事業者が支払期日までに下請代金を支払わなかった場合、下請事業者(現:受託事業者)に対して年率14.6%の遅延利息を支払う義務が発生します。
これは、受領した日から起算して60日を経過した日から実際に支払いが行われる日までの期間の日数に応じた金額になります。 - ・書類の作成・保存義務
親事業者は、取引に関する記録(下請事業者から受領した給付(物品等)の内容、下請代金の額など)を書類または電磁的記録(データ)として作成し、2年間保存する必要があります。
親事業者の禁止行為
次の11の項目が禁止されています。
| 禁止事項 | 概要 |
|---|---|
| 受領拒否 (第4条1項1号) |
注文した物品などの受領を拒むこと。 |
| 下請代金の支払遅延 (第5条1項2号) |
下請代金を受領後 60日以内に定められた支払期日までに支払わないこと。 |
| 下請代金の減額 (第4条1項3号) |
あらかじめ定めた 下請代金をあとから減額すること。 |
| 返品 (第4条1項4号) |
受け取った物を 返品すること。 |
| 買いたたき (第4条1項5号) |
下請代金を 類似品などの 価格や市価に 比べて、 不当に著しく 低く定めること。 |
| 購入・利用強制 (第4条1項6号) |
親事業者が指定する物や役務を強制的に購入、利用させること。 |
| 報復措置 (第4条1項7号) |
親事業者の 不公正な行為を 下請事業者が公正取引委員会または中小企業庁に 知らせたことを 理由として、 下請事業者に対して取引数量の削減や 取引停止などの 不利益な取扱いをすること。 |
| 有償支給原材料等の対価の早期決済 (第4条2項1号) |
有償で支給した 原材料などの 対価を、 その原材料などを 用いて製造された 物品の下請代金の 支払期日より 早い時期に 相殺したり、 支払わせたり すること。 |
| 割引困難な手形の 交付 (第4条2項2号) |
一般の金融機関で 割引を受けることが 困難だと認められる 手形を交付する こと。 |
| 不当な経済上の 利益の提供要請 (第4条2項3号) |
下請事業者から 金銭や労務の 提供などを させること。 |
| 不当な給付内容の 変更・ 不当なやり直し (第4条2項4号) |
注文内容の変更や 受領後のやり直し などを、 費用を負担せずに やらせること。 |
| 禁止事項 | 条文番号 | 概要 |
|---|---|---|
| 受領拒否 | (第4条1項1号) | 注文した物品などの受領を拒むこと。 |
| 下請代金の支払遅延 | (第4条1項2号) | 下請代金を受領後60日以内に定められた 支払期日までに支払わないこと。 |
| 下請代金の減額 | (第4条1項3号) | あらかじめ定めた下請代金をあとから 減額すること。 |
| 返品 | (第4条1項4号) | 受け取った物を返品すること。 |
| 買いたたき | (第4条1項5号) | 下請代金を類似品などの価格や市価に 比べて、不当に著しく低く定めること。 |
| 購入・利用強制 | (第4条1項6号) | 親事業者が指定する物や役務を強制的に 購入、利用させること。 |
| 報復措置 | (第4条1項7号) | 親事業者の不公正な行為を下請事業者が 公正取引委員会または中小企業庁に 知らせたことを理由として、 下請事業者に対して 取引数量の削減や取引停止などの 不利益な取扱いを すること。 |
| 有償支給原材料等の 対価の早期決済 |
(第4条2項1号) | 有償で支給した原材料などの対価を、 その原材料などを用いて製造された物品の下請代金の支払期日より早い時期に 相殺したり、支払わせたりすること。 |
| 割引困難な手形の交付 | (第4条2項2号) | 一般の金融機関で割引を受けることが 困難だと認められる手形を交付すること。 |
| 不当な経済上の利益の 提供要請 |
(第4条2項3号) | 下請事業者から金銭や労務の 提供などをさせること。 |
| 不当な給付内容の変更 ・不当なやり直し |
(第4条2項4号) | 注文内容の変更や受領後の やり直しなどを、 費用を負担せずにやらせること。 |
【参考資料】:親事業者の禁止行為(公正取引委員会)
下請法改正の理由と経緯
今回の下請法の改正には、次のような背景・意図があります。
賃上げの原資(財源)確保
近年の急激な物価上昇や人件費・原材料費・エネルギーコストの高騰により、事業者(企業)にとっては「物価上昇を上回る賃上げ」が大きな課題となっています。
従業員の賃上げを実現するためには、適正な価格交渉を通じて財源を確保できるよう、取引環境を整備する必要がありました。
価格転嫁の定着
(価格転嫁の困難さの是正)
賃上げの原資の確保のためには、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」 の実現を図っていくことが急務です。
しかし、特に中小企業や物流事業者などの下請事業者(受託事業者)は物価上昇やコストの高騰に対し、価格転嫁できずに負担を強いられる構造が問題視されてきたため、これを是正する必要がありました。
不公正な商慣習の是正
(取引の対等性の確保)
これまで、協議に応じない一方的な価格決定行為などは価格転嫁を阻害し、 下請事業者(受託事業者)に負担を押しつける商慣習となっていました。
そのため、手形払い、価格据え置き、荷待ち・荷役の無償対応など下請事業者に不利な慣行を排除する必要がありました。
物流問題への対応
また、運送委託取引を新たに規制対象とし、物流業界の取引適正化を図る必要もありました。
こうした状況を受けて、政府は従来の「下請的」な構造を見直して親事業者(委託事業者)と下請事業者(受託事業者)が対等な立場で交渉できる環境整備のために不適切な商慣習を一掃し、取引を適正化することを検討してきました。
そこで、取引を適正化して価格転嫁をさらに進めていくため、下請法の抜本的な改正に踏み切ったわけです。
【参考資料】:下請法・下請振興法改正法の概要(公正取引委員会
改正下請法で何が変わるのか?
─改正内容の概要について─
次に、今回の改正下請法の内容についてポイントを解説していきます。
法律名・用語の変更
これまで使用されてきた「下請」や「親事業者」といった用語は、委託事業者と受託事業者が対等な関係ではないという語感を与えるとの指摘がありました。
また、時代の変化にともない、委託事業者である大企業側でも「下請」という用語は使われなくなってきており、「サプライヤー」などの用語を用いているという状況もあることから、次のように法律名や用語の変更が行なわれます(改正法第2条8項・9項)。
<改正のポイント>
おもな用語等の変更点は次のとおりです。
こうした変更にともない、事業者としては旧法律名や用語が記載されている資料(各種社内規程やマニュアル類、帳票類等)や契約書などは修正していく必要があります。
価格協議義務の明確化
市価の認定が必要となる「買いたたき」とは別に(買いたたき禁止のルールはそのまま残したうえで)、対等な価格交渉を確保する観点から、中小受託事業者(下請事業者)から価格協議の求めがあったにもかかわらず協議に応じなかったり、委託事業者(親事業者)が必要な説明を行なわなかったりするなど、一方的に代金を決定して中小受託事業者の利益を不当に害する行為を禁止する規定を新設しました(改正法第5条2項4号)。
- ・委託事業者は価格協議に誠実に応じる義務を負います。
そのため、協議を適切に行なわない一方的な価格決定は禁止されます。 - ・価格協議の拒否については、公正取引委員会はこれまで以上に、勧告・社名公表・指導を行なっていく可能性があります。
手形払等の禁止
(支払の厳格化)
現行の下請法では、手形期間が60日(2か月)を超える長期手形での下請代金の支払は禁止されていましたが、手形を用いること自体は禁止されていませんでした。
そのため、支払手段として手形などを用いることで委託事業者が中小受託事業者に資金繰りに関係する負担を求める商慣習が続いてきたという問題がありました。
そこで、手形のほか、電子記録債権・ファクタリングなど現金化困難な支払手段は使用禁止となります(改正法第5条1項2号)。
現金受領までの期間が短縮されます。
- 「現行法」
製品や役務の受領日から支払日までの期間
(60日)+手形サイト(60日)
= 現金受領までの期間(120日) - 「改正法」
製品や役務の受領日から支払日までの期間
(60日)
= 現金受領までの期間(60日)
対象取引に特定運送委託を追加
立場の弱い物流事業者が、荷役や荷待ちを無償で行なわされているなど、荷主と物流事業者間の問題が顕在化している状況において、これまでは発荷主から元請運送事業者への委託は、本法の対象外(独占禁止法の物流特殊指定で対応)となっていました。
そこで、機動的に対応できるようにするため、発荷主が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引=特定運送委託が本法の対象となる新たな類型として追加されます(改正法第2条5項・6項)。
- ・現行の、運送事業者の元請から下請への再委託に加え、発荷主(メーカーや卸売事業者など)から運送事業者(元請)への委託(特定運送委託)も規制対象に追加されます。
- ・発荷主としての運送の委託については、これまでは「物流特殊指定」という規制があり、下請法と同様の行為(代金の支払遅延や減額、買いたたきなど)が禁止されていました。
それに加え、今回の改正では「発注書の交付や役務提供から60日以内の支払い」が求められるなど、別途の対応が必要となることに留意する必要があります。
従業員基準の追加導入
現行法では、委託事業者(親事業者)と中小受託事業者(下請事業者)の資本金額により、適用範囲を定めていました。
しかし、事業規模は大きいものの当初の資本金が少額である事業者や、減資をすることによって下請法の適用を免れようとしたり、下請事業者に増資を求めたりする事例が問題になっていました。
そこで改正下請法では、従来の資本金基準に加えて、さらに適用基準として従業員数の基準が新たに追加されます(改正法第2条8項・9項)。
- ・資本金基準に加え、従業員数(300人・100人)による適用判断が追加されます。
- 「300人基準」
・従業員300人超の法人事業者が、従業員300人以下の法人事業者などに委託する場合に適用される。 - 「100人基準」
- ・従業員100人超の法人事業者が、従業員100人以下の法人事業者等に委託する場合に適用される。
- ・これまでの資本金基準での「3億円基準」が適用されるケースと、新設される特定運送委託については「300人基準」が適用されます。
- ・これまでの資本金基準における「5,000万円基準」が適用されるケースについては「100人基準」が適用されます。
| 中小受託法の適用対象 | ||
|---|---|---|
| 取引の内容 | 委託事業者 | 中小受託事業者 |
| 製造委託 修理委託 特定運送 委託 |
資本金 1,000万円超 ~3億円 以下 |
資本金 1,000万円 以下 |
| 資本金 3億円超 |
資本金 3億円以下 |
|
| 従業員数 300名超 |
従業員数 300名以下 |
|
| 情報 成果物 作成委託 役務提供 委託 |
資本金 1,000万円超 ~5,000万円 以下 |
資本金 1,000万円 以下 |
| 資本金 5,000万円超 |
資本金 5,000万円 以下 |
|
| 従業員数 100名超 |
従業員数 100名以下 |
|
たとえば、資本金3億円超の企業が、資本金3億円超の企業に製造委託をする場合などは、現行法では資本金要件を満たさないため下請法の対象外とされました。
しかし、これまでは資本金要件を満たさず下請法の対象外とされる委託先でも、委託先企業の従業員数が300人または100人以下の場合は改正下請法の対象になります。
そのため、委託先企業が資本金要件を満たさないけれども、従業員数が300人または100人以下の可能性がありそうな場合、委託事業者(親事業者)としては改正下請法が施行される前に個別に従業員数を確認しておく必要があるでしょう。
現行法の資本金基準では、資本金1,000万円以下の発注企業は委託事業者(親事業者)に該当しないため、下請法への対応は不要とされていました。
しかし改正下請法のもとでは、従業員数が300人または100人を超えている場合は新たに委託事業者として下請法の遵守を求められることにも注意が必要です。
面的執行の強化
現行法では、事業所管省庁には中小企業庁の調査に協力するための調査権限が与えられているだけでした(下請法第9条3項)。
また、中小受託事業者(下請事業者)が委託事業者(親事業者)の下請法違反を事業所管省庁(トラック・物流Gメンなど)に通報した場合、「報復措置の禁止」の対象とされていませんでした(下請法第4条1項7号)。
そこで改正下請法では、中小受託事業者の保護を図るため、公正取引委員会や中小企業庁、事業所管省庁が相互に協力して面的な法執行を行なえるようにするための次の法改正が行なわれます。
法改正の内容は次のとおりです。
- ①事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与する(改正法第8条)。
- ②公正取引委員会や中小企業庁、事業所管省庁に対して、下請法の執行のため個別の事案に関する情報交換を行なう権限を付与する(改正法第13条1項・2項)。
- ③「報復措置の禁止」の申告先として、現行の公正取引委員会や中小企業庁長官に加え、事業所管省庁の主務大臣を追加する(改正法第5条1項7号)。
その他の改正事項
「金型以外の型等の製造委託」を追加(改正法第2条1項)
<現行法>
物品等の製造に用いられる金型のみが製造委託の対象物とされており、木型や治具などについては製造委託の対象物とされていない。
<改正法>
もっぱら製品の作成のために用いられる木型や治具などについても、金型と同様に製造委託の対象物として追加する。
必要的記載事項が電磁的方法により提供可能に(同法第4条)
<現行法>
書面交付義務については、下請事業者から事前の承諾を得たときに限り、書面の交付に代えて、電磁的方法により必要的記載事項の提供を行なうことができる。
<改正法>
書面等の交付義務については、中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず、必要的記載事項を電磁的方法により提供可能とする。
遅延利息の対象に減額を追加(改正法第6条2項)
<現行法>
下請代金の支払遅延については、「親事業者に対し、その下請代金を支払うよう勧告するとともに、遅延利息を支払うよう勧告すること」とされているが、減額については当該規定が存在 しない。
<改正法>
遅延利息の対象に減額を追加し、代金の額を減じた場合、起算日から60日を経過した日から実際に支払をする日までの期間について、遅延利息を支払わなければならないものとする。
既に違反行為が行なわれて
いない場合等の勧告に係る
規定の整備(同法第10条)
<現行法>
受領拒否などをした親事業者が勧告前に受領などをした場合や、支払遅延をした親事業者が勧告前に代金を支払った場合に、勧告ができるかどうかが規定上明確になっていない。
<改正法>
既に違反行為が行なわれていない場合などの勧告に関わる規定を整備し、勧告時点において委託事業者の行為が是正されていた場合でも、再発防止策などを勧告できるようにする。
【参考資料】:下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案新旧対照条文(公正取引委員会)
委託事業者と中小受託事業者が
注意するべきポイントまとめ
ここでは、委託事業者(親事業者)と中小受託事業者(下請事業者)それぞれが注意するべき、必要となるポイントについてまとめておきます。
委託事業者(親事業者)
の注意点
価格交渉体制の整備
受託事業者(下請事業者)からの価格交渉に対しては根拠資料を提示し、誠実に対応する体制を構築する必要がある。
支払条件の見直し
現金払いへの切り替え、支払期日の再設定などが必要。
契約書・取引書面の修正
用語変更や支払方法の制限に対応した文言修正の実行。
電子交付システムの導入
書面交付の電子化に対応するためのシステム整備が必要。
社内研修の実施
法改正の内容を関係部署に周知し、社内研修を実施するなどして違反リスクの低減に努める。
中小受託事業者(下請事業者)の注意点
価格交渉の準備
原価上昇の根拠資料(原材料費・人件費など)を整理・準備し、委託事業者との交渉に備える。
交渉履歴の保存
委託事業者との協議内容を記録し、万が一の法的トラブルに備える。
資金繰り計画の見直し
支払サイトが短縮されることでキャッシュフローの改善が見込めるため、資金繰り計画の見直しに着手する。
契約条件の確認
従業員数基準や運送委託の追加により、自社が新たに法律適用対象となる可能性を確認する。
電子交付への対応
取引書面の電子化に対応できる体制を社内で整備する。
<実務対応のチェックリスト>
- ☑️ 契約書の用語修正
- ☑️ 支払方法の現金化
- ☑️ 価格交渉体制の整備
- ☑️ 電子交付システムの導入
- ☑️ 社内研修の実施
- ☑️ 交渉履歴の保存
- ☑️ 対象取引の再確認
下請中小企業振興法
(下請振興法)の改正について
下請事業者の自立を支援し、振興を図るための環境整備を行なうことを目的とした法律に「下請中小企業振興法(下請振興法)」があります。
国は、親事業者と下請事業者が望ましい取引を行なうための指針として「振興基準」を定めています。
今回の下請法の改正では、同時にこの下請振興法も改正され、「受託中小企業振興法」と名称も変更されます。
詳しい内容については、こちらのサイトを参考にしてください。
【参考資料】:下請法・下請振興法改正法の概要(公正取引委員会)
改正下請法でリスクを負わないためには弁護士にご相談ください!
2026年1月1日施行の「改正下請法」は、単なる法令変更ではなく、企業間取引の構造そのものを見直す大改革です。
委託事業者(親事業者)と中小受託事業者(下請事業者)はともに、対等な関係のもとで適正な価格交渉と支払が行なわれることを前提とした新ルールに対応する必要があります。
企業の信用や取引継続に直結する法改正ですので、早期の準備と社内体制の整備が不可欠です。
改正下請法でリスクを負わないためにも、まずは一度、弁護士にご相談ください。
弁護士法人みらい総合法律事務所は全国対応で、随時、無料相談を行なっています(事案によりますので、お問い合わせください)ので、気軽にご連絡いただければと思います。