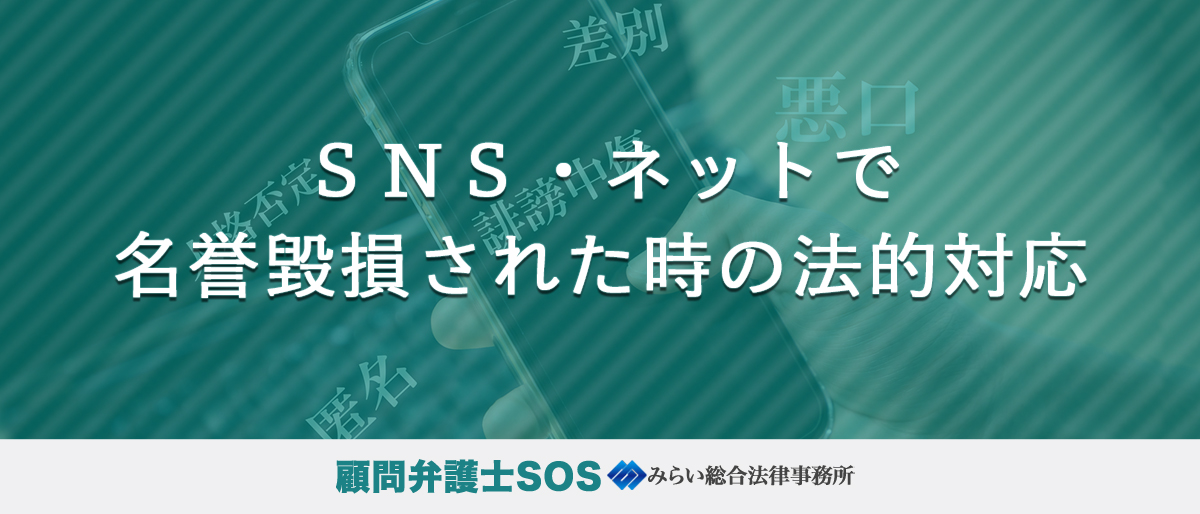SNS・ネットで名誉毀損された時の法的対応
現代ではインターネットの利用は日常のことになり、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)に投稿したりすることで、他の誰かとつながり、情報を共有している人も多いと思います。
しかし一方で、現実にはさまざまな問題が起きています。
その一つが、誹謗中傷投稿などによる名誉棄損の問題です。
本記事では、SNSや投稿サイトで、「根拠のない悪口やデマを書かれた」、「個人情報を無断でさらされた」といった被害にあった場合に、
- ・SNSへの書き込みを名誉毀損と判断できるのか?
- ・匿名の書き込みに対して、どう対応していけばいいのか?
- ・相手を特定し、法的措置をとるにはどうすればよいのか?
- ・損害賠償金の請求はできるのか?
といった疑問などについて、弁護士が法的な対応方法と解決策を解説していきます。
ぜひ正しい知識を知って、被害の拡大を防ぎ、名誉を回復していきましょう。
目次
名誉毀損とは?
名誉毀損と法律の関係
「名誉毀損」(一般的な使用では名誉棄損とも)とは、他人の名誉を傷つけることで、民事では不法行為による損害賠償の対象となり、刑事事件としては刑事罰の対象にもなる行為です。
「刑法」
第230条(名誉毀損)
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
「民法」
第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第723条(名誉毀損における原状回復)
他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
名誉毀損は、人(個人)に対してだけでなく、法人(会社)にも適用されます。
企業や組織に対する名誉毀損は「信用毀損罪・業務妨害罪」に該当する場合もあります。
「刑法」
第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
たとえば、「〇〇社はブラック企業だ」とSNSに投稿された場合、この会社の社会的評価を低下させたと判断されれば、信用毀損罪・業務妨害罪が成立します。
しばしば、名誉棄損罪と似たものとして「侮辱罪」があげられますが、こちらは「事実を指摘しなくても、公然と人を侮辱する」こと、と規定されています(刑法第231条)。
つまり両者の違いは、事実を指摘するかどうかの違い、ということになります。
たとえば、インターネット上のSNSや掲示板などに「〇〇はバカ」と書き込みをした場合、それは主観的な評価であって、事実を指摘しているわけではないので侮辱罪が適用されます。
一方、「〇〇は詐欺をした」などと書き込んだ場合は事実を指摘しているので、名誉毀損罪が適用されます。
名誉毀損罪での名誉とは法的には外部的名誉のことで、ある人に対して社会が与えている評判や世評などの評価をいいます。
そのため、他者から誹謗中傷などを受けた人が、たとえ心が傷ついたとしても、社会的評価を低下させられたと認められない場合は、名誉毀損罪は成立しないことに注意が必要です。
誹謗中傷と批判の違いは
どう判断するか?
誹謗中傷とは、「根拠のない悪口やデマを言いふらす」、「それらをインターネット上に投稿する」といった行為で名誉や人格を傷つけ、人や企業の社会的評価を低下させる行為です。
批判と誹謗中傷の違いに明確な基準があるわけではなく、判断が難しい面がありますが、批判は異なる意見を主張することといえるので、基本的には、悪意や虚偽の有無が大きな判断材料になります。
また仮に、投稿者に悪意はなくても、受け取った人にとっては誹謗中傷となる可能性もあるので注意が必要です。
判断が難しい場合は、今後の法的対応も含めて弁護士に相談してみることをおすすめします。
SNSで誹謗中傷により
名誉毀損された時の対処法は?
では、インターネット上のSNSや掲示板などに根も葉もない誹謗中傷をされた場合、どのように対応すればいいのでしょうか。
大きくは、次の4つがポイントになります。
- ①サイト運営会社に、インターネット上の誹謗中傷投稿やコメントの削除を依頼。
- ②サイト運営会社に対して発信者情報開示請求を行ない、IPアドレスを取得。
- ③IPアドレスからプロバイダ(インターネット接続事業者)を特定し、発信者情報開示請求を行なう。
- ④発信者が特定できたら、示談交渉、刑事告訴、損害賠償請求の検討に入る。
次の章から、詳しく解説していきます。
サイト運営会社への削除依頼
削除依頼をするメリットと
デメリット
誹謗中傷の投稿、書き込みを確認したら、まず内容を保存します。
その後は、サイト運営会社を確認して、直接、削除依頼を行ないます。
X(旧Twitter)やInstagramなどのSNS、5ちゃんねるなどの掲示板は利用者が多く、依頼フォームが用意されていることが多いので、削除の条件などを確認して連絡します。
削除依頼をすることのメリットは、費用がかからず手軽に請求できることですが、サイト運営会社が削除請求を拒否する可能性もあることがデメリットになるでしょう。
裁判所に仮処分の申請をする
サイト運営会社が削除要求に応じない場合は、投稿の削除を求めて法的に仮処分の申請を行なうことも検討しましょう。
裁判所に、仮処分という暫定的な措置を求め、認められた場合は、裁判所がサイト運営会社に対して削除命令を発令する、という流れになります。
発信者情報開示請求の流れと
注意するべきポイント
発信者情報開示請求とは?
前述の手続により、サイト運営会社に削除依頼し、投稿などが削除されたとしても、残念ながら根本的な解決になりません。
なぜなら投稿者は、また同じように誹謗中傷投稿をする可能性がありますし、投稿内容が拡散されてしまう可能性があるからです。
そこで次に打つ手として、「発信者情報開示請求」を行ない、投稿者の身元を特定して法的責任を追及していくことが必要になります。
発信者情報開示請求の流れと
手続き
IPアドレスを求める
加害者の身元を特定するため、サイト運営会社(コンテンツプロバイダ)に対して発信者情報開示請求をして、IPアドレスの開示を求めます。
IPアドレス(Internet Protocol Address)というのは、インターネットに接続しているデバイスに割り当てられる、インターネット上での住所を示すものです。
【参考資料】:発信者情報開示命令申立て(裁判所)
個人情報の開示を請求する
ただし、IPアドレスからは特定できる情報と、できない情報があります。
- ・通信が行なわれた国(日本の場合は、都道府県まで特定が可能)
- ・IPアドレスの保有者
- ・回線情報
- ・端末情報(PC、スマートフォン、タブレットなど)
- ・OS(ソフトウェア)
<特定できない情報>
- ・氏名
- ・住所
- ・その他の個人情報
そのため次は、アクセスプロバイダ(通信回線などを経由して、契約者にインターネットへの接続を提供する事業者)に対して、該当するIPアドレスを利用していた者の個人情報(氏名や住所など)の開示(任意開示)を請求することが必要になります。
任意開示を求める方法としては、弁護士会照会(弁護士法23条の2に基づく照会)などの方法があります。
訴訟を提起する
しかしながら、任意開示請求には強制力がないため、プロバイダ自らが発信者情報開示に対応することは、ほぼないのが現状です。
その場合は、アクセスプロバイダに対して「発信者情報開示請求訴訟」を提起することになります。
流通プラットフォーム対処法について>
プロバイダ等の損害賠償責任の制限、発信者情報の開示請求、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続について定めた法律が「プロバイダ責任制限法」です。
発信者情報の開示請求については、第5条の規定が該当します。
以前は、コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダそれぞれに対して、別々の手続きをとる必要があったため、発信者を特定するには両方の裁判手続が必要でした。
しかし、簡易で迅速に発信者情報の開示手続きを行なえるよう改正が行われ、2022(令和4)年10月1日に施行されています。
この法改正により、被害者が加害者に損害賠償請求する裁判手続も含めると、計3回の裁判手続が必要だったところ、現在では「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」によって、発信者情報の開示請求を1つの手続で行なうことが可能になっています。
また、海外の事業者に対する発信者情報開示請求についても、この非訟手続により、訴状の送達などにかかっていた時間が短縮され、手続きが簡易になっています。
【参考資料】:インターネット上の違法・有害情報に
対する対応(プロバイダ責任制限法)(総務省)
プロバイダ責任制限法Q&A(総務省)
なお、プロバイダ責任制限法は2024(令和6)年にも改正が行われ、「情報流通プラットフォーム対処法」と名称が変更され、2025(令和7)年4月1日から施行されます。
これは、インターネット上の個人や企業への誹謗中傷などによる権利侵害の被害回復が実効的になされるよう、SNS等の事業者(大規模プラットフォーム事業者)に対して、「投稿の削除対応の迅速化」や、その「運用状況の透明化」などの具体的措置を義務づけるものになっています。
【参考資料】:情報流通プラットフォーム対処法の 省令及びガイドラインに関する考え方(総務省)
発信者情報開示請求訴訟で
注意するべきポイント解説
訴訟においては、次のポイントが重要になります。
権利侵害の明白性
多くの場合、「権利が侵害されたことが明らかであること」が問題となり、明白性については、
- ・権利侵害の事実
- ・違法性阻却事由の存在をうかがわせるような事情が存在しないこと
がポイントになります。
通常であれば違法である行為が違法にならないような特別の事情のことを「違法性阻却事由」といいます。
刑法には、「正当防衛」「緊急避難」「正当行為」の3つが明記されています。
発信者情報開示請求では、情報を開示される側(発信者側)のプライバシーや表現の自由が考慮されます。
そのため、請求者(被害者)側が違法性阻却事由について主張立証する必要があることに注意が必要です。
正当な理由の存在
発信者情報開示請求者には、正当な利益として発信者情報を取得するための法的手段をとるにあたり、次のような発信者本人を特定する必要性が求められます。
- ・発信者に対して削除要請を行なうため
- ・民事において損害賠償請求を行なうため
- ・名誉回復の要請を行なうため
- ・差止請求権を行使するため
- ・刑事告発・告訴を行なうため など
総務省令で定められている発信者情報には、次のものがあります。
- ・氏名
- ・住所
- ・メールアドレス
- ・発信者のIPアドレス/IPアドレスと組み合わされたポート番号
- ・携帯端末のインターネット接続サービス利用者識別番号
- ・SIMカード識別番号
- ・発信時間(タイムスタンプ) など
これらは重要な情報になるため、発信者情報開示請求を行なう際は弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。
発信者情報の保存期間に
要注意!
発信者情報は、いつまでも残っているわけではありません。
通常、サイト運営会社がIPアドレスのログ情報(利用履歴を記録したデータ)を保存しているのは、投稿から約3~6か月と考えられています。
サイト運営会社に対して発信者情報開示請求や訴訟を提起する場合には、IPアドレスのログ情報の消去禁止も同時に求めることが重要になってくることを知っておいていただきたいと思います。
名誉棄損でSNS投稿者の法的処罰を求める方法
SNSの誹謗中傷投稿をやめさせ、今後新たな投稿をさせないためにも、投稿者の身元が特定できたら、刑事と民事の両方で法的責任を追及していく方法があります。
刑事告訴
警察などの捜査機関に通報し、刑事告訴をする方法があります。
刑事告訴とは、被害者などが犯罪被害の申告をして、加害者の法的処罰を求めることで、罰金刑や拘禁刑などの刑事処分を求めることができます。
【参考資料】:インターネット上の誹謗中傷等への対応(警察庁)
前述したように、SNSの誹謗中傷投稿による名誉毀損では次のような犯罪が成立する可能性があります。
名誉棄損罪(刑法第230条)
不特定多数の人が閲覧するインターネット上での書き込みや投稿には、名誉棄損罪が成立する可能性があります。
刑事罰:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
侮辱罪(刑法第231条)
事実でなくても、インターネット上の書き込みや投稿の内容が侮辱にあたる場合は侮辱罪が成立する可能性があります。
刑事罰:1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料
被害者が警察に告訴をすることで、検察が犯罪として加害者を起訴して刑罰を問うことができるものを「親告罪」といいます。
名誉棄損罪や侮辱罪は親告罪のため、被害を受けた場合は刑事告訴をする必要があるのです。
<名誉毀損が認められる条件>
SNSなどへの投稿で名誉毀損が認められるには、次の条件を満たしている必要があります。
①公然性
不特定または多数の人によって認識される、閲覧可能な状態であること。
たとえば、被害者個人宛てに誹謗中傷メールなどが送られてきても、不特定多数の人が見るわけではないので公然性は満たしません。
②事実摘示性
事実を摘示していること。
SNSの投稿内容が真実かどうかではなく、具体的な事実を出していて、その真偽を確認できるかどうかがポイントになります。
たとえば、「〇〇は会社のお金を横領している」、「〇〇は〇〇と不倫をしている」という内容には事実摘示性はあると判断されますが、「〇〇はアホだ」という投稿には確認する証拠がないため事実の摘示にはならないわけです。
なお、「アホ」「バカ」「ブス」などは主観的な表現になるので侮辱罪を検討していくのがいいでしょう。
③名誉毀損性
SNSの内容が、人の社会的評価を低下させるようなものであること。
「〇〇は犯罪者」など、社会通念上その人の名誉を傷つけ、評価を低下させるような内容が該当します。
④相手を特定できていること
前述したように、投稿者の身元が特定できていることが必要です。
⑤時効が成立していないこと
一定の時間が経過したために、あることの効力や権利が消滅する制度を「消滅時効」といいます。
時効には、民事と刑事があります。
民事で時効が成立して、相手方が時効を援用すると慰謝料などの損害賠償請求ができなくなるので注意が必要です。
※時効の援用=時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張すること。
ここでは、名誉棄損の投稿を行なった者が時効を主張すること。
なお、名誉毀損で相手に刑事罰を科したい場合、「告訴時効」と「公訴時効」があることを知っておいてください。
「告訴時効」
名誉毀損罪は親告罪のため刑事告訴をする必要があり、この時効期間は「犯人を知った時から6か月」となっています(刑事訴訟法第235条)。
「公訴時効」
被害者が警察に刑事告訴をすると事案は検察に送られ、検察は起訴するかどうかを決定します。
その後、裁判により有罪か無罪かの判決がされるわけですが、この時効期間について名誉棄損罪の場合は「3年」となっています(刑事訴訟法第250条2項6号)。
民事における損害賠償請求
損害賠償請求の流れ
誹謗中傷の書き込みで名誉を棄損された場合は、損害賠償請求とをして民事上の責任を問うことができます。
一般的な流れとしては、次のように進めていきます。
- ・相手方に内容証明郵便で請求
- ・交渉を開始
- ・交渉が決裂した場合は損害賠償請求訴訟を提起
- ・裁判所の判決
示談による和解
当事者同士の示談交渉は、なかなか着地点を見いだせない場合が多く、もめてしまうことも多いため、弁護士をたてて交渉を進めていくほうが解決への近道だといえます。
示談交渉では次のような項目の取り決めを行ないます。
- ・投稿者から被害者への謝罪。
- ・今後、これ以上の名誉棄損投稿を行なわないこと。
- ・名誉棄損投稿を行なった場合は刑事告訴に踏み切ること。
- ・示談が成立すれば告訴は行わないこと(すでに告訴していた場合は取消すこと)。
- ・慰謝料などの損害賠償金の金額・支払い方法・支払期限
- ・示談成立後は「示談書(合意書)」を作成。
なお、相手方が交渉に応じない場合、あるいは直接交渉をしたくない場合なども含め、早急に弁護士に依頼して代理人になってもらい、交渉を任せてしまうことをおすすめします。
民事上の時効期間にも要注意!
損害賠償請求ができる期間(時効期間)は、名誉毀損の相手を知ったときから「3年」、名誉毀損の事実から「20年」になっています。
実務的に考えると、発信者情報開示請求をして投稿者を特定できた時から3年、名誉毀損の投稿がされた時から20年で時効成立となってしまうので注意が必要です。
SNSで名誉棄損投稿をされた場合は弁護士にご相談ください!
ここまで、SNSでの誹謗中傷による名誉毀損への対応についてお話ししてきましたが、解決までにはやらなければいけない手続きが山ほどあり、法律の知識も必要なことがわかっていただけたと思います。
やはり、望む結果を得るためには弁護士への相談・依頼をご検討ください。
- ・発信者の特定手続きを依頼できる。
- ・刑事告訴や損害賠償請求など法的な問題を任せられる。
- ・手続きの手間が省けて、問題の早期解決を実現できる。
- ・相手方との交渉などでの精神的な負担・ストレスを大幅に軽減できる。
弁護士法人みらい総合法律事務所では、いつでも無料相談を行なっています。
※事案によるので、まずはお問い合わせください。
SNSに関わるトラブルは他人事ではありません。
一人で悩まず、まずは一度、気軽にご連絡ください。