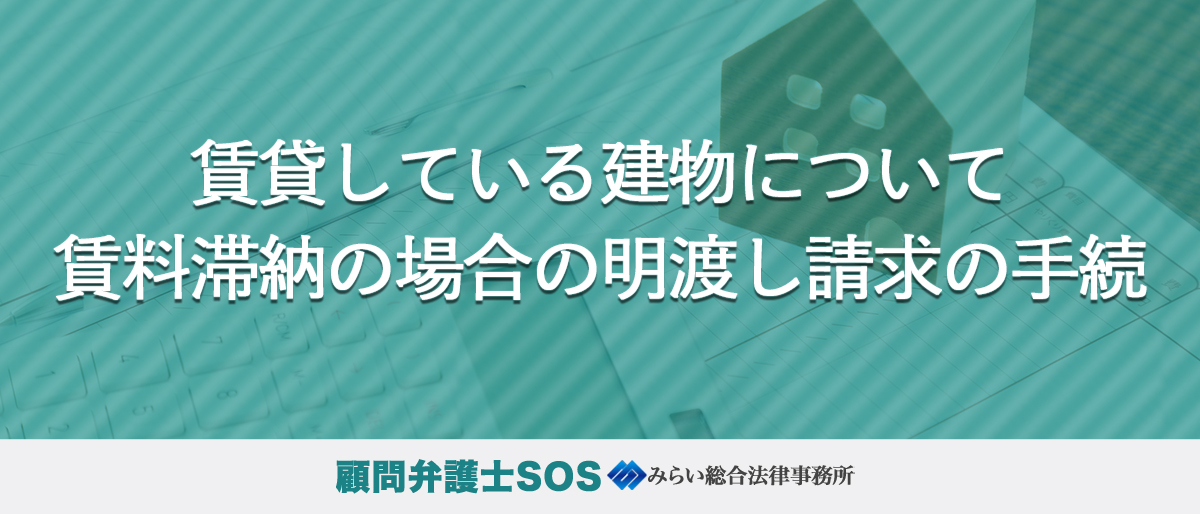賃貸している建物について賃料滞納の場合の明渡し請求の手続
本記事では、賃貸している建物で賃料滞納が発生した場合の明渡し請求の手続と流れ、さらには訴訟を起こす場合の手続と注意ポイントなどについて、弁護士が解説します。
重要なポイントは次の3つです。
- ① 賃料滞納による建物明け渡し請求では、まずは賃貸契約解除のために「内容証明郵便」で賃料支払を催告のうえ、支払いがされない場合の「契約解除通知」を送付します。
- ② 契約解除を通知しても賃借人が退去しない場合は、強制的に退去させるために
「建物明け渡し訴訟」を提起します。 - ③ 裁判上の和解をし、または判決が確定して賃借人が建物を明け渡さない(退去しない)場合は、強制執行により賃借人を強制的に
退去させることができます。
できるだけ、わかりやすい解説をしています。
あまり難しく考えずに、まずは最後まで読んでいただいて、正しい法的知識を身につけてください。
目次
建物明け渡し請求の流れと手続を
解説
建物明け渡し請求とは、シンプルに言えば、賃料を支払わない入居者に出ていってもらうように求めることです。
賃貸人(貸主)として、建物を貸しているなら賃料を得るのは当然です。
しかし、困ったことに賃借人(借主)が賃料を支払わない、滞納するという事態が起きることがあります。
そうした場合は、「建物明け渡し請求」と「建物明け渡し訴訟」が必要になるので、おおまかな流れと手続を解説していきます。
契約解除の準備
賃料滞納は契約違反となるため、まずは契約解除の準備を進めていきます。
信頼関係破壊の確認
しかし、賃借人が賃料の滞納を1回でもすれば契約解除ができるかといえば、そうはいきません。
判例上、契約解除をして建物明け渡し請求をするには「信頼関係破壊」が認められる必要があります。
通常、3か月ほどの滞納があれば認められるもので、これを「信頼関係破壊の論理(法則)」といいます
ただし、次のようなケースでは信頼関係破壊が否定される場合があります。
- ・契約解除直後に、賃借人が滞納額を支払った。
- ・賃借人に病気や高齢などの理由があり滞納が発生した。
- ・これまで賃借人は長期間にわたり滞りなく賃料を支払っていたが、最近になって滞納が発生した。
- ・賃貸人側の落ち度、ミスのために賃料滞納が発生した。 など
内容証明郵便で催告
契約解除の意思表示を賃借人に伝えるため、賃料の支払いの期限を決めて、「内容証明郵便」で催告および解除通知をします。
内容証明郵便には、次の項目などを明記します。
- ・滞納家賃の金額
- ・支払い期限の日付
- ・振込先の情報
- ・支払期限日までに家賃を支払わなければ、あらめて通知をすることなく賃貸契約を解除する旨 など
<注意するべきポイント>
- ・支払期限日は、内容証明郵便を発送した1週間後を目途に設定するのがいいでしょう。
- ・内容証明郵便は、弁護士に依頼したほうが賃借人にプレッシャーをかけることができますし、賃貸人はその後の手続きも有利に進めることができます。
- ・そのうえで、内容証明郵便は弁護士から送付し、賃料の滞納分の振込先は法律事務所が指定する預かり口座にします。
なお、賃借人が行方不明の場合は、内容証明郵便の送付を行なうことなく、訴状提出を行ないます。
<コラム①裁判をしたくない場合の
対処法>
提訴して裁判を行なうと、時間も費用もかかってしまうのが現実です。
また、後ほど詳しく解説しますが、裁判後に強制執行まで進むと相応の費用がかかってしまいます。
できれば、強制執行までやりたくない、できるだけ費用を抑えたいと考える方もいらっしゃるでしょう。
- ・賃借人がいつまでも出ていかず、滞納賃料がさらにかさんでしまうのを避けたい。
- ・早く新たな賃借人を募集して、家賃収入を得る機会を逃したくない。
という場合は、滞納家賃の支払い交渉よりも、退去の交渉を優先させていくことも重要になってきます。
契約解除後、提訴して裁判に入る前に次のような提案をして、任意の退去を促す方法もあります。
「ここで出て行ってくれるなら、滞納家賃は請求しない」
「立ち退き料として〇万円支払うから出ていってくれ」
若干の持ち出しがあっても、和解してしまったほうが得な場合もあるのです。
一方、賃借人にプレッシャーをかける場合は退去を催促する際、次のような内容を賃借人に伝えるといいでしょう。
- ・期限までに退去しなければ、提訴して裁判に移行する場合もあること。
- ・裁判になると、賃貸人(家主)側の弁護士費用なども家賃滞納者の負担になる可能性があること。
- ・連帯保証人も裁判で被告に加える場合があること。
状況に応じて対応は変わってくるので、一度、弁護士に相談してみるのもいいでしょう。
建物明け渡し訴訟の手続と注意
ポイントについて
ここからは、提訴して裁判に突入した場合について解説していきます。
建物明け渡し訴訟の手続と流れ
訴状提出
契約解除を通知しても、賃借人が法的義務を無視して建物(賃貸物件)に住み続けるケースがあります。
そうした場合は、強制的に退去させるために「建物明け渡し訴訟」を提起します。
訴状を作成し、裁判所に提出しますが、その他に次のような書類を手配する必要があります。
- ・訴状
- ・賃貸借契約書
- ・発送した内容証明郵便の控え
- ・内容証明郵便の配達記録証明書
- ・賃貸している不動産の固定資産評価証明書
- ・代表事項証明書(家主が法人の場合)
- ・弁護士に依頼する際の委任状 など
<コラム②賃借人が訴状を受け
取ろうとしない場合の対応策は?>
訴状を裁判所に提出すると、裁判所から訴状を賃借人(家賃滞納者)に送達するシステムになっています。
通常、訴状は賃借人には手渡しで届けられますが、相手方がわざと受け取らない、あるいは長期不在などで受け取れないといった場合は、次のような対応をとる必要があります。
「休日送達」
仕事などで平日は訴状を受け取らない、受け取れないような場合は、裁判所から休日に再度訴状を送達してもらうことも可能です。
「就業場所への送達」
就業場所(勤務先等)に裁判所から訴状を送達してもらうことも可能です。
「付郵便送達」
相手方が受け取りをしたかどうかに関わらず、発送の事実をもって、送達されたと見なすものです。
そのため、賃借人が訴状を受け取らなくても、訴状は届いたものと同じ扱いになります。
裁判所から書留郵便で訴状を送達してもらうことになりますが、賃貸人のほうで相手方の住所地、居住状況、就業場所などについて調査をする必要があります。
「公示送達」
相手方の所在が不明で意思表示が到達されないといった場合に、裁判所に申立てをすることで、法律上、その意思表示を到達させてしまう制度です。
公示送達では、裁判所の掲示板に内容が掲示された日から2週間が経過すると、訴状の送達があり、相手方が受け取った、という扱いになります。
【参考資料】:意思表示の公示送達(東京簡易裁判所)
第1回期日
建物明け渡し訴訟の「管轄裁判所」(裁判をする土地)は、原則として、当該物件の所在地を管轄する地方裁判所・簡易裁判所になります。
裁判所が訴状を受理すると、通常は訴状提出から1~2か月後に第1回期日が開かれます。
弁護士に依頼した場合は、弁護士のみが代理人として出席するので、賃貸人ご本人は出席する必要はありません。
なお賃借人には、第1回期日に出席するよう、裁判所から呼出状が送達されます。
判決/和解
賃借人が裁判に出席するか否かなどによって、裁判所の判断・対応は次のように変わります。
●賃借人が裁判に欠席した場合
裁判所は審理を終結させ、通常は1~2週間後に判決言渡期日を定め、建物明け渡しを命じる判決を言い渡します。
●賃借人が裁判に出席して賃貸人の主張を
認めた場合
通常、裁判所は和解の意向の有無を聴取するため、和解するかどうか、あらかじめ弁護士と話し合って決めておく必要があります。
賃貸人は和解せずに、建物明け渡しを命じる判決を求めることもできます。
和解が成立した場合は、ここで審理は終結となります。
和解を求めない場合は、審理の終結後、約1~2週間後に裁判所が判決言渡期日を定めます。
●賃借人が裁判に出席して賃貸人と争った場合
裁判所は賃借人の主張が法的に認められるかを審理するため、およそ1か月~1か月半に1回程度期日を開き、賃貸人と賃借人それぞれの主張の交換を行なっていきます。
賃貸人としては、訴訟を早期に終結させるためには、できるだけ証拠を集めて主張を積み上げていく必要があります。
その後、裁判所は審理を結審し、判決を言い渡しますが、途中で和解することもできます。
判決における注意ポイント
判決は書面で送達されるため、判決期日に賃貸人と賃借人は裁判所に出頭する必要はありません。
判決の送達を受けた翌日から2週間以内であれば、賃借人は控訴することができます。
その場合、賃貸人は弁護士と話し合い、今後の対応について検討します。
2週間が経過すると判決は確定するので、なおも賃借人が建物を明け渡さない(退去しない)場合は、強制執行により賃借人を強制的に退去させることができます。
和解(建物明け渡しを含む)における注意ポイント
和解については、賃貸人と賃借人の双方が納得して合意するなら、訴訟が進行中のほとんどの段階で和解を成立させることができます。
和解を成立させる場合、建物明け渡しまでの猶予期限を決め、「何月何日まで」と設定する必要があります。
和解したものの、賃借人が猶予期限までに退去しない場合は強制執行を行なうことになります。
強制執行の手続と流れを解説
家賃滞納による強制執行とは?
強制執行とは、執行官や執行業者などが臨場(現場に行くこと)したうえで、賃借人を強制的に退去させる手続です。
第168条(不動産の引渡し等の強制執行)
1.不動産等(不動産又は人の居住する船舶等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の引渡し又は明渡しの強制執行は、執行官が債務者の不動産等に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法により行う。
建物明け渡しの強制執行は、2段階で行われ、①「催告執行」(1回目の強制執行)と、②「断行執行」(2回目の強制執行)があります。
<コラム③占有移転禁止の
仮処分とは?>
建物明け渡し訴訟中に、占有者が変更され、強制執行が不可能になる事態を防ぐために、民事保全手続きの一種として認められているのが、「占有移転禁止の仮処分」の手続きです。
たとえば、次のようなことが起きる場合があります。
転貸していたため、BやCといった人間が部屋に住んでいた。
②該当する物件に賃借人以外の複数の人間が出入りしており、占有者の特定が困難な状態。
上記①の場合、判決が確定しても、それはAを強制的に退去させることしかできず、BやCを退去させる効果はありません。
そのため、BやCを相手に、あらたに訴訟を起こさざるを得なくなってしまうのです。
こうした事態が想定される場合は、あらかじめ占有移転禁止の仮処分の手続きを検討するべきでしょう。
強制執行の手続と流れ
強制執行申立書などの提出
強制執行申立書と必要書類を裁判所に提出します。
- ・強制執行申立書
- ・送達証明書
- ・資格証明書(家賃滞納者が法人の場合)
- ・委任状 など
明け渡しの催告執行
強制執行申立書を提出してから2週間以内に「催告執行」が行なわれます。
執行官(裁判所職員)・執行業者・弁護士・立会人などが貸室に行き、賃借人に建物の明け渡しの期限を伝えて、退去を要請します。
明け渡しの期限は、原則として催告執行の実施日から1か月以内です。
明け渡しの断行執行
期限内に賃借人が自主的に退去しなければ、「断行執行」が行なわれます。
専門の執行業者が物件内に残っているすべての荷物を搬出します。
賃借人がいない場合は、鍵を開けて中に入ります。
執行官は、賃借人がその場に居座っていても強制力をもって物件から追い出すことになります。
その後、鍵業者が新しい鍵の交換作業を行ないます。
荷物(残置物)の保存と処分
原則として、物件内から搬出した残置物は、1か月ほど保管しておきます。
その場合、賃貸人が保管場所を用意できないなら、執行業者に倉庫を手配してもらうなどの必要があるため、費用がかかってしまうことになります。
賃借人が取りに来ない場合は、売却または廃棄することができます。
なお、賃借人が長期の間、行方不明であったり、明らかに価値の低いものの場合は「即時売却」の手続きが取られる場合もあります。
強制執行の費用について
強制執行にかかる費用には、次のものなどがあります。
裁判所に納める予納金:10万円程度
- ・執行官が手続きを進めていく際の費用などに使われます。
- ・各裁判所によって金額が異なります。
- ・強制執行の手続終了後、返金がある場合もあります。
執行業者に支払う費用:物件によって金額が
異なる
- ・おおよその金額は次のようになります。
- ・ワンルームマンション/20万円~30万円程度
- ・ファミリー向けマンションなど/50万円~100万円程度
- ・一戸建て住宅など/100万円以上
実費(各種書類の取得費用・郵送費用・印紙代など):10万円程度
弁護士費用:案件により異なる
・おおむね10万円~50万円ほどのケースが多いといえます。
荷物がかなり多い場合、ペットがいる場合、危険物など特殊なものがある場合などでは執行費用が高額になるケースがあります。
強制執行の費用を賃借人に請求できるか?
なお、強制退去させた賃借人に対して、費用の一部を請求することが可能です。
ただし、簡単に事が運ぶケースは少ないため、詳しい内容・費用の見積もりなどについては、建物の明け渡し請求・訴訟に精通した弁護士に問い合わせてみることをおすすめします。
家賃滞納でお困りの場合は弁護士にご相談ください!
これまでも経験されている方もいらっしゃると思いますが、家賃を滞納した賃借人への対応は、なかなか難しく、早期に解決せず長引いてしまう場合があります。
そうした時は、一人で悩まず、弁護士に相談・依頼することも検討してください。
弁護士に相談・依頼すると、次のようなメリットがあります。
法的に適切な対応を依頼できる
契約解除ができるかどうかの判断は、法的な知識が必要になります。
また当然ですが、建物明け渡しの請求や訴訟では法的な手続きが必要です。
賃貸人の方は法的な知識がなくても、弁護士に依頼することで、適切な対応をしてもらえます。
裁判の前に解決できる可能性がある
賃借人を提訴する前の交渉段階で弁護士に依頼することで、弁護士が賃貸人の代理人として交渉をしてくれます。
ここで退去や家賃回収ができる可能性が高まります。
早期の解決が可能になる
賃貸人と賃借人の当事者同士のやり取りでは、なかなか解決できない場合が多くあります。
その点、弁護士に依頼することで早期解決も可能になります。
強制執行も任せることができる
裁判後に強制執行を行なう場合、賃貸人が個人で実行し、解決していくのは難しいと言わざるを得ません。
建物明け渡しの請求や訴訟に精通した弁護士なら、安心してすべての手続きを任せることができます。
精神的なストレスから
解放される
賃料滞納の賃借人への対応は、なにかと精神的なストレスが大きく、手続きも難しいものです。
弁護士に任せてしまえば、賃貸人は煩わしさやストレスから解放され、事業に集中でき、安心して日常生活を送ることができます。
弁護士法人みらい総合法律事務所では随時、無料相談を行なっています。(※事案によるので、まずはお問い合わせください)
賃料滞納でお困りの場合は、まずは一度、気軽にご連絡いただければ幸いです。