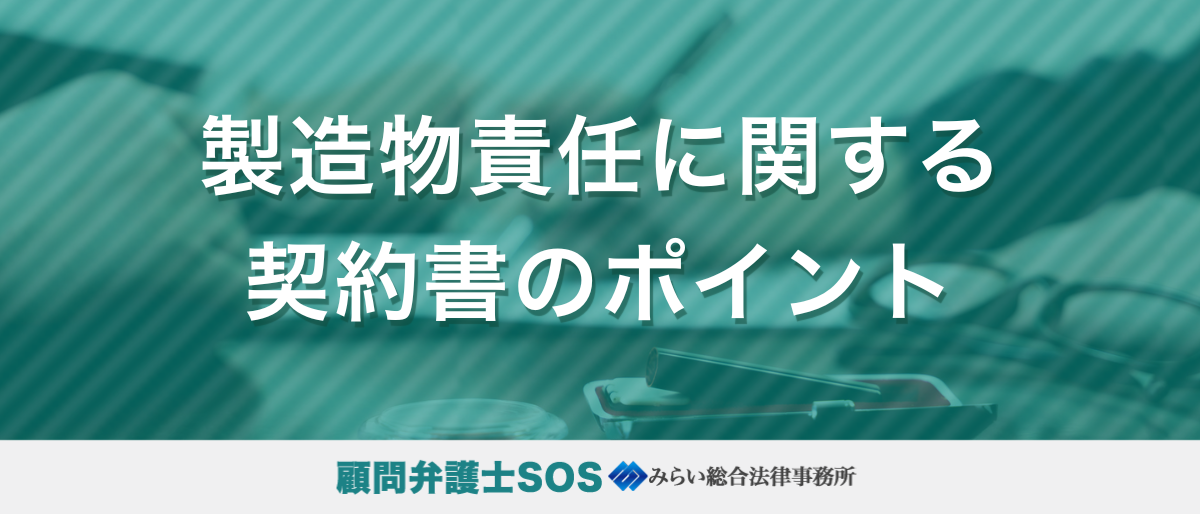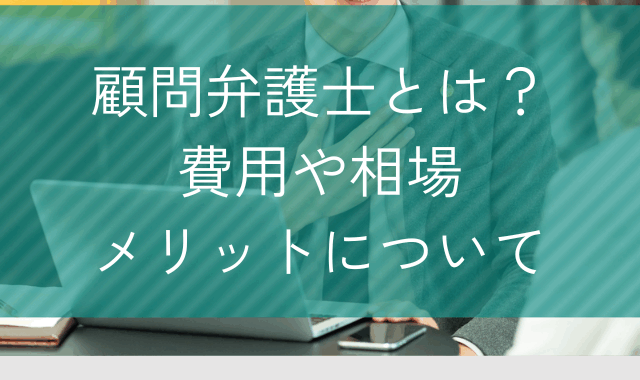製造物責任に関する契約書のポイント
製造物(製品)の欠陥などにより損害が生じた場合に重要になるのが「製造物責任法」です。
以前は、欠陥製品によって損害を受けた被害者は、製造業者(メーカー)に過失があったことを立証し、損害賠償請求をすることが必要でした。
しかし、製造物責任法は、製造業者の過失ではなく、製造物に欠陥があったことを要件とするので損害賠償請求がしやすくなっています。
そのため、製品の製造に関して委託する企業も、受託する企業も製造物責任法で注意しなければいけないポイントを知って、リスクを回避する必要性が高まっています。
- ・製造物(製品)の欠陥によって生じた損害の責任は、はたして誰にあるのか?
- ・誰が、誰に対して、その損害の責任追及や損害賠償請求をすることができるのか?
- ・関連する法律は、どういった内容なのか?
- ・製造物の委託企業、受託企業ともにトラブルを回避するためには何が大切なのか?
本記事では、こうした問題についての法的な対応方法、リスク回避策を中心に解説していきます。
目次
製造物責任法の概要を確認
製造物責任法とは?
製造物(製品)に欠陥があり、その欠陥によって人の生命や身体、財産等に損害が生じた場合、製造業者などがその損害を賠償する責任を負う、という考え方を「製造物責任」といいます。
英語のproduct liability(プロダクト・ライアビリティ)の頭文字をとって、「PL」とも呼ばれます。
民法の不法行為責任(民法第709条)に基づき損害賠償請求する場合、被害者(原告)が加害者(被告)の過失を立証する必要があります。
※不法行為責任=故意または過失により誰かに損害を与えた場合に、その損害を賠償する責任。
しかし、過失の証明が困難な場合も多く、被害者が損害賠償を得ることができないという問題がありました。
たとえば、ある電化製品に欠陥があることの過失を立証して製造業者に損害賠償を求める場合、製造に関与していないユーザー(被害者)が製造業者の過失を立証して、責任を追及していくことは非常に困難です。
そこで、この責任を明確化し、被害者の救済を目的とするため、製造業者の過失ではなく、製造物に欠陥があったことを要件とすることで損害賠償請求をしやすくしたのが「製造物責任(PL)法」ということになります。
対象となる製造物とは?
製造物責任法では、製造物を「製造又は加工された動産」と定義しています(第2条1項)。
民法上、動産とは不動産以外のもののことを指します(民法第86条2項)。
サービスや不動産、未加工の動産は定義上含まれません。
たとえば、コンピュータのプログラムは対象になりませんが、プログラムに欠陥があったソフトウェアを搭載したパソコンなどを使用したことで損害を受けた場合は、パソコン(ハードウェア) = 動産となり製造物責任法の対象になるわけです。
責任を負う者の範囲
製造物の責任を負う者
製造物責任法では、次の者が責任を負うことになります(第2条3項)。
- ・製造業者
- ・輸入業者
- ・表示製造業者
(※自ら製造業者として製造物にその氏名等の表示をした者、製造物にその製造業者と誤認させるような表示をした者、その実質的な製造業者と認めることができる表示をした者)
たとえば、ある部品に欠陥があった場合で考えてみます。
その部品の製造業者は、業として部品を製造しているので製造物責任を負います。
同時に、その部品を使って製造品を完成させた製造業者も製造物責任を負います。
そのため、両者ともに損害賠償請求を受ける可能性があるということになります。
製造物の責任を負わない者
基本的に販売業者は責任を負いません。
しかし、輸入業者や表示製造業者になる場合は責任を負う対象になるため注意が必要です。
製品の設置・修理については、製品の流通後のことであるため、設置・修理業者は基本的には製造物責任を負う対象になりません。
OEMやプライベートブランドの考え方
OEM
OEM(他社ブランドの製品を製造すること)で他社に製造委託をした企業は、自ら製品・商品を製造していませんが、自社ブランドであることを表示するので表示製造業者として製造物責任を負うことになります。
OEM製品・商品では、自社ブランド製品の製造委託をする企業(製造委託者)と、これを受託して製造する企業(製造受託者)の両社が製造物責任を負うことになるわけです。
つまり、この両社ともユーザーから責任追及、損害賠償請求を受ける可能性があるのです。
プライベートブランド
販売業者等が製造業者と誤認させるような表示をした場合は表示製造業者に該当するため、製造物責任を負う対象になります。
また、販売業者がその製品の製造に実質的に関与しているとみられる場合は表示製造業者に該当するため、製造物責任を負う対象となります。
この場合、販売業者等の経営の多角化や、製造物の設計・構造・デザイン等への関与の状況などから判断されます。
欠陥の定義と判断は?
法律上、製造物に関するさまざまな事情を総合的に考慮して、「製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」を「欠陥」といいます(第2条第2項)。
そのため、安全性に関わらないような品質上の不具合については、製造物責任法の損害賠償責任の根拠とされる欠陥には該当しないと考えられます。
なお、製造物の「通常有すべき安全性」の内容や程度は、個々の製造物や事案によって異なるため、製造物に関わる諸事情を総合的に考慮して判断されます。
法律上では、次の3つが考慮事情として例示されています。
- ・製造物の特性
- ・通常予見される使用形態
- ・製造業者等が当該製造物を引き渡した
時期
欠陥の分類
欠陥は、具体的には次の3つに分類されます。
製造上の欠陥
製造物の製造過程で粗悪な材料が混入、製造物の組立てに誤りがあった、などの原因で製造物が設計・仕様のとおりに作られず、安全性を欠くような場合。
設計上の欠陥
製造物の設計段階で、十分に安全性に配慮しなかったなどの原因のために、製造物が安全性に欠ける結果となった場合。
指示・警告上の欠陥
有用性または効用との関係で、除去し得ない危険性が存在する製造物について、その危険性の発現による事故を、消費者側で防止・回避するのに適切な情報を、製造者が与えなかった場合。
損害賠償請求について
製造物責任法では、損害賠償請求ができるのは次の場合と規定しています。
- ・製造物の欠陥によって人の生命、身体に被害をもたらした場合。
- ・欠陥のある製造物以外の財産に損害が
発生したとき(拡大損害が生じたとき)
欠陥による被害が、その製造物自体の損害にとどまった場合は、製造物責任法の対象になりません。
たとえば、自動車を走行中にエンジンルームから煙が上がり走行不能となったトラブルで、自動車以外には人的・物的な被害が生じなかった場合は、この法律の対象にはならないわけです。
このような損害の場合、民法に基づく不法行為責任や契約不適合責任、債務不履行責任などの要件を満たすのであれば、被害者からそれぞれの責任追及を受ける可能性があります。
拡大損害の定義は?
前述のように、拡大損害が起こった場合は、製造業者等は過失の有無に関わらず損害賠償責任を負うことになります。
製造物責任法で拡大損害に
該当する例
- ・建物の損害
家電製品の欠陥が原因で出火し、火災により家屋が損傷した場合の修繕費、建替え費など。 - ・交通事故で負った損害
自動車のブレーキの欠陥が原因で交通事故を起こし、運転者や搭乗者がけがを負った場合の治療費や入院費、休業損害など。 - ・家の内装の汚損等
洗濯機から水が漏れて、家具や床などが汚損した場合の修理費など。 - ・食に関わる健康被害
細菌やカビに汚染された食品を食べて食中毒が発生した場合の治療費や入院費、休業損害など。
拡大損害に該当しない例
- ・パソコンの欠陥のために出火したが、家財道具や床などの内装には損害がなかった。
- ・テレビの欠陥のために映像が映らないが、それ以外の損害はなかった。
- ・食品にカビが生えていたことが食後に判明したが、食中毒などの健康被害はなかった。
免責の規定
製造物責任を負う製造業者等は、一定の事項を立証することによって、賠償責任が免責されます(第4条)。
- ① 製造物を引き渡した時点における科学・技術知識の水準によっては、欠陥があることを認識することが不可能であったこと
(第4条1号、開発危険の抗弁) - ② 部品・原材料の欠陥が、もっぱら当該部品・原材料を組み込んだ他の製造物の製造業者が行なった設計に関する指示のみに起因し、欠陥の発生について過失がなかったこと
(第4条2号、部品・原材料製造業者の抗弁)
消滅時効について
製造業者等は、「消滅時効」についても注意する必要があります。
消滅時効とは、法律が定める一定の期間が経過することで、権利行使ができなくなる制度で、時効期間が過ぎると被害者は損害賠償請求などができなくなってしまうものです。
製造物責任法では、損害賠償請求権の消滅時効を次のように規定しています(第5条)。
- ① 被害者が損害および賠償義務者を知った時から「3年間」行使しないとき。
- ② 人の生命、身体を侵害した場合は、損害および賠償義務者を知った時から「5年間」行使しないとき。
- ③ 製造業者等が当該製造物を引き渡した時から「10年」を経過したとき。
これらの定めの期間うち、より早く到達したときに消滅時効が成立します。
【参考資料】:製造物責任法の概要Q&A(消費者庁)
製造委託契約の締結と契約書で
注意するべきポイントを解説
企業間で製品の製造・販売・流通に関する契約を交わす際には、製造物責任法に関連する法的責任を踏まえた契約設計が不可欠です。
ここでは契約の種類と、製造物責任に関するリスク分担を明確にするために契約書に盛り込むべき項目について解説します。
製造物責任法に関連する
契約の種類
製造物責任法に関連する契約の種類としては、主に次のものがあげられます。
- ・製造委託契約
発注者が製造者に製品の製造を委託する
契約。
OEM契約も含まれる。 - ・販売店契約
製造者が販売店に製品の販売を委託する契約。 - ・ライセンス契約
技術や商標を提供し、製品の製造・販売を許諾する
契約。 - ・輸入販売契約
海外製品を国内で販売する際の契約。
輸入業者は製造者と同等の責任を負う。
たとえば、製品の製造を外部の業者に委託する際には「製造委託契約」を締結する必要があります。
なぜなら、製造委託契約は製品の品質や納期、知的財産の保護など、企業の信頼と利益に直結する重要な契約だからです。
製造物責任法に基づいて契約書を作成する際、次のポイントを盛り込むことでリスクを回避できます。
責任分担条項
製造者、販売者、流通業者の間で、製品の品質や安全性に関して製造物責任が発生した場合、どの当事者が一次的責任を負うかを明確にして、明記しておくことが重要です。
製品の欠陥に起因する損害については、製造者が一義的に責任を負うものとする
品質保証条項
製品が、法的に求められる一定の品質基準を満たしていることを保証する旨を記載します。
製造者は、製品がJIS規格に準拠し、安全性を有することを保証する。
製品の仕様条項
どういった製品を(製造対象)、どのような品質・性能(納品検査基準)で製造するのかを仕様書に明記し、明確化しておきます。
同時に、仕様の変更が発生した時の対応についても明記しておく必要があります。
使用が変更されればコストなどにも影響が及ぶため、受託者に不利益が生じかねません。
「対価」や「納期」、「品質」などについて、内容が曖昧な記載だと、あとで「完成品か否か」でトラブルに発展する可能性があるので注意が必要です。
検品・契約不適合責任条項
納品後の製品の検査方法と不具合対応(修理・代替・減額など)についても明記しておきます。
なお、改正民法(2020年4月施行)では、それまで「瑕疵担保責任」と呼ばれていたものは、「契約不適合責任」に統一されています。
「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」(改正民法第562条1項)に、売主が買主に対して負う責任を契約不適合責任といいます。
再委託の可否に関する条項
下請け業者への再委託を許可するかどうかを明確に規定しておきます。
通常、発注者の事前承諾を要件にする場合が多いといえます。
第三者との紛争に対する
責任条項
製品に関して、第三者の権利を侵害する等の紛争が生じた場合の責任についても明確化しておきます。
こちらについては、2024年10月に中小企業庁が「知的財産取引ガイドライン」を改定しています。
委託者(通常は大企業を想定)が、受託者(通常は中小企業を想定)に一方的に責任を転嫁することがないように定められています。
立ち入り調査権条項
製造現場への立ち入りの可否と条件について明記します。
通常、「正当な理由」や「事前合意」などの制限を設けます。
クレーム対応条項
事故や苦情が発生した際の対応手順、費用負担、報告義務などを定めておきます。
販売店は、消費者からの事故報告を受けた場合、速やかに製造者に通知し、協議の上対応する。
知的財産・ノウハウの保護条項
受託者は、委託者の要求以上の情報を提供する必要はないため、意図しない技術提供を避けるための条項が必要になります。
中小企業庁の「知財取引ガイドライン」には、次のような規定が盛り込まれています。
- ・受託者の秘密情報は受託者に帰属する
こと。 - ・受託者は秘密情報の開示義務を負わない
こと。 - ・受託者は、その保有する知的財産権の
提供義務を負わないこと。
【参考資料】:知的財産取引に関するガイドライン・契約書のひな形について(中小企業庁)
保険加入義務条項
さまざまな条項を記載し、契約書を交わしても、製造受託者に資力がなければ求償に応じられない場合もあるでしょう。
そうした場合に備えるためにも、製造物責任(PL)保険への加入を義務付け、販売店や委託元も被保険者に含めることなどを明文化しておきます。
製造物責任法にはPL保険への加入を義務付ける規定がないからこそ、契約書に定めておくことも大切になります。
製造者は、製造物責任保険に加入し、販売店を追加被保険者として登録するものとする。
免責条項
使用者の誤使用や改造など、製品の適切な使用方法や安全指示を守らなかったことなどによる損害については責任を負わない(責任を限定する)旨などを記載します。
免責条項を設定することで、リスクを最小限に抑えることができます。
製品の使用説明書に反する使用による損害について、製造者は責任を負わない。
製造委託契約書で注意するべきポイント
最後に、契約書を作成し、契約を締結する際の注意点についてまとめておきます。
契約書の文言は明確に記載する
契約書の文言が曖昧だと、実際に事故が発生した際に責任の所在が不明確となり、訴訟リスクが高まる可能性があります。
たとえば、次のような事例が考えられます。
自社ブランドで販売したところ、製品の欠陥による火災事故が発生。
消費者はブランド表示を根拠に国内メーカーに損害賠償を請求。
契約書には製造者責任の明記はあったが、表示製造業者としての責任は免れず、結果的にメーカーが損害賠償を負うことになった。
特に、OEM契約では、ブランド表示をした企業が「表示製造業者」とし、製造物責任法上の責任を問われる可能性があるため、契約書に「製造者が責任を負う」といった旨を明記するだけでは不十分だといえます。
仕様変更に関する条項を明確に規定する
仕様変更の手続きや費用調整方法などを契約書に明確に記載しておくべきです。
たとえば、受託企業(中小企業やスタートアップ企業)が製造途中で仕様変更を依頼したところ、委託企業が「追加費用が発生する」と主張。
契約書に仕様変更手続きが明記されていなかったため、納期遅延と追加請求で争いが起きるケースなどが考えられます。
納品後の不具合対応期間を
明確に規定する
製品の不具合への対応期間は、「納品後〇か月」といったように実態に即した期間設定をしておくべきです。
たとえば、納品から半年後に製品の不具合が判明したケースで、契約書には「検収後1か月以内に通知」と記載されていたため、委託企業が無償対応を拒否するといったトラブルなどが考えられます。
知的財産・ノウハウの保護を
明確に規定する
知的財産やノウハウ等の保護を明確に規定していなかったために起きるトラブルも回避しなければいけません。
たとえば、委託企業が、同様の製品を他社に委託して製造していたことが判明。
調査したところ、受託企業の設計図や製造ノウハウが無断で流用されていた、といったトラブルが考えられます。
こうしたトラブルを回避するためには、「守秘義務」や「自社内利用の禁止」、「知的財産権の帰属」、「委託先による流用禁止」などの条項の規定が有効です。
契約書を定期的に見直し
修正を加えていく
法改正や新たな裁判例などの変化に対応していくためには、契約書を定期的に見直し、修正する必要があります。
自社内に法務部がない、対応できないといった場合は早急に弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。
製造物責任法に関わる契約で
お困りの場合は弁護士に相談を!
製造委託契約は、単なる「作ってもらう契約」ではなく、品質・納期・知財・責任分担など多岐にわたるリスク管理が求められます。
契約書には、曖昧さを残さず、万一のトラブルにも備えた条項設計が不可欠です。
しかし……、
- ・社内に法務部を設置する余裕がない。
- ・社内に専門知識のある人材がおらず
対応できない。 - ・もう何年も同じ契約書を使い回しして
いるので心配になってきた。 - ・そもそも、何から手をつけて改善して
いけばいいのかわからない。
といったお悩みをお持ちの経営者の方もいらっしゃるでしょう。
そうした場合は、できるだけ早急に対応していくためにも製造物責任法関連に詳しい弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。
弁護士法人みらい総合法律事務所は全国対応で、随時、無料相談を行なっています(事案によりますので、お問い合わせください)。
また、顧問弁護士についてのご相談もいつでもお受けしていますので、まずは一度、気軽にご連絡ください。