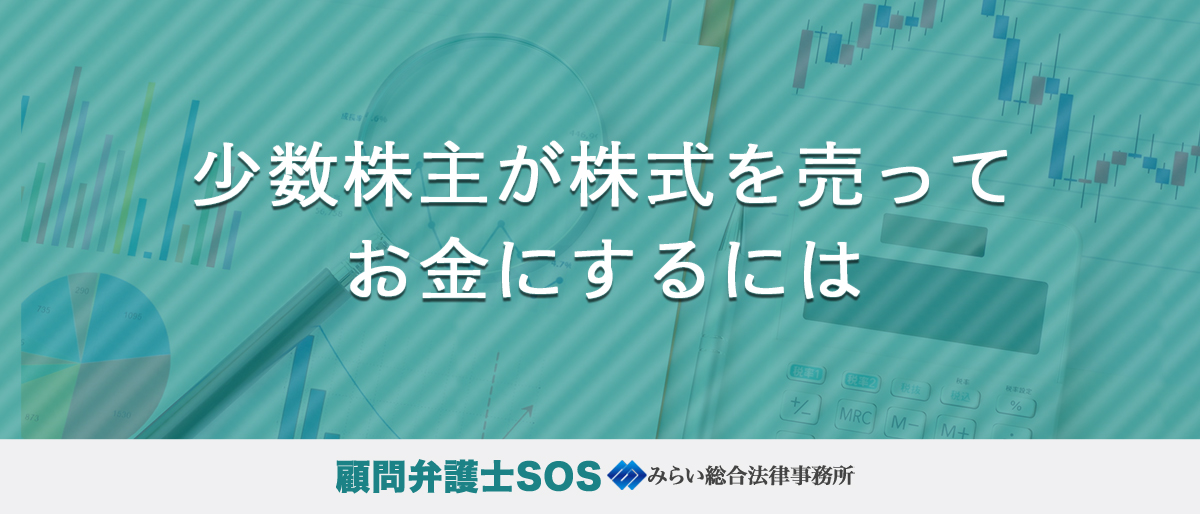少数株主が株式を売ってお金にするには
少数株主の場合、親族経営などの非上場企業の株式を持っていても、メリットがないことがほとんであり、むしろ、デメリットのほうが大きいかもしれません。
配当はつかない場合がほとんどですし、株式を相続した場合は相続税がかかります。
できれば売却したいけれど、譲渡制限がかけられていることが多く、会社が買い取ってくれないなど、なかなか難しい現実に直面している方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、「反対株主の株式買取請求」や「譲渡制限株式の買取請求制度」などを解説しながら、非上場企業の少数株主の方が、株式を売却して現金化する方法について解説していきます。
せっかくの財産ですから、この機会に現金化する方法を知っていただきたいと思います。
目次
非上場企業の少数株式を持つことはリスクになる!?
非上場企業の少数株主から
寄せられるお悩みとは?
買った時よりも大きく値下がりしてしまい、売るに売れなくなって長期保有している株式を「塩漬け株」などといいます。
ところで、売るに売れない株式というと、非上場企業の少数株式を保有していて困っている方もいらっしゃるでしょう。
「父親が設立した会社の株式を10%持っているが、兄が2代目社長をしており、自分は役員でもないし、配当金ももらえない。この株式、売却できないだろうか?」
「若い時に夫と創業した家族経営の会社の株式を49%保有しているが(夫の株式は51%)、離婚することになったので会社とも縁を切って、保有株を現金化したいのだけれど……」
「祖父が創業した会社を引き継いで経営していた父が亡くなり、会社の株式を5%相続したが、自分は経営には関わっていないので必要もない。ところが相続税がかかることを知って、どうすればいいのかわからず困っている」
当法律事務所では、このようなご相談を受けることがあるのですが、じつは非上場企業の少数株式は売却するのが難しいという現実があります。
非上場企業の少数株主とは?
中小企業庁が2023(令和5)年に公表したデータによると、2021年時点での日本の企業数は、中小企業が336.5万社(うち小規模事業者は、285.3万社)、大企業が1万社強で、合計約337.5万社となっています。
【参考資料】:中小企業・小規模事業者の数
(2021年6月時点)の集計結果を公表します
(中小企業庁)
数字から見ていくと、およそ99.7%が非上場企業になり、親族経営の中小企業などのほとんどは非上場企業ということになります。
非上場株式とは、株式公開をしていないために株式市場での取引価格が形成されていない株式のことです。
非上場企業の多くは、経営に支配力を持つ「支配株主(大株主)」と、それ以外の「少数株主」から構成されています。
一般的に、少数株主とは過半数未満(数%から50%未満)の株式しか保有していない株主のことです。
非上場企業の少数株主が抱えるリスクと問題点とは?
ある相談者の方は、亡くなった親から非上場企業の少数株式を相続し、当初はよろこんでいたといいます。
ところが、次々に不都合な事実を知って愕然としました。
そこには、非上場企業の少数株主が直面するリスクがあるからです。
非上場企業の少数株式の売却はハードルが高い
多くの中小企業では、株式を第三者に譲渡する際に譲渡制限がかけられているため売却が難しい。
非上場企業の株式の買い手を探すのは難しい。
高額な相続税を支払わなければいけない
株式を相続した場合も相続税が課される。
特に、株式評価額が高額な場合は、相続税も高額になってしまう。
株式を持っていても配当を
得られるわけではない
多くの非上場企業では、少数株主のための経営が行なわれていない(支配株主が賛成しない)ため、配当などの利益還元も行なわれない。
配当を増やすには株式の過半数を持っている必要(株主総会における議決権の過半数の賛成が必要)があるため(会社法第454条第1項)、少数株主は配当を増やすよう会社に請求することが難しい。
非上場企業の少数株式が
売却しにくい理由とは?
株主としては、自分が希望する時に、できるだけ高額で、会社が株式を買い取ってくれることを望むでしょう。
しかし、非上場企業の少数株主の場合、そうはいかない現実があるのですが、それはなぜなのでしょうか?
少数株主には株式買取請求権がない!?
「株式買取請求権」とは、株式発行会社に対し、株主が自己の保有する株式を公正な価格で買い取るように請求する権利のことです。
しかし法律上、非上場会社の少数株式を保有しているだけでは、少数株主は会社(支配株主)に対して株式の買取請求を行なうことはできないし、自由に第三者に株式を譲渡することもできないことがほとんどです。
なぜかというと、つねに株式自由譲渡や株主から会社への株式買取請求が認められてしまうと、
- ・会社の資本が流出して財政基盤が脅かされてしまう
- ・会社にとって好ましくない人物が経営に関与することになってしまう
- ・株式の保有関係が複雑化してしまう
といったリスクにさらされてしまうからです。
こうした事態を防ぐため、多くの非上場中小企業では、「株式を第三者に譲渡するには会社の承認を得なければならない」という決まりを会社の定款に定めています(会社法2条17号)。
※ただし、少数株主による株式買取請求権の行使が認められるケースがあるので、後ほど詳しく解説します。
非上場企業の株式には
売買のための市場がない
少数株主でも、上場企業の場合は株式市場で株式を売却することができます。
しかし、そもそも非上場企業の場合、株式を売買するための市場がないため、非上場株式の売却が難しいのです。
買い手が見つかりにくい
非上場企業の少数株式を保有していも、会社の経営に影響を与えられるわけではなく、また将来的に株式を売却する手段が制限されるなどの理由から、メリットよりリスクのほうが大きいと判断されるケースがほとんどです。
そのため、なかなか買い手が見つからないという現実があります。
非上場企業の少数株主が株式を
売却する方法とは?
じつは法律上、会社側は、株主からの株式の買い取り要求の申し入れに従う義務はありません。
では、非上場企業の少数株主が株式を売却して現金化する方法はあるのでしょうか?
ここでは、
(1)「反対株主の株式買取請求」
(2)「会社による譲渡制限株式の買取り」
(3)「第三者の買い手を見つける」
(4)「交渉による任意売却」
の4つの方法について見ていきます。
反対株主の株式買取請求
反対株主の株式買取請求の
具体例
会社法では、株主に対して株式買取請求権を認めなければ、株主が著しく不利益を受けるおそれがある場合に限り、例外的に株主による株式買取請求権の行使を認めています。
たとえば、会社が事業譲渡などをする場合や、合併・会社分割・株式交換・株式移転・株式交付をする場合など重要な事項を行おうとするとき、これに反対する株主は会社に対して「公正な価格」で株式を買い取るよう請求ができます。
これを「反対株主の株式買取請求」(会社法第469条)というのですが、次に具体的な内容について見ていきましょう。
<事業譲渡等をする場合>
会社が事業譲渡等をする場合、それに反対する株主(反対株主)には、株式買取請求権が認められています。
これは、事業譲渡等を株主の多数決で行なう場合に、保有株式の公正な価格を受け取って会社から退出する機会を反対株主に保障するという趣旨になっています。
なお、「公正な価格」は原則として協議で決めることとされています。
合意に至らない場合は、裁判所に価格決定の申立てをして、決めてもらうことができます(会社法第470条第2項)。
なお、例外的に次のようなケースでは株式買取請求権が認められません。
- ・事業の全部譲渡の際に、譲渡承認決議と同時に会社の解散を決議した場合
- ・簡易の事業譲受の場合(譲受会社の既存株主に与える影響が軽微なため) など
<合併・会社分割・株式交換・株式移転・
株式交付をする場合>
合併や会社分割等の組織再編に反対する株主に対しては、保有している株式を公正な価格で会社に買い取ってもらい、会社から退出する機会を確保・保障するために、株式買取請求権が認められています。
- ・株主が受け取る合併対価が「持分等」で
ある場合 - ・簡易組織再編に該当する場合
<株式の併合をする場合>
複数の株式を合体させることを「株式の併合」といい(会社法第180条)、会社が少数派株主の追い出し(キャッシュ・アウト)を目的に行なう場合があります。
株式の併合は、株主の利益や地位に大きな影響を与えるため、株主を保護するために株式併合に反対する株主に対して、株式買取請求権が認められています(会社法第182条の4)。
<その他の場合>
- ・株式に全部取得条項を付す場合
- ・種類株主に損害をおよぼすおそれがある場合
- ・単元未満株主が株式買取請求をする場合
- ・株式に譲渡制限を課す場合 など
いずれの場合も、法的知識がないと難しいため、会社法などに精通した弁護士に相談されることをおすすめします。
反対株主の株式買取請求権の
行使手続きについて
<反対株主になる手続き>
反対株主による株式買取請求権を行使するには、「反対株主」となる必要があります。
そのためには、次の手続きが必要です。
- ・株主総会に先立って当該総会決議事項に反対する旨を会社に対して通知
- ・当該株主総会で実際に反対の議決権を
行使する
※なお、議決権を行使できない株主は、特別の手続をとることなく反対株主になることができます(会社法第116条第2項1号ロ)。
<株式買取請求権の行使の手続き>
会社に対する株式買取請求権の行使では、次の点を確認してください。
- ・前述の各行為の効力発生日の20日前から効力発生日の前日までに会社に対して行使します。
- ・行使する株式買取請求に係る株式の数(種類株式の場合は種類と種類ごとの数)を明示する必要があります(会社法第116条第5項)。
- ・株券発行会社の場合は、株券の提出も必要です(会社法第116条第6項)。
なお一度、株式買取請求権を行使すると、その後は会社の同意を得ない限り撤回できないことにも注意が必要です。
非上場株式の買取価格の
決定について
株式買取請求権を行使した後の株式の買取価格については原則、株主と会社の間での協議により決定します(会社法第117条第1項)。
協議がまとまらない、つまり反対株主が株式の買取価格に納得がいかない場合、株主または株式会社は、裁判所に対して価格の決定の申立てをすることができます(会社法第117条第2項)。
ただし、買取価格の決定では争いになる場合が多いといえます。
非上場株式の場合は市場価格が存在しないため、株式評価の基準となるデータがありません。そこで、おもに使われる評価手法としては、まず、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)があります。
DCF法は、会社の将来の収益力(キャッシュフロー)を予測、投資のリスクを反映させた一定の割引率で割り引いて会社の現存価値を算出、さらに現存価値から会社の負債額を控除して株式価格を算出する方法で、実際の裁判でも用いられています。
その他にも、「類似会社比準法」、「配当還元法」、「収益還元法」、「純資産価額法」などの評価手法がありますが、実際の算定では、弁護士や公認会計士などの専門家と相談しながら進めていくのがいいでしょう。
会社による譲渡制限株式の
買取り
会社法では、「株主は、その有する株式を譲渡することができる。」と定めています(会社法第127条)。
同時に、会社は「株式を第三者に譲渡する場合は会社の承認を得なければならない」といった決まりを定款に定めることができます(会社法第2条17号)。
多くの非上場の中小企業では、第三者が株主として自由に参入してくることを防ぐため、譲渡制限をかけています。
しかし会社法では、会社が「譲渡制限株式」の第三者への譲渡を承認しない場合には、会社自らその株式を買い取るか、会社が指定する買取人(参入してきても問題ない者など)を譲受人にすることができるとしています(会社法第140条)。
これを「譲渡制限株式の買取請求制度」といいます。
買取請求後、会社が買い取る場合は、「譲渡承認の請求」の不承認が通知されてから40日以内に買取を通知する必要があります。
会社が指定した買取人が買い取る場合は、同様に「譲渡承認の請求」の不承認が通知されてから10日以内に買取を通知する必要があります。
価格の協議が折り合わない場合は、裁判所に対して売買価格の決定を請求することができます。
第三者の買い手を見つける
会社等が少数株式の買い取りをしない場合、少数株主は自ら買い手を探す必要があります。
買い手が見つかった場合、少数株主は会社に対して当該買い手への株式譲渡を承認するように譲渡制限株式の「譲渡承認の請求」をします。
会社は、少数株主に対して2週間以内に承認、あるいは不承認の通知を出す必要があります。
会社が通知をしなかった場合は、譲渡が承認されたとみなしてよいこととされています。
会社が株式の譲渡を承認した場合は、買い手との間で株式の売買手続きを進めていくことになります。
交渉による任意売却
そもそも、法律上の株式買取請求権によらず、株主と会社、あるいは株主同士で株式の売買交渉をすることも可能です。
会社側としても、株式を集約したい事情があるケースもあります。
たとえば、M&Aで会社を売却する場合、買い手企業やファンドからは全株式を求められる場合が多いでしょう。
また、事業承継を考えた場合、少数株主がいると将来的な紛争の種になる可能性があります。
役員や株主同士の仲違いなどの紛争があり、少数株主に会社から退場してもらいたいケースなどでは、会社が株式買取りの交渉を行なってくる場合もあります。
こうした状況などを上手に活用することも重要です。
たとえば、会社がM&Aにより会社を譲渡(売却)する場合、そこで決定された株式の買取価格で交渉することができます。
もちろん任意の交渉ですから交渉がまとまらない可能性もありますが、法的な手続きのための労力、時間、費用などを削減できるといったメリットもあります。
非上場企業の少数株式の売却は
弁護士に相談・依頼してください!
ここまで、非上場企業の少数株主の方が株の売却をする場合の手続きや注意ポイントなどについてお話ししてきました。
法的知識がない、時間と労力が足りないなど、ご自身が単独で行なっていくには、なかなかに難しい手続きだと感じた方もいらっしゃるでしょう。
その場合は、ぜひ会社法に精通した弁護士に相談・依頼されることを強くおすすめします。
法律と交渉の専門家である弁護士なら、依頼者の利益を最優先に考えながら、段取り、交渉を進めていくことができます。
弁護士法人みらい総合法律事務所では、依頼者の経済的な負担を少しでも軽減するためにも、まずは無料相談の利用をおすすめしています(※随時開催していますが、事案によるので、お問い合わせください)。
この弁護士なら「信頼できる」、「任せたい」と判断されたら正式に依頼をしていただく、という流れで問題ありません。
少数株式の売却でお困りの時は一人で悩まず、まずは一度、ご連絡ください。