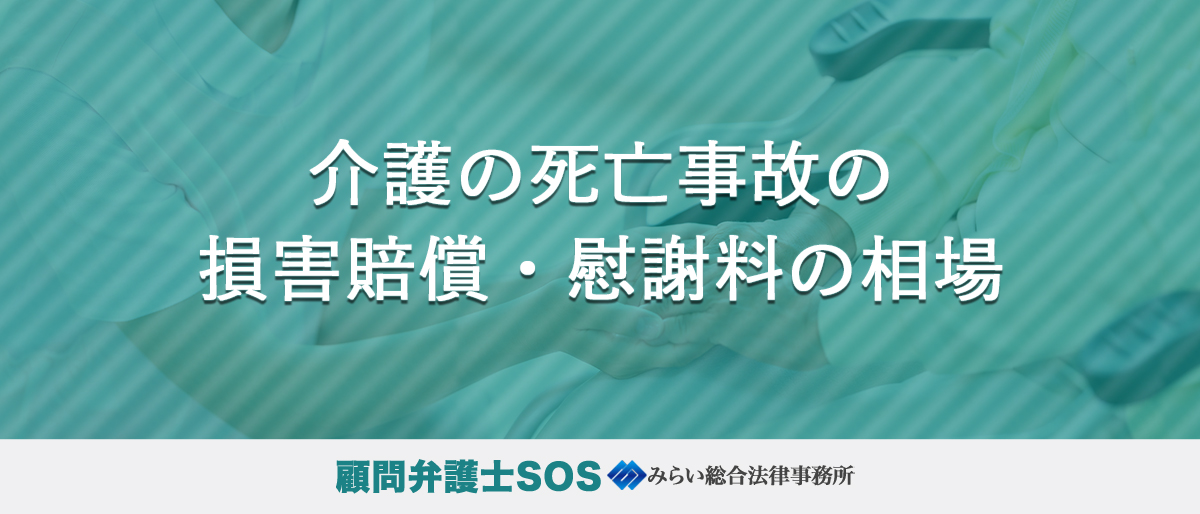介護の死亡事故の損害賠償・慰謝料の相場
超少子高齢化社会の日本では、介護施設への需要がますます高まっています。
ただし、ここで問題なのが、比例して介護事故の発生件数も年々増加傾向にあり、一定の割合で介護施設での死亡事故が起きている、という見過ごすことのできない事実もあることです。
大切なご家族を亡くされたご遺族の中には、介護施設に対して慰謝料などの損害賠償請求を検討されている方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、介護施設に対する損害賠償請求について、次の内容を中心にお話ししていきます。
ぜひ最後まで読んでいただき、正しい知識を手に入れ、準備を進めていただきたいと思います。
目次
介護事故とは?
介護事故とは、介護の現場で発生する事故のことで、死亡事故につながるケースとしては、おもに次のものがあります。
①転倒・転落事故
転倒・転落事故は、歩行中、浴室やトイレの利用時、ベッドや車いすからの移動時などに起きることが多いもので、介護事故では最も多いケースです。
死亡事故の事例としては、施設の上階から転落したといったケースも報告されています。
②誤嚥・誤飲事故
飲食時に、誤って食物や水分が喉頭と気管に入ってしまう状態を誤嚥といいます。
特に高齢者の誤嚥は窒息や肺炎の原因になり、死亡に至るケースもあるため注意が必要です。
③送迎時の交通事故
過去には、送迎車の走行中における死亡事故も発生しています。
④徘徊・無断外出
徘徊行動により、線路内に侵入して鉄道事故にあった事例や川に転落した死亡事故の事例、また行方不明になるケースも報告されています。
⑤感染症・食中毒
近年のコロナウイルスなどによる感染症での死亡事例も発生しています。
⑥褥瘡(じょくそう)
⑦火災
⑧虐待
⑨職員の違法行為・不祥事 など
その他、職員による虐待行為などの事例も報告されており、全体的に死亡事故は増加傾向にあります。
なお、厚生労働省の統計上、介護事故の発生件数や死亡者数は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設で多い傾向があります。
【参考資料】:高齢者の不慮の事故(消費者庁)
介護死亡事故の損害賠償請求と
慰謝料の関係について
次に、損害賠償請求や慰謝料に関して、まずは知っておくべき知識について見ていきましょう。
損害賠償金・示談金・慰謝料の違いとは?
介護死亡事故が起きた場合に、ご遺族が介護施設等に対して損害賠償請求した際、問題になるものに損害賠償金・示談金・慰謝料があります。
ところで、これらは何がどう違うのか、それとも同じものなのか、ご存知でしょうか?
- ・損害賠償金:被害者側から見た場合、被った損害をお金で賠償してもらうものの総額
- ・示談金:被害者側と加害者側の間で示談によって損害金額が合意されるもの
- ・慰謝料:多数ある損害賠償項目の1つで、被害者の方の精神的苦痛や損害に対して支払われるもの
損害賠償金と示談金は、立場や視点の違いなどによって呼び方が違うだけで、じつは同じもの。
慰謝料は、さまざまある損害賠償項目のうちの1つであり、各損害賠償項目の金額を合計したものが損害賠償金ということになります。
慰謝料は1つではないという
事実
慰謝料というのは1つではなく、大きくは4種類あることを知っておいてください。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
被害者の方が、ケガの治療のために入通院した場合の精神的苦痛や損害に対して支払われる慰謝料。
後遺障害慰謝料
(後遺症慰謝料)
被害者の方のケガが完治せず後遺障害が残ってしまった場合に支払われる慰謝料。
死亡慰謝料
被害者の方が死亡した場合の精神的苦痛・損害に対して支払われる慰謝料。
近親者慰謝料
被害者の方の近親者(家族など)が被った精神的苦痛・損害に対して支払われる慰謝料。
ご家族が亡くなった場合や、重度の後遺障害が残り将来に渡った介護が必要な場合などに認められる。
介護死亡事故で受け取ることができる損害賠償項目一覧
では介護事故に限らず、損害賠償項目にはどういったものがあるのか、順番に確認していきましょう。
積極損害
被害者の方が現実に支払った、または支払いを余儀なくされた金銭的損害を積極損害といいます。
- ・治療費
- ・付添介護費
- ・将来介護費
- ・入院雑費
- ・将来雑費
- ・通院交通費
- ・葬儀関係費
- ・損害賠償請求関係費用
- ・弁護士費用 など
消極損害
事故が起きなければ、将来的に得ることができたであろう収入などの損害を消極損害といいます。
- ・休業損害
- ・死亡逸失利益 など
※逸失利益:事故にあわずに生きていれば得られたはずだった収入(利益)。
【参考資料】:交通死亡事故で高額の逸失利益を
獲得した5つの事例
慰謝料
被害者の方が治療後に亡くなった場合は、入通院慰謝料と死亡慰謝料を受け取ることができます。
ご遺族の精神的な苦痛が大きいと判断された場合は、近親者慰謝料が認められる可能性があります。
慰謝料額は被害者の方の家庭内での立場や状況によって、概ねの相場金額が決まっています。
被害者の方は亡くなっているため、受取人はご遺族(相続人)になります。
介護死亡事故で慰謝料請求するには条件がある
安全配慮義務違反とは?
介護施設で起きた事故であれば、すべてのケースで慰謝料などの損害賠償請求ができる、というわけではありません。
事業者に「安全配慮義務違反」が認められるなら、法的な責任を果たしていないとして「債務不履行責任」(民法415条)に基づいて、慰謝料などの請求をすることが可能です。
たとえば、足腰が弱っていて以前から転倒することがあった利用者や、嚥下機能が低下して誤嚥をしていた利用者に対して、事業者が適正な見守りをつけていなかったことで死亡事故が起きた場合は損害賠償責任を負う場合があるわけです。
「予見可能性」と
「結果回避可能性」がポイント
この点、安全配慮義務違反については、介護死亡事故の発生に「予見可能性」と「結果回避可能性」があったかどうかが検討されます。
予見可能性とは、施設側で事故が発生することを予見できた可能性です。
そして、事故の発生を予見できた場合は、結果=事故を回避できたかどうかが問われるわけです。
そのため、たとえばこれまで誤嚥をしたことがなかった利用者の事故などでは、介護施設側の法的責任を問えるかどうかについて慎重な判断が必要になってきます。
誰が慰謝料を請求することが
できるのか?
慰謝料を請求できるのは相続人
もう一点、介護事故の慰謝料は誰が請求できるのかについても知っておくべきです。
じつは誰でも請求できるわけではなく、次の人が法的に請求できることになります。
- ・被害者本人
- ・相続人
死亡事故の場合、被害者ご本人は亡くなっていますから、相続人は誰なのか? がポイントになるわけです。
相続人と相続順位と法定相続分について
配偶者は、つねに相続人になります。
このポイントは、抑えておいてください。
その他の相続人には、法的に相続順位と法定相続分が定められています。
「相続人順位第1位:子」
・子がすでに死亡している場合、子の子ども、つまり被害者の方の孫が相続人順位第1位になります。
・法定相続分は、配偶者と子それぞれが2分の1を相続します。
たとえば、子が2人いる場合は、2分の1を2人で分けるので、それぞれ4分の1ずつになります。
「相続人順位第2位:親」
・被害者の方に子がいない場合、親が相続人になります。
・法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1になります。
「相続人順位第3位:兄弟姉妹」
・被害者の方に子も親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
・兄弟姉妹が死亡している場合、兄弟姉妹の子が同順位で相続人になります。
・法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。
死亡事故の慰謝料と損害賠償金額について
慰謝料の相場金額はいくら?
介護事故の慰謝料の相場金額については、一律にいくらと決まっているわけではありません。
基本的には、事故の類型や損害の程度などによって、過去の判例を参考にしながら算出することになります。
その際、交通事故の慰謝料算定基準(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準)を用いることも多いので、詳しい内容については、こちらの記事を参考にされるといいでしょう。
・人身事故の慰謝料と示談金の相場
高齢者の死亡慰謝料については、およそ1,000~2,000万円が相場金額になっています。
また、ご遺族の近親者慰謝料は100万円ほどが認められる可能性があるでしょう。
損害賠償金の項目と内訳に
ついて
介護死亡事故で、ご遺族が請求できるおもな項目には次のものがあります。
- ①死亡慰謝料
- ②近親者慰謝料
- ③死亡逸失利益(年金分)
- ④葬儀費用(葬儀代・法要費用・墓石建立費用など)
ここで知っておいていただきたいのは、介護死亡事故の場合、被害者の方が高齢であったり、体調が悪い場合もあり、その分を差し引いて損害賠償金が減額される傾向があることです。
そうしたことも考慮すると、損害賠償金の合計はおおむね1,500万円以上、交通死亡事故の場合は2,000万円以上、と考えておくといいでしょう。
・死亡事故で遺族が受け取れるお金のまとめ
介護事業社側に死亡事故の責任があると認められた場合、慰謝料などの損害賠償金を請求できますが、被害者側にも過失があった場合はその程度に応じて減額されることがあり、これを「過失相殺」といいます。
示談交渉では、介護事業社側が被害者の方の過失を主張してくることがあり、そうすると示談交渉が長引き、最終的には決裂、裁判へという流れもあります。
相手方から過失相殺を主張された場合は、死亡事故の原因究明も含め、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
介護死亡事故の慰謝料請求の方法を解説
ご遺族が慰謝料請求をして損害賠償金を受け取るには、「示談」「調停」「裁判」という方法があります。
示談
まずは、事業者側とご遺族側で話し合いを行ないます。
これを示談交渉といいますが、金額の折り合いがつき、交渉が上手く進んで合意となれば示談成立、その後に示談書を取り交わすという流れになります。
示談によって解決できれば、当事者としては金額的にも時間的にも負担が少なくて済みます。
しかし、当事者同士が話し合っても合意に至らないケースも多いのが現実です。
調停
示談交渉が決裂した場合は、調停に進むことができます。
簡単にいうと、調停とは簡易裁判所で調停委員に間に入ってもらい、話し合いを行なうものです。
忘れてはいけないのは、調停はあくまで話し合いであることです。
そのため、お互いに納得がいかなければ調停も不成立ということになります。
一般的には、ここまでに話し合ったにもかかわらず決着がつかなかったという流れがあるため、示談決裂後は調停手続は取らず、すぐに訴訟を提起することが多いといえます。
裁判
示談交渉や調停が決裂した場合は、民事での裁判で決着を図ることになります。
裁判となれば、双方が弁護士を代理人に立てて進めていくので、ご遺族が思っているほど負担が大きく、大変なものではないといえます。
・交通事故の示談交渉が決裂後の調停・裁判の手続きを解説
介護死亡事故の判例
高齢化が進む現在、介護事故の訴訟は増加しており、今後もさらに増えていく可能性があります。
ここでは、介護死亡事故の裁判例を紹介します。
①特別養護老人ホーム内で転倒後に死亡した96歳女性の判例
2009(平成21)年、福岡県北九州市の特別養護老人ホーム施設の短期入所サービスを利用していた当時96歳の女性が、共同生活室から個室に移動する際に転倒し、胸部を強打。
胸椎骨折などと診断され、2か月後に死亡したため、遺族が社会福祉法人に1,200万円の損害賠償を求めて提訴した。
法人側は「転倒事故は予見不可能だった」などと主張したが、2014年、福岡地裁小倉支部は「安全配慮義務を怠った」と法人側の過失を認定。
「女性はいつ転倒してもおかしくない状態だった」と指摘し、職員が歩行を介助したり、見守ったりしていれば、事故を防止できたとして、事故と死亡との因果関係も認めた。
判決では、480万円の支払いが命じられた。
(福岡地裁小倉支部平成26年10月10日判決)
②特別養護老人ホームで食べ物を喉につまらせて死亡した81歳女性の判例
2019年、愛知県春日井市の特別養護老人ホームに入居していた当時81歳の認知症の女性が、食事中に食べ物を喉につまらせて心肺停止状態となり、その後、窒息死した事例。
遺族が施設側に、計約3,550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2023年に名古屋地裁であり、裁判所は施設側の注意義務違反を認定し、計約1,370万円の支払いを命じた。
判決では、女性は以前から食事をかき込んで食べ、たびたび嘔吐していたことから、「吐いた食べ物で窒息する危険性を予見できた」と指摘。
女性が食事する際は職員が常に見守るべきだったのに、目を離した結果、女性が死亡したと認定した。
(名古屋地裁令和5年2月28日判決)
介護死亡事故の慰謝料額は弁護士で変わる!
ここまで、介護死亡事故での慰謝料など損害賠償請求について解説してきました。
実際に介護施設側と示談交渉を行ない、決裂した場合は裁判にまで進むことを考えているのであれば、弁護士に相談・依頼することを検討してください。
弁護士に依頼するメリット①
慰謝料が増額する可能性
前述したように、介護死亡事故の慰謝料など損害賠償金には算定基準はありますが、法的に一律に決まった金額があるわけではありません。
ということは、弁護士に依頼して、確かな法的根拠を用意して示談交渉を行なうことで、慰謝料などの損害賠償金額が増額する可能性が大きくなるということです。
また、介護事故や交通事故に精通した弁護士に依頼することで、慰謝料などの損害賠償金がさらに増額する可能性も高まります。
つまり、依頼した弁護士によって金額が低くも高くもなる、という事実を忘れないでいただきたいと思います。
弁護士に依頼するメリット②
示談交渉のストレスから
解放される
弁護士に代理人をまかせることで、ご遺族自身が直接、示談交渉や裁判手続きを行なわなくて済むようになります。
つまり、弁護士に依頼することでストレスやプレッシャーなどから解放され、仕事に集中でき、安心して日常生活を送ることができるのです。
弁護士法人みらい総合法律事務所では、いつでも無料相談を行なっています。
(※事案によるので、まずはお問い合わせください。)
介護事故に関わる問題は他人事ではありません。
一人で悩まないでください。
まずは一度、気軽にご連絡いただければと思います。