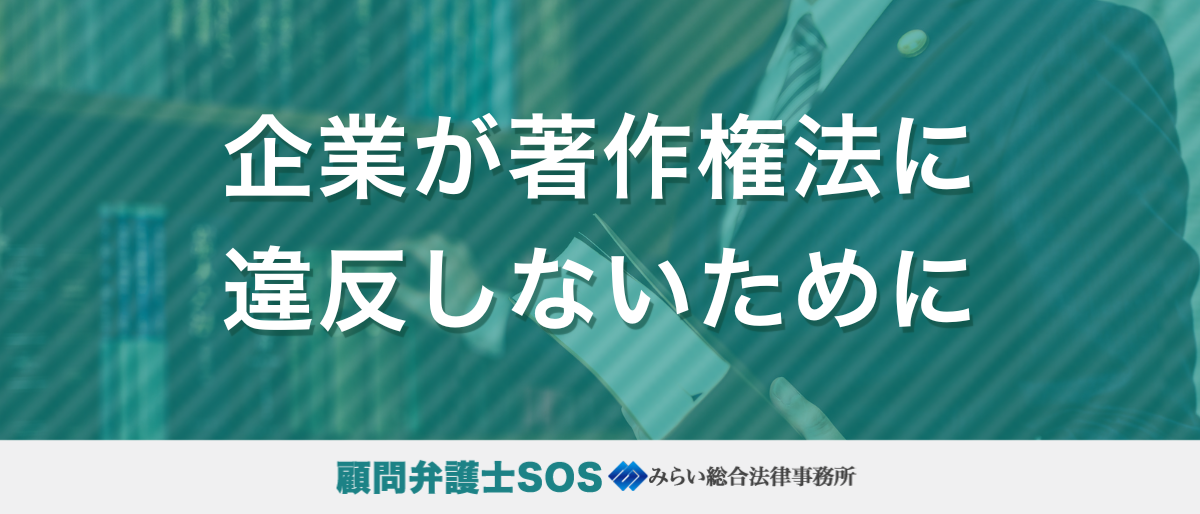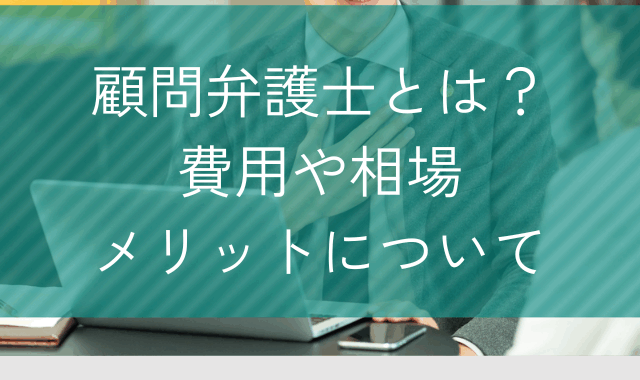企業が著作権法に違反しないために|基礎知識
私たちの日常生活や企業活動にとって身近なのに、じつは意外とわかっていない法律に「著作権」があります。
著作者に無断で著作物を使用すると、著作権侵害により「10年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金」に処され、会社にも「3億円以下の罰金」が科される可能性があります。
著作権について知っておかないと、知らないうちに著作権侵害を侵してしまう可能性が高いといえます。
- ネットや雑誌などで見つけた写真や
イラストを自社のウェブサイトや
パンフレットに無断で掲載。 - YouTubeで見つけた
他社のプロモーション動画を
一部切り取って自社SNSで投稿。 - 人気の楽曲をBGMとして使用し、YouTubeにアップロード。
- 漫画や小説を「紹介」といいながら、
ほぼ全文投稿。 など
しかし、著作権には「複製権」、「上演権」、「公衆送信権」などさまざまな種類があり、知らないでいると、リスクを抱えてしまうことになりかねません。
そこで本記事では、
- 著作権の概要と種類
- 著作権侵害になるケースと
ならないケース - 著作権侵害で注意するべきポイント
- 企業が直面する法的リスク
- 著作権侵害を回避するために大切なこと
- 著作権侵害で訴えられた時に
やるべきこと
などについて詳しく解説していきます。
目次
著作権に関する基礎知識を再確認
著作権とは?
著作権(コピーライト)とは、著作物を創作したことにより、著作者に発生する権利のことです。
「創作物を創った人 = 著作者が持つ権利」で、「創作した作品を無断で利用されないように保護するもの」であり、「作品がどう使われるか著作権者が決めることができる権利」が著作権ということになります。
第1条(目的)
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
著作権で保護された創作物を、著作者以外が無断で使用することは、著作権法違反になり、刑事罰を科される可能性があります。
著作権は知的財産権の一つとなります。
知的財産権は、①産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権など)と、②著作権に分けることができます。
【参考資料】:知的財産権について(特許庁)
著作権には存続期間が定められています。
- 著作権の存続期間は、著作者の死後70年(第51条)。
- 無名または変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後70年(第52条)。
※ただし、その存続期間の満了前に著作者の死後70年を経過していると認められる場合は、その著作者の死後70年を経過したと認められる時において消滅する。 - 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後70年(第53条)。
※ただし、その著作物が創作後70年以内に公表されなかった時は、その創作後70年。 - 映画の著作権は、公表後70年
(第54条)。
ただし、その著作物が創作後70年以内に公表されなかった時は、その創作後70年。
著作物の定義
著作物について、著作権法では次のように定義されています。
「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、または音楽の範囲に属するものをいう」(第2条1項1号)
著作物の種類
文章、音楽、写真、動画、プログラム、デザインなど、さまざまな表現による創作物が著作権の対象になります。
著作物の種類としては、次のものなどがあげられます(第10条1項)。
- 「言語の著作物」
講演、論文、レポート、作文、小説、脚本など。 - 「美術の著作物」
絵画、版画、彫刻、漫画、書など。 - 「音楽の著作物」
楽曲、楽曲を伴う歌詞など。 - 「映画の著作物」
劇場用映画、アニメ、ビデオ、ゲームソフトなど。 - 「写真の著作物」
写真、グラビアなど。 - 「プログラムの著作物」
コンピュータプログラムなど。 - 「舞踊・無言劇の著作物」
バレエ、ダンス、舞踏、パントマイムの振り付けなど。 - 「建築の著作物」
芸術的な建築など。 - 「地図・図形の著作物」
地図、学術的な図面、図表、設計図、立体模型など。
これらの創作物が著作物として認められるには、著作者本人の思想や感情が表現されていればよく、プロか素人か、有名か無名か、上手いか下手かといったことは関係ありません。
なお、その他の特殊な著作物として次のものが規定されています。
- 「二次的著作物」(第2条1項11号)
著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・映画化、翻案することで創作した著作物。 - 「編集著作物」(第12条)
編集物で、その素材の選択や配列によって創作性を有するもの。
たとえば、百科事典、新聞紙面の構成、ウェブサイトのデザインなど。 - 「データベースの著作物」(第12条の2)
データベースで、その情報の選択または体系的な構成によって創作性を有するもの。
例としては、顧客データベースや文献データベースなどがあげられます。
著作物に該当しないものとは?
一方、次のものは著作物にはならないとされます。
- 事実の伝達にすぎない雑報および
時事の報道(第10条2項)。 - プログラミング言語や
規約(プロトコル)、
解法(アルゴリズム)(第10条3項)。
知っておくべき著作権の種類について
著作者が有する著作権には、さまざまな種類がありますが、大きくは次の2つに分類されます。
著作物を活用して収益や名声などを得ることができる財産的権利。
通常の著作権は、この財産権のことを指します。
<著作者人格権>
著作物の内容と著作者を紐づけることで、著作者の人間性を正確に表現する人格的権利。
ここでは、著作財産権について主なものをピックアップして解説します。
複製権(第21条)
印刷、写真、複写、録音、録画、その他の方法により有形的に再製することを複製といい(第2条1項15号)、著作物の典型的な利用形態になります。
複製権とは、著作者だけが、その著作物を複製する権利を有していることを規定したものです。
そのため、たとえば新聞記事をコピーしたり、ネット記事をプリントアウトして社内に配布する、インターネット上で取得した写真を載せた社内報を社内に配布する、などの行為は複製権の侵害となります。
上演権・演奏権(第22条)
「演奏」は音楽を、「上演」は音楽以外の著作物を演ずることをいいます(第2条1項16号)。
著作物を録音、録画したものを再生することも上演に含まれます。
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ、または聞かせることを目的として上演、演奏、歌唱する権利を専有することを規定したものです。
なお、公衆というのは不特定もしくは多数を意味します。
そのため、公衆になり得る状況には注意が必要です。
たとえば、結婚式や葬儀でBGMとして曲を流せば、演奏権の侵害になる可能性があります。
上映権(第22条の2)
著作物(公衆送信=インターネット配信などされるものを除く)を映写幕その他の物に映写することを上映といいます(第2条1項17号)。
映画の著作物の音を再生することも含まれます。
上映権は、著作物を公に上映する権利ですから、たとえば会社などで著作者以外が映画やスライド資料などをスクリーンやモニターに映すことは上映権の侵害になります。
公衆送信権(第23条1項)
公衆送信権とは、著作者がその著作物について、公衆送信を行なう権利をいいます。
公衆送信(第2条1項7号の2)は、放送・有線放送・自動公衆送信と、その他に分類されます。
このうち「自動公衆送信」とは、公衆からの求めに応じて自動的に行なう公衆送信(放送・有線放送を除く)をいい(同項9号の4)、送信可能化が含まれます(法23条1項括弧書)。
送信可能化(同項9号の5)とは、インターネットに接続されているサーバー上にデータをアップロードすることをいいます。
そのため、たとえば他人の著作物を自社のウェブサイトに無断で掲載したり、メルマガに掲載して発信したりする行為は公衆送信権の侵害となる可能性があります。
公衆伝達権(第23条2項)
公衆伝達権とは、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公衆に伝達する権利をいいます(第23条2項)。
たとえば、テレビやラジオなどで放送された番組を会社などで、そのままスピーカーで流して従業員に聞かせるなどの行為は公衆伝達権の侵害となる可能性があります。
口述権(第24条)
著作者が、言語著作物を公に口述する権利を口述権といいます。
口述とは、朗読やその他の方法で著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く)をいうため(第2条1項18号)、小説や詩などを無断で朗読するのは法的に禁止された行為になります。
展示権(第25条)
著作者が、美術の著作物、またはまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利です。
ギャラリーやオフィスなどの施設で開催する展覧会などでの展示が該当します。
頒布権(第26条)
著作者が、映画の著作物の複製物を、有償無償を問わず頒布(はんぷ:公衆に譲渡や貸与)する権利です(第2条1項19号)。
映画DVDの販売やレンタルなどが該当します。
譲渡権(第26条の2)
著作物(映画を除く)の原作品や複製物を、著作者が譲渡により公衆に提供する権利です。
ソフトウエアのライセンス(使用許諾)販売などが該当します。
貸与権(第26条の3)
著作物(映画を除く)の複製物を、著作者が公衆に貸与する(貸し出す)権利です。
レンタルショップでのDVD(映画除く)やCD、本などの貸し出しが該当します。
翻訳権・翻案権(第27条)
著作者が、著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、翻案(既存の作品を原案・原作として、新たに別の作品を作る行為)する権利です。
漫画原作のアニメ化や、アニメの小説化(ノベライズ)などが該当します。
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(第28条)
翻訳・翻案・脚色などによって作られた二次的著作物については、原著作物の著作者だけでなく、その創作者にも著作権が認められます。
たとえば、著作者Aが創作した小説を原作としてB社がアニメを製作し、さらにC社がこのアニメをコミカライズ(漫画化)する場合、C社は著作者AとB社の両方に許諾を得る必要があります。
著作権以外に注意するべき
権利についても知っておく
著作物の内容や利用方法に深く関わる権利として、次の2つの権利があるので理解しておくといいでしょう。
著作者人格権
前述したように、著作物の内容と著作者を紐づけることで、著作者の人間性を正確に表現する人格的権利として「著作者人格権」があります。
自分が創作した著作物を公表するかしないか決定できる権利。
公表する場合は、“いつ” “どのような方法”で公表するかを決めることができる。
「氏名表示権」(第19条)
自分の著作物を公表する際、著作者名を表示するかしないか決定できる権利。
表示する場合、 実名か変名かを決めることができる。
「同一性保持権」(第20条1項)
自分の著作物のタイトルや内容などを自分の意に反して改変されない権利。
著作隣接権
著作物の創作者ではないが、著作物を公衆に伝達するのに重要な役割を果たしている者(実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者)に与えられる権利です。
【参考資料】:著作隣接権(文化庁)
著作権はいつ発生する?
著作権を取得するには、特許庁への登録や申請などは必要ありません。
著作物が創作された時点で、著作権は発生します。
そのため、日々膨大な著作物が創作されるのと同時に、その一つひとつに著作権が発生していることになります。
著作権侵害になるケース/
ならないケースとは?
著作権侵害が成立するための
5要件について
著作権侵害とは、前述したような著作者が有する著作権(権利や利益)を侵し、損害を与えることです。
著作者の利用許諾を受けずに勝手に著作物を利用すると、著作権侵害になります。
著作権侵害が成立するには、次にあげる5つの要件が必要とされます。
- 著作物である
- 著作権が存在している
- 著作権の効力がおよぶ範囲で
利用されている - 利用者が著作物利用について
正当な権限を有していない - 権利侵害がある
著作権侵害になるケースとは?
会社で起こり得る行為で著作権侵害になるのは、次のようなケースなどが考えられます。
- 新聞や雑誌の記事をコピー、またはインターネットで見つけた記事をプリントアウトして社内で配布。
- 他人の著作物をそのまま複製するのは問題があると考え、文章や写真の一部をカットして加工したものを社内で配布。
- 新聞や雑誌の記事を自社のホームページにアップロードしたり、SNSで発信。
- YouTubeで見つけた他社のプロモーション動画を一部切り取って自社SNSで紹介。
- 他社が作成した研修資料を無断で社内研修に使用。
- 漫画のコマや小説の一節を「紹介」と称してほぼ全文投稿。
著作権侵害にならない
(無断利用できる)
ケースとは?
一方、次のように著作者の許諾を得ることなく利用できる場合もあります。
ここでは、日常生活や社会活動の中で頻度が高いと思われるケースをいくつか解説します。
私的利用(著作権法第30条)
著作物を個人的に、または家庭内、あるいはこれに準ずる限られた人間関係の範囲内で複製する場合は、著作者の許諾を得る必要はありません。
【具体例】:CDを購入して、曲をスマホに取り込む。家族で映画を録画して観る。
図書館などでの複製
(同法第31条)
図書館での複製は営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録、その他の資料を用いて著作物を複製することができます。
【具体例】:絶版書籍の保存用コピー。利用者が1部だけ複製する。
引用(同法第32条)
「公正な慣行に合致」し、「引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの」であれば、報道・批評・研究などの目的で、過去の作品や論文から引用する場合は著作者の許諾を得る必要はありません。
ただし、引用部分があまりに多すぎて、自説のほうが少ないようなものは著作権侵害にあたると考えられます。
引用部分は必要最小限にとどめ、出典を明記する必要があります。
【具体例】:ブログなどでニュース記事の一部を引用し、自分の意見を述べる。
教育機関での使用
(同法第35条)
学校、その他の教育機関での授業で使用する場合は著作権者の許諾は必要ありません。
ただし、予備校や学習塾など営利目的の組織での使用の場合、そこで得られた利益の一部は著作者に還元すべきものと考えられるため、無償での無断利用はできません。
【具体例】:教科書からコピーしたものを資料として配布する。動画を授業中に視聴する。
試験問題に使用(同法第36条)
入学試験、その他、人の学識技能に関する試験、または検定の目的上必要と認められる限度での複製では著作権者の許諾は必要ありません。
【具体例】:試験問題に文章をコピーして使用する。
営利を目的としない上演・演奏
(同法第38条)
営利目的でなければ、著作物の上演や演奏、上映が可能です。
【具体例】:地域の文化祭などでの無料上映会、コンサートで演奏。公民館で開催される入場無料の演劇を上演。
著作権の保護期間が
終了した著作物の利用
(同法第51条)
原則として、著作者の死後70年で著作権は消滅します。
【具体例】:夏目漱石の小説を自由に出版。ベートーヴェンの楽曲を演奏。
アイデア・事実・データの利用
著作権は「表現」にのみ適用されるため、アイデアや事実は対象外です。
【具体例】:「未来から来た猫型ロボット」というアイデアを使った創作。発明のアイディアや小説の構想。
フリー素材の利用
利用条件を守れば、著作権者の許諾なしで使用できます。
ただし、企業が商業目的で使用する場合は使用料が発生すると明記しているもの、クレジット表記が必要なもの、商用利用不可のものもあるため、必ず使用条件を確認する必要があります。
【具体例】:無料画像サイトの素材をSNSのアイコンに使用
著作権者が明示的に
許諾している場合
「この作品は自由に使ってください」等と明記されている場合は許諾なしで使用できます。
ただし、著作者人格権にも注意しましょう。
原作者のクレジット(氏名、作品タイトルなど)を表示し、かつ非営利目的であり、元の作品を改変しないことを主な条件に、作品を自由に再配布できる「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス」(CCライセンス)の作品であるかを確認するといいでしょう。
【参考資料】:クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは(Creative Commons Japan)
著作権侵害で注意するべきポイント解説
企業が直面する
法的リスクとは?
前述した、さまざまな著作権を企業が侵害した場合は「著作権侵害」となり、さまざまなリスクを負うことになります。
差止請求を受ける
著作者、著作権者、出版権者、実演家、著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権、著作隣接権を侵害する者、または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止、または予防を請求することができます(第112条1項)
損害賠償請求を受ける
著作権者などは、著作権侵害により自己の受けた損害の賠償を請求することができます(第114条)。
不当利得返還請求を受ける
不当利得を得た人に対して、それによって損失を被った人は利益の返還を求めることができます。
名誉回復等の措置請求を受ける
著作者は、著作者人格権を侵害した者に対して、名誉・声望を回復するための措置を請求することができます(第115条)。
刑事責任の追及を受ける
著作権侵害を行なった者は、原則として10年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金に処され、場合によっては拘禁刑と罰金刑が両方が科される場合もあります(第119条)。
また、会社の従業員や役員が著作権侵害を行なった場合、その処罰に加えて、会社にも3億円以下の罰金が科される可能性があります(第124条)。
著作権侵害を回避するために
知っておくべきこと
著作権等管理事業者を利用する
著作権等を集中的に管理している団体(著作権等管理事業者)がある場合、窓口として利用の了解を得られる場合があります。
著作権等管理事業者については、文化庁のサイトなどを参考にされるといいでしょう。
【参考資料】:著作権に関するお問い合わせ先(文化庁)
なお、著作者が自分の著作物を他人に自由に使ってもらってよいと考えるものを表示するためのマークもあるので参考にしてください。
【参考資料】:自由利用マーク(文化庁)
引用する場合の要件を再確認
他人の著作物を引用する場合、複製権と公衆送信権の侵害になる可能性があります。
著作権侵害にならないためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 1. 引用の必要性があること。
- 2. 引用部分とそれ以外が明瞭に
区別されていること。
引用部分を、「」や太字で表示、または書体を変えるなどして、引用部分とそれ以外の部分が明瞭に区別できるようにします。 - 3. 本文が主、引用部分が
従の関係で
あること。
本文の分量が、引用部分の分量に比べて圧倒的に少ない場合は引用にはなりません。 - 4. 引用部分にオリジナルからの
変更が加えられていないこと。 - 5. 出典(引用元)を表示すること。
著作権者が複数いる場合は?
著作者が2人以上いて、共同創作された作品は「共同著作物」といいます(第2条1項12号)。
各人の創作した部分を分離して利用できないため、全員がその割合に応じて著作権を有することになります。
そのため、著作権者全員に対して使用許諾をとる必要があります。
職務著作とは?
会社の命令により、従業員が職務上作成する著作物を「職務著作」といいます。
会社名義で公表する場合、創作したのは従業員であっても、契約などで定めがない限り、著作者は会社になります。(第15条)。
社内ルールなどを徹底する
著作権侵害を回避するためには、次のように社内でのルールを明確に規定しておくことも必要です。
- 権利確認フローの社内ルール化
- 定期的な社員教育・研修の開催
- 外注契約書で著作権譲渡や利用許諾を
明記
企業が著作権侵害で
訴えられた時の対応について
万が一、著作権侵害で相手から訴えられた場合は次のような対応が必要です。
- 事実関係を速やかに確認
(利用経緯や素材の出所など) - 必要に応じて利用中止、削除
- 弁護士に相談
- 和解、損害賠償交渉の準備と実行
著作権侵害をされた時の
企業の対応策
企業にとっては、著作権侵害をしてしまうことは問題ですが、逆に著作権侵害をされる可能性もあることを忘れてはいけません。
著作権侵害を受けた場合は、次のポイントについて対応する必要があります。
- 侵害の証拠収集
(スクリーンショットなどで
データを保存) - 弁護士を通じて警告書送付
- 必要なら損害賠償請求や仮処分の準備と実行
- 著作権登録制度を利用し立証を強化
【参考資料】:著作権侵害への救済手続(特許庁)
著作権でお困りなら
弁護士にご相談ください!
企業にとって著作権は「守る側」であると同時に「守られる側」でもあります。
日常業務で何気なく使用している写真や文章が思わぬ法的リスクを招くことがあります。
「使う前に確認」、「契約で権利を明確化」、「教育で意識向上」がリスク回避の三本柱です。
しかし……、
「著作権の基本はわかったが、まだ不安がある」
「著作権について社内研修をしたいが、種類や違反事項が多く判断が難しい」
「著作権で訴えられている、できるだけ早急に解決したい」
といった問題に直面しているなら、まずは一度、著作権に精通した弁護士にご相談ください!
弁護士法人みらい総合法律事務所は全国対応で、随時、無料相談を行なっています(事案によりますので、お問い合わせください)。
また、いつでも相談・依頼できる顧問弁護士についてのご質問などもお受けしていますので、一人で悩まず、お気軽にご連絡いただければと思います。