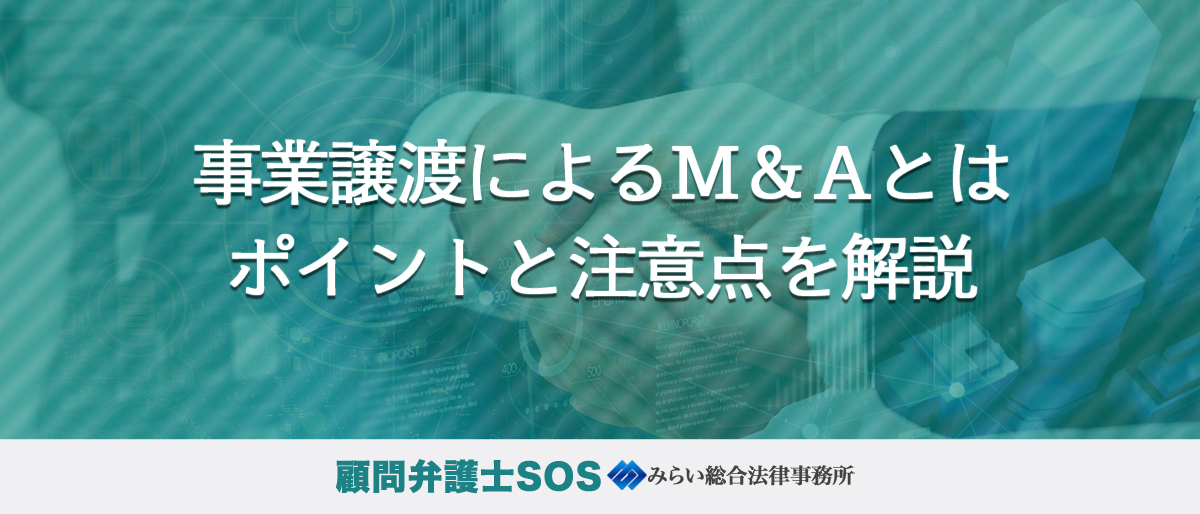事業譲渡によるM&Aとは|ポイントと注意点を解説
本記事では、事業譲渡の実施について、譲渡(売り手)側企業と譲受(買い手)側企業それぞれの立場に立って、次のテーマを中心に解説していきます。
- ・事業譲渡を実施する目的
- ・事業譲渡のメリットと
デメリット - ・事業譲渡と事業承継、M&Aの関係
- ・事業譲渡の手続きと流れ
- ・事業譲渡を実施する場合に注意するべき
ポイント など
企業にとって、事業譲渡は非常に大きく、重大な決断になります。
また、さまざまな法律が関係してくるため、まずは本記事で必要な知識を身につけていただきたいと思います。
本記事では、主に株式会社を対象として解説していきます。
目次
事業譲渡と事業承継、M&Aの関係について
事業譲渡とは?その目的に
ついて
事業の全部、あるいは事業の重要な一部を第三者(他の会社など)に譲渡(売却)することを「事業譲渡」といいます。
そのため、事業売却とも呼ばれます。
関わる法律は「会社法」などで、法的には、「事業譲渡の効力を生ずる日(効力発生日)の前日までに、株主総会の決議によって、事業譲渡に関わる契約の承認を受けなければならない」とされています(会社法第467条1項・2項)。
事業譲渡では、譲渡(売り手)側企業の経営権はそのまま残り、譲渡対象の事業の所有権が譲受(買い手)側企業に移転するため、買い手は譲渡された事業を引き継ぐことになります。
売り手が事業譲渡を行なう理由としては、次のケースがあげられます。
不採算部門を切り離して会社を成長させる
複数の事業を営んでいると、好調な部門と不採算部門が混在することがあると思います。
そうした場合に、不採算部門を切り離して、好調な部門に資源を集中させ、会社を成長させるために事業譲渡を行なうことは有効な手段のひとつになります。
経営を立て直して会社を
存続させる
資金繰りが苦しい場合などでは事業譲渡を行なうことで会社の事業を整理し、得られた対価(売却益)を運転資金に充てることができます。
これにより廃業などを回避でき、会社を存続させて再建を図ることができます。
一方、買い手としては、会社まるごとの買収資金がない場合、ほしい事業のみを引き継ぎたい場合、相手先企業が抱える負債やリスクは引き継ぎたくない場合などで、事業譲渡を有効に活用することができます。
事業承継とは?
事業譲渡に似たものに「事業承継」がありますが、こちらは後継者に会社の株式を贈与などして相続し、事業を引き継ぎ、継続していくことを目的に行なうものです。
事業承継では、株式だけでなく、会社が保有している「人」「資産」「知的資産」なども引き継ぎます。
特に中小企業は、経営者の経営手腕が会社のベースになっており、将来的な業績拡大や会社の存続などを左右します。
そのため、誰を後継者にするかが課題になりますが、基本、子供などの親族承継が多くなっています。
ただし近年では、親族以外の従業員や第三者への事業承継が増加傾向にあるといえます。
【参考資料】:事業承継(中小企業庁)
M&Aを実施する理由とは?
企業や事業の合併・買収を「M&A(エムアンドエー)」といいます。
合併(Mergers)と買収( Acquisitions)の英語の頭文字をとって、M&Aと呼ばれています。
M&Aは、事業譲渡でも事業承継でも活用されるスキームです。
譲渡(売り手)側企業がM&Aで会社や事業を売却する目的はさまざまですが、主な理由としては次のことがあげられます。
後継者不在での事業承継
子供や親族などの後継者がいない場合に、第三者(他社)への事業承継のスキームとしてM&Aを活用。
自社の成長戦略
会社を成長させるために、大手企業の傘下に入ったり、PEファンドと手を組む際にM&Aを活用。
創業者利益の確保
創業した会社を売却し、創業者利益を確保する。
さらには、新たな事業を立ち上げる目的でM&Aを活用。
事業譲渡以外の手法について
企業の組織再編では、次の手法が使われることもあります。
株式譲渡
譲渡(売り手)側企業の株主が保有する株式を他社に売却し、譲受(買い手)側企業が経営権を引き継ぐ手法を株式譲渡といいます。
事業譲渡との違いとしては、次の点があげられます。
「経営権」
事業譲渡では会社の経営権は売り手に残るが、株式譲渡の場合は買い手に移る。
「契約関係」
事業譲渡では、買い手は各種契約について個別に、再度、締結する必要があるが、株式譲渡の場合はそのまま包括的に引き継ぐことができる。
「リスク関係」
事業譲渡では、買い手は売り手が抱える負債やリスクを引き継ぐ必要はないが、株式譲渡では簿外債務などのリスクを引き継ぐ可能性がある。
買い手としては、売り手の株式を取得することで経営権を引き継ぐことができますが、さまざまなリスクも考えながら実施するかどうかの検討をすることが重要になります。
会社分割
1つの会社を2つに切り離し、そのうちの片方を他の会社に吸収させるM&A手法を「会社分割」といい、次の2つのパターンがあります。
「吸収分割」
既存の企業に、分割した会社の一部を吸収させる。
「新設分割」
新しく設立した会社に、会社の一部を引き継がせる。
事業譲渡とは違い、会社分割の場合は、既存の契約関係は売り手から買い手へ引き継がれます。
そのため、取引先や従業員などとあらたに契約を締結する必要がない、というメリットがあります。
一方、会社法により、事業譲渡に比べて会社分割では厳格な手続きが規定されていることに注意が必要です。
事業譲渡のメリットとデメリットを解説
ここでは、譲渡(売り手)側企業と譲受(買い手)側企業に、どのようなメリット、デメリットがあるのか見ていきましょう。
事業譲渡のメリットと
デメリット
譲渡側(売り手)のメリット・デメリット
<メリット>
- ・株式譲渡とは違い、売り手に経営権が残るので、経営権を維持できる。
- ・特定の事業のみを譲渡(売却)できるので、残しておきたい事業は残せる。
- ・特定の事業の譲渡(売却)で得た対価(売却益)を他の事業や新規事業の立ち上げに投資できる。
- ・売り手は存続するので、取引先や従業員を維持したまま、売却益で経営の立て直しを図ることができる。
- ・事業の中の不採算部門は譲渡対象から除外できるため、買い手が見つかりやすい。
<デメリット>
・会社まるごとではなく、個別に事業を譲渡するため手続きが複雑になりがち。
※事業譲渡では、取引先との基本契約、賃貸借契約、従業員の雇用契約など、さまざまな契約を引き継ぐ必要があるため、取引先や関係者への個別の説明や交渉が必要になります。
・競業避止義務を負う。
※事業譲渡をした場合、その後、同じ事業を、一定の期間・地域で行なうことができません。
会社法では、買い手と同一の市町村、または隣接する市町村では、20年間の競業避止義務が規定されています(会社法第21条)。
・法人税の負担がかかる。
※事業譲渡は、個別の資産や権利等を譲渡するものですから、事業譲渡によって発生した利益に法人税等がかかります。
なお、個人株主の株式譲渡の場合の税率は約20%です。
譲受側(買い手)のメリット・デメリット
<メリット>
- ・会社まるごとではなく、必要な事業のみ譲受するため、投資額を抑えることができる。
- ・売り手の不採算事業など、必要ない事業を譲受ける必要がない。
- ・特定の事業のみ譲受けるため、売り手に紐づく税務リスクや負債などを引き継ぐ必要がない。
<デメリット>
・売り手の契約や許認可はそのまま引き継ぐことができないため、譲受後にあらためて手続きなどをする必要がある。
※たとえば、不動産を引き継ぐ場合は登記の移転手続きが必要です。
また、従業員とはあらためて個別に雇用契約を結ばなければいけないため、離職への対策も含めて説明や交渉も必要になります。
・消費税が課せられる。
※非課税資産(土地や有価証券など)を除き、事業譲渡の対象資産の取得に対しては消費税等を納税する必要があります。
・デューデリジェンス(DD)が必要になるため、費用と手間がかかる。
※M&Aを実施する際に、売り手の事業の適正な価値(金額)や、抱えているリスク等を正確に分析・把握するために買い手が費用を出し、法務・財務・税務・人事などの買収監査を行なう必要があり、これをデューデリジェンスといいます。
・会社のM&AにおけるDD
(デューディリジェンス)とは?
事業譲渡で必要な手続きを解説
次に、事業譲渡で必要になる基本的な手続きや流れ(フロー)について、概要を解説していきます。
譲渡(売り手)側と譲受側
(買い手)双方で、M&Aの
相手企業を選定
M&A仲介会社などを介して、譲渡(売り手)側企業は譲受(買い手)側企業の候補をリストアップ。
買い手は、交渉に入るかどうかの検討を行ないます。
秘密保持契約締結後に
トップ面談
売り手、買い手の双方で秘密保持契約を締結し、トップ面談などを行ないます。
その後は、基本合意契約に進みます。
デューデリジェンスの実施
買い手が、売り手に対してデューデリジェンスを実施します。
取締役会決議(取締役による
決定)
売り手、買い手の双方で取締役会決議等により、事業譲渡に関する基本的事項の決議を行ないます。
事業譲渡契約の締結
売り手、買い手の双方で事業譲渡契約の締結を行ないます。
株主への対応
- ・事業譲渡の効力発生日の20日前までに、株主への通知もしくは公告を行なう必要があります。
- ・株主総会の特別決議が必要な場合があります。
<売り手側>
譲渡する対象が、「事業の全部」、もしくは「事業の重要な一部(譲渡対象資産が買い手企業の総資産の5分の1超)」である場合は、事業譲渡日の前日までに株主総会による承認が必要になります。
<買い手側>
譲受する事業が、「他の会社の事業の全部」である場合、かつ「交付する財産が買い手企業の純資産の5分の1超」である場合には、事業譲渡日の前日までに株主総会による承認が必要になります。
なお、売り手と買い手それぞれの株主で、事業譲渡に反対する者がいる場合は、会社に対して公正な価格で保有株式の買取り請求をすることができます。
事業譲渡で課される税金について
事業譲渡では次のような税金が課されます。
譲渡(売り手)側企業に
課される税金
●法人税
●消費税・地方消費税等
- ・課税対象資産/営業権、有形固定資産(土地を除く)、無形固定資産、棚卸資産(商品・原材料の在庫など)
- ・非課税対象資産/土地、有価証券(株式など)、債権(売掛金など)
譲受(買い手)側企業に
課される税金
●不動産取得税
※譲渡対象資産に不動産が含まれている場合
●登録免許税
※譲渡対象資産に不動産が含まれている場合
M&Aで事業譲渡をする場合に知っておくべき3つの注意ポイント
事業譲渡では事業の相手方
(契約先)の承諾が必要
事業譲渡は、売り手と買い手の合意だけで成立させることはできません。
前述したように、取引先や従業員など相手方との契約について個別に承諾を得る必要があるのです。
仮に、ある取引先の承認が得られない場合、事業譲渡が成立したものの、その取引先との契約が譲渡(売り手)側企業に残ったままとなり、譲受(買い手)側企業にとってのメリットがなくなってしまいます。
また、従業員の大量離職が起きてしまえば、中身のない事業の箱だけを買ってしまうようなものになってしまい、事業運営に支障をきたす可能性もあります。
詐害行為取り消しに要注意!
民法には、「詐害行為取消権」が規定されています(第424条1項)。
詐害行為とは、債務者が債権者を害することを知りながら自己の財産を減少させる行為のことで、たとえば次のような行為が該当します。
- ・債務者が、債権の弁済ができなくなることを知りながら、責任財産を不当に流出させる。
- ・債務者が、一部の債権者に対してのみ、抜け駆けのように弁済する。
このような行為は、債権者に対する債務者の背信行為ともいえます。
そのため、債務超過の企業が事業譲渡を行なう場合は、事業(資産)の譲渡が詐害行為に該当するとして、債権者から事業譲渡の取り消しを請求されてしまわないように注意する必要があります。
対策としては、
- ・弁護士に相談・依頼して詐害行為に該当しないかを確認。
- ・公認会計士に依頼して、事業譲渡の対価(売却益)を客観的かつ適切に算出。
ということが重要になってきます。
従業員の整理解雇が不当解雇にならないように注意
事業譲渡の際に、従業員の一部を解雇しなければいけない局面もあると思います。
その場合、整理解雇が解雇権の濫用と判断されて不当解雇にならないように注意しなければいけません(労働契約法第16条)。
整理解雇が認められるには、次の4つの要素が必要とされています。
- ①整理解雇の必要性があること
- ②整理解雇回避のための努力を尽くしたこと
- ③解雇の人選基準が、客観的・合理的な基準であり、適正にその基準を運用したこと
- ④解雇の際、労働者への説明、協議を行うなど、解雇の手続きが妥当であること
これらの要件を満たすかどうかについては、事業譲渡やM&A、労働関係法に強い弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。
事業譲渡の相談は頼れる弁護士へ!
事業譲渡は、会社にとって非常に大きく重要な決断になります。
また、会社法や労働関係法などの法律が関係してきますし、法務デューデリジェンスも必要になってきます。
譲渡(売り手)側企業、譲受(買い手)側企業ともに事業譲渡を検討されている場合は弁護士への相談・依頼を検討してください。
みらい総合法律事務所は全国対応です。
関東圏だけでなく、地方の事業者の方からの無料相談も随時お受けしています(※事案によるので、まずはお問い合わせください)。
まずは一度、お気軽に、ご連絡ください。